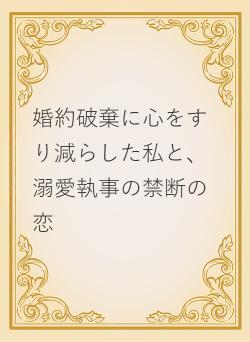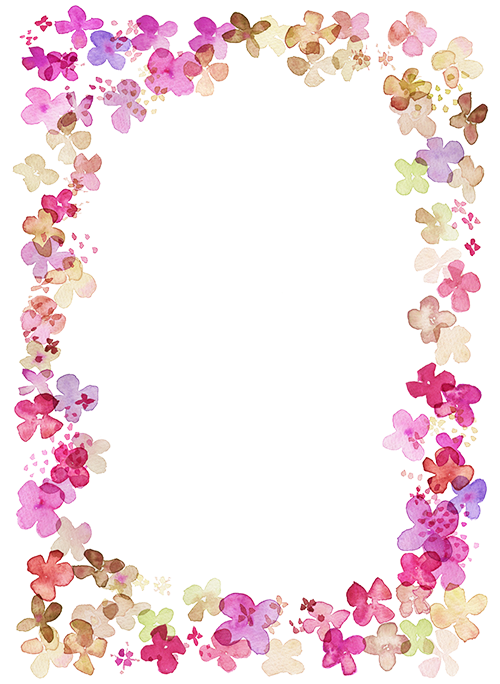だから目の前にいる自分よりも2歳年上の彼も、自分のことを嫌いになるなり、避けるなりしていくのだろう。
そんな風に感じていたが、現実は違った。
「ヴィオラっ! こっちに来てごらんっ! ほら、ダリヤの花が咲いている」
彼女の手を引いて、リーベルトは赤いダリヤの花のある花壇へと駆け寄っていく。
花に顔を近づけて匂いを嗅ぐと、目を閉じて微笑んだ。
「ダリヤの花言葉を知っているかい?」
「いいえ……」
「『華麗』というんだ。ふふ、君にぴったりだろう」
そう言って彼は笑った。
しかし、彼女は知っていたのだ。
ダリヤにはもう一つ裏の花言葉があることを……。
──『裏切り』
そうだ、きっと今はこんな風に親の指示で彼も自分に構っているだけだろう。
元々王立学院の同級生だった母親同士が結びつけた縁。
そこに自分の意思は必要ないし、きっとそこに心も、そして愛もない。
そうヴィオラは思っていた。
(きっと皆私の元からいなくなっていく。そして誰も私を愛してなどいない)
そうヴィオラ自身が思うのには理由があった。
そんな風に感じていたが、現実は違った。
「ヴィオラっ! こっちに来てごらんっ! ほら、ダリヤの花が咲いている」
彼女の手を引いて、リーベルトは赤いダリヤの花のある花壇へと駆け寄っていく。
花に顔を近づけて匂いを嗅ぐと、目を閉じて微笑んだ。
「ダリヤの花言葉を知っているかい?」
「いいえ……」
「『華麗』というんだ。ふふ、君にぴったりだろう」
そう言って彼は笑った。
しかし、彼女は知っていたのだ。
ダリヤにはもう一つ裏の花言葉があることを……。
──『裏切り』
そうだ、きっと今はこんな風に親の指示で彼も自分に構っているだけだろう。
元々王立学院の同級生だった母親同士が結びつけた縁。
そこに自分の意思は必要ないし、きっとそこに心も、そして愛もない。
そうヴィオラは思っていた。
(きっと皆私の元からいなくなっていく。そして誰も私を愛してなどいない)
そうヴィオラ自身が思うのには理由があった。