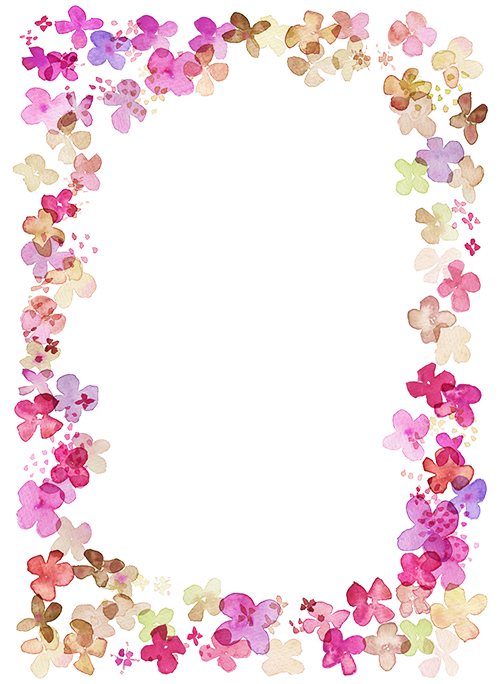自室へ向かうと、何やら騒がしい。自室の前で、スフィアとカイラが何か揉めていた。
「どうしたのっ」
慌てて駆け寄り、二人に割って入る。スフィアは漸く来たレティシアに詰め寄り、強い眼差しで睨み付けてきた。
「あんたに渡したドレスを返してって言ってるのよ! それをこの失礼なメイドが邪魔するし! ふざけないでよね!」
「ふざけてるのスフィアお嬢様の方です! 私はお嬢様が手直ししたドレスを寄越せと言われたからお断りしているだけですっ」
カイラの言葉に、レティシアは目を見開いた。何故、スフィアは私が手直ししたドレスを欲しているの――?
「いいから寄越しなさい! それとも、魔導公爵の妻になる私に歯向かうの?」
スフィアが欲している理由はわからない。だが、手直ししたドレスはたとえお下がりでもどれも思い入れがある。脅されようとも、手渡す訳にはいかなかった。
「スフィア、他のドレスは好きにしていいわ。でも手直ししたドレスだけは渡せない」
「はあ!?」
「それに、私のサイズに補修してあるドレスを渡してもあなたには直せないわ」
だから諦めて。そう告げると、顔を真っ赤にしながら肩を震わせた。
「『不良品』の癖に私に歯向かわないで! お父様に言ってやるわよ!」
「スフィア……」
どうして諦めてくれないのだろうか――。魔糸で補修してある以上、補修箇所を直すのにも解くのにも魔糸の魔力伝導の調整が必要になる。魔糸に魔力伝導の調整を施すと、強度や撓りがでる。だから魔糸は重宝されるのだ。だが、スフィアがドレスを直そうにも、レティシアが魔力伝導の調整を施した魔糸を解くのは職人でも難しい。魔糸の魔力伝導は施した人によって差異が生じる。魔糸で誂えたドレスというのはドレスを作った本人に直して貰うのが当たり前。魔糸の魔力伝導が上手く出来ないと、魔糸に込められている魔力が霧散してただの糸と同じになってしまうからである。レティシアは魔法の基礎である魔力探知や魔力操作しか出来ない。だがその分、魔力調整はお手の物だ。魔石生成も魔糸の調整も、一人で行い補修をしている。レティシアの手直しをカイラが手伝わないのはそれが理由だ。それだけ、魔糸の魔力伝導の調整というのは個性が際立つのである。
それくらいの初歩を、どうして理解してくれないのだろうか。
「こっちは忙しいの! さっさと渡しなさいよ!」
スフィアは怒りに身を任せ、魔力を放出させた。緑の炎のようにスフィアの周りに魔力が纏われる。レティシアの背後では、カイラも魔力を放出しだした。
「っ、二人とも、落ち着いて……っ」
このままでは、騒ぎが大きくなる。どうすれば――。
「スフィアお嬢様」
渡すしかないのか、そう思った瞬間、クラリックが表れた。レティシアはホッと安堵する。
「お時間が迫っています。早くお召し物を変えないと、魔導公爵様がお目見えになります」
「~~~~っ」
スフィアは振り返り、キッとレティシアを睨み付ける。
「絶対、お父さまに言いつけてやるから!」
そう言い、足早に自室へと戻っていった。レティシアはホッと一息吐き、クラリックに駆け寄る。
「ありがとう、クラリック。本当に助かったわ」
「私は事実を述べたまでですので、お気になさらず。それより……」
視線をカイラに向け、歩み寄るクラリック。未だスフィアの去った方向を見ながら魔力を放出しているカイラに、デコピンを食らわす。
「いったあっ!」
軽快な大きな音が響いた。カイラはハッと我に返り、レティシアに駆け寄った。
「お嬢様、大丈夫でしたか!?」
「大丈夫じゃないのはお前だ、カイラ」
クラリックの怒気の籠った声に、カイラが縮こまる。ゆっくり振り返るカイラに、クラリックは青筋を立てていた。
「スフィアお嬢様に向けて魔力を放出するなど、使用人としての意識が足りないぞ」
そう言いつつ詰め寄ってくるクラリックに、カイラは頬を膨らませる。
「私のご主人様はレティシアお嬢様だからいいのっ」
「そのお前の態度、行動からレティシアお嬢様に被害が及ばないとは考えないのか!」
クラリックの怒声に、カイラは言葉の意味を理解し青ざめる。すぐさま後ろを振り返り、レティシアに深く頭を垂れた。
「すみませんっ、お嬢様の為と思って……でも、お嬢様を危険にしちゃうなんて考えてもいなくてっ」
涙交じりに、カイラは何度も頭を下げてくる。レティシアはクラリックに視線を向ける。クラリックは深く溜息を吐くだけだ。その表情を見ると、すぐにカイラに視線を戻した。
「頭を上げて、カイラ」
そっと、カイラの肩に手を添える。大きく肩を震わせ、カイラはゆっくりと顔を上げた。
「私はいいの、大丈夫よ。でも私は私の所為でカイラが酷い目に遭うのは嫌だわ。だから、今回のようなことはしないで」
ね? とお願いするレティシアに、カイラは目に涙を溜め表情を歪ませながら何度も頷く。本当は主としてしっかりと怒る方が良いのかもしれない。でも、ずっと側に仕えてくれているカイラなら、これでわかってくれると、そう信じてる。だからこれでいい、良いのだ。
涙を堪えるカイラに、ハンカチを差し出しながら、レティシアは微笑む。
そんな二人を、クラリックは呆れながらも見つめていた。
「どうしたのっ」
慌てて駆け寄り、二人に割って入る。スフィアは漸く来たレティシアに詰め寄り、強い眼差しで睨み付けてきた。
「あんたに渡したドレスを返してって言ってるのよ! それをこの失礼なメイドが邪魔するし! ふざけないでよね!」
「ふざけてるのスフィアお嬢様の方です! 私はお嬢様が手直ししたドレスを寄越せと言われたからお断りしているだけですっ」
カイラの言葉に、レティシアは目を見開いた。何故、スフィアは私が手直ししたドレスを欲しているの――?
「いいから寄越しなさい! それとも、魔導公爵の妻になる私に歯向かうの?」
スフィアが欲している理由はわからない。だが、手直ししたドレスはたとえお下がりでもどれも思い入れがある。脅されようとも、手渡す訳にはいかなかった。
「スフィア、他のドレスは好きにしていいわ。でも手直ししたドレスだけは渡せない」
「はあ!?」
「それに、私のサイズに補修してあるドレスを渡してもあなたには直せないわ」
だから諦めて。そう告げると、顔を真っ赤にしながら肩を震わせた。
「『不良品』の癖に私に歯向かわないで! お父様に言ってやるわよ!」
「スフィア……」
どうして諦めてくれないのだろうか――。魔糸で補修してある以上、補修箇所を直すのにも解くのにも魔糸の魔力伝導の調整が必要になる。魔糸に魔力伝導の調整を施すと、強度や撓りがでる。だから魔糸は重宝されるのだ。だが、スフィアがドレスを直そうにも、レティシアが魔力伝導の調整を施した魔糸を解くのは職人でも難しい。魔糸の魔力伝導は施した人によって差異が生じる。魔糸で誂えたドレスというのはドレスを作った本人に直して貰うのが当たり前。魔糸の魔力伝導が上手く出来ないと、魔糸に込められている魔力が霧散してただの糸と同じになってしまうからである。レティシアは魔法の基礎である魔力探知や魔力操作しか出来ない。だがその分、魔力調整はお手の物だ。魔石生成も魔糸の調整も、一人で行い補修をしている。レティシアの手直しをカイラが手伝わないのはそれが理由だ。それだけ、魔糸の魔力伝導の調整というのは個性が際立つのである。
それくらいの初歩を、どうして理解してくれないのだろうか。
「こっちは忙しいの! さっさと渡しなさいよ!」
スフィアは怒りに身を任せ、魔力を放出させた。緑の炎のようにスフィアの周りに魔力が纏われる。レティシアの背後では、カイラも魔力を放出しだした。
「っ、二人とも、落ち着いて……っ」
このままでは、騒ぎが大きくなる。どうすれば――。
「スフィアお嬢様」
渡すしかないのか、そう思った瞬間、クラリックが表れた。レティシアはホッと安堵する。
「お時間が迫っています。早くお召し物を変えないと、魔導公爵様がお目見えになります」
「~~~~っ」
スフィアは振り返り、キッとレティシアを睨み付ける。
「絶対、お父さまに言いつけてやるから!」
そう言い、足早に自室へと戻っていった。レティシアはホッと一息吐き、クラリックに駆け寄る。
「ありがとう、クラリック。本当に助かったわ」
「私は事実を述べたまでですので、お気になさらず。それより……」
視線をカイラに向け、歩み寄るクラリック。未だスフィアの去った方向を見ながら魔力を放出しているカイラに、デコピンを食らわす。
「いったあっ!」
軽快な大きな音が響いた。カイラはハッと我に返り、レティシアに駆け寄った。
「お嬢様、大丈夫でしたか!?」
「大丈夫じゃないのはお前だ、カイラ」
クラリックの怒気の籠った声に、カイラが縮こまる。ゆっくり振り返るカイラに、クラリックは青筋を立てていた。
「スフィアお嬢様に向けて魔力を放出するなど、使用人としての意識が足りないぞ」
そう言いつつ詰め寄ってくるクラリックに、カイラは頬を膨らませる。
「私のご主人様はレティシアお嬢様だからいいのっ」
「そのお前の態度、行動からレティシアお嬢様に被害が及ばないとは考えないのか!」
クラリックの怒声に、カイラは言葉の意味を理解し青ざめる。すぐさま後ろを振り返り、レティシアに深く頭を垂れた。
「すみませんっ、お嬢様の為と思って……でも、お嬢様を危険にしちゃうなんて考えてもいなくてっ」
涙交じりに、カイラは何度も頭を下げてくる。レティシアはクラリックに視線を向ける。クラリックは深く溜息を吐くだけだ。その表情を見ると、すぐにカイラに視線を戻した。
「頭を上げて、カイラ」
そっと、カイラの肩に手を添える。大きく肩を震わせ、カイラはゆっくりと顔を上げた。
「私はいいの、大丈夫よ。でも私は私の所為でカイラが酷い目に遭うのは嫌だわ。だから、今回のようなことはしないで」
ね? とお願いするレティシアに、カイラは目に涙を溜め表情を歪ませながら何度も頷く。本当は主としてしっかりと怒る方が良いのかもしれない。でも、ずっと側に仕えてくれているカイラなら、これでわかってくれると、そう信じてる。だからこれでいい、良いのだ。
涙を堪えるカイラに、ハンカチを差し出しながら、レティシアは微笑む。
そんな二人を、クラリックは呆れながらも見つめていた。