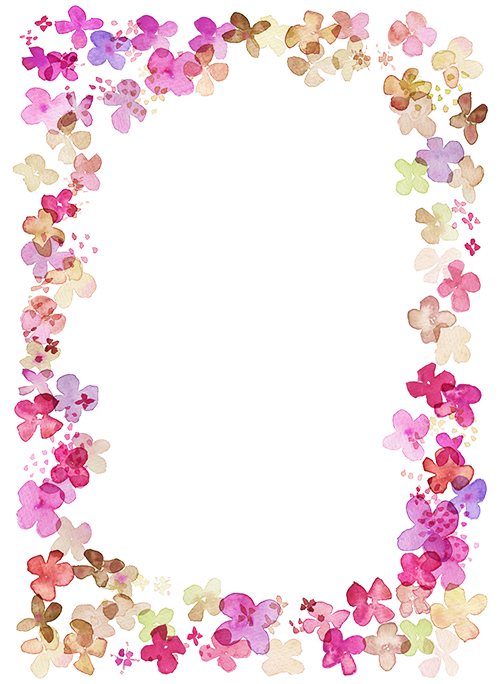クラリックが部屋を後にし、カイラと二人きりになる。そうなった瞬間、カイラは事あるごとに先程のことを聞いてきた。
「も~、本当に何を話してたんですか?」
唇を尖らせながら何度目も聞いてくるカイラに、レティシアは笑みを返すだけに留める。
「こればかりは内緒よ」
「クラリックの奴~っ、羨ましいっ」
不貞腐れるカイラに、レティシアは笑みを零した。こればかりはクラリックと私だけの内緒にさせてね、カイラ。
「今日の髪形は如何なさいます?」
髪を梳かれながら窺われる。今日は辛い日になる。ならばせめて、髪形だけでも自分の好きにして元気をだそう。そう思った。
「今日は編み込みのハーフアップにしてちょうだい。髪飾りは鈴蘭ので」
「はいっ」
香油を染み込ませながら、念入りに櫛で梳かれていく。所々で編み込まれ、後頭部で鈴蘭の髪留めで留めて貰う。化粧を薄く施し、赤と茶色のオーバー・チェック柄のシフォンワンピースへ袖を通す。
「よし、完成!」
「何時もありがとう」
お気に入りのシフォンタイプのワンピースに身を包み、カイラに礼を述べるとくるりと一回転して見せるレティシア。うん、気分だけでも上げていかねば。そう思いながらも、気が重いのは事実だ。どうしても、溜息が出てしまう。
「お嬢様……」
心配そうに見つめてくるカイラに、レティシアは大丈夫と微笑んだ。仕方ないのだ、受け入れるしかない、そう何度も自分に言い聞かせる。
時計を確認すると、朝食の時間ぴったりだ。カイラにこれ以上心配させてはなるまいと、笑顔を作りドアの方へと足を進める。
「さあ、お父様達の元へ行きましょう」
ドアを開け、室内を後にした。
朝食の間も、昨日同様、父と母、スフィアは魔導公爵の話で持ちっきりだった。中でもスフィアは先日会った魔導公爵の美貌の虜になってしまっているようで、終始頬が緩みきっていた。
「魔導公爵さま、いつ頃ここに来るの?」
朝食も終わり、食後の紅茶が運ばれてくる。会話に混ざることのないレティシアは、この家で飲む最後の紅茶の味を堪能しようとカップに口を付けた。
「九時には此方に着くとの話だ」
「やだっ、急いで身支度しなきゃ!」
急ぎ立ち上がり、スフィアは部屋を後にする。残った両親は、そんなスフィアを温かな眼差しで見送った。
「やれやれ、せわしい娘だ」
「そこがスフィアの可愛い所ではありませんか」
「そうだな」
レティシアには興味も向けず、スルグとユノアは談笑している。そんな二人に、レティシアはどうしようもないとわかっていても悲しさが湧き上がった。
「レティシア」
「っ、はい」
突然話しかけられ、レティシアはカップをソーサーに置き顔を上げる。見上げたスルグとユノアの顔は先程までとは打って変わり、険しい表情だった。
「魔導公爵が来る際、出迎えには参加しなさい」
「『不良品』といえど、我が家の一員です。ただし、スフィアよりも目立つことをしたら……わかりますね」
両親からの威圧的な視線に、レティシアは俯き身体を縮こませる。最後の日でも、両親は私を『不良品』と呼ぶのか――。
「……わかりました」
美味しかった筈の紅茶の味がわからなくなる。カップの残りを飲み干し、そっとその場を後にした。
「も~、本当に何を話してたんですか?」
唇を尖らせながら何度目も聞いてくるカイラに、レティシアは笑みを返すだけに留める。
「こればかりは内緒よ」
「クラリックの奴~っ、羨ましいっ」
不貞腐れるカイラに、レティシアは笑みを零した。こればかりはクラリックと私だけの内緒にさせてね、カイラ。
「今日の髪形は如何なさいます?」
髪を梳かれながら窺われる。今日は辛い日になる。ならばせめて、髪形だけでも自分の好きにして元気をだそう。そう思った。
「今日は編み込みのハーフアップにしてちょうだい。髪飾りは鈴蘭ので」
「はいっ」
香油を染み込ませながら、念入りに櫛で梳かれていく。所々で編み込まれ、後頭部で鈴蘭の髪留めで留めて貰う。化粧を薄く施し、赤と茶色のオーバー・チェック柄のシフォンワンピースへ袖を通す。
「よし、完成!」
「何時もありがとう」
お気に入りのシフォンタイプのワンピースに身を包み、カイラに礼を述べるとくるりと一回転して見せるレティシア。うん、気分だけでも上げていかねば。そう思いながらも、気が重いのは事実だ。どうしても、溜息が出てしまう。
「お嬢様……」
心配そうに見つめてくるカイラに、レティシアは大丈夫と微笑んだ。仕方ないのだ、受け入れるしかない、そう何度も自分に言い聞かせる。
時計を確認すると、朝食の時間ぴったりだ。カイラにこれ以上心配させてはなるまいと、笑顔を作りドアの方へと足を進める。
「さあ、お父様達の元へ行きましょう」
ドアを開け、室内を後にした。
朝食の間も、昨日同様、父と母、スフィアは魔導公爵の話で持ちっきりだった。中でもスフィアは先日会った魔導公爵の美貌の虜になってしまっているようで、終始頬が緩みきっていた。
「魔導公爵さま、いつ頃ここに来るの?」
朝食も終わり、食後の紅茶が運ばれてくる。会話に混ざることのないレティシアは、この家で飲む最後の紅茶の味を堪能しようとカップに口を付けた。
「九時には此方に着くとの話だ」
「やだっ、急いで身支度しなきゃ!」
急ぎ立ち上がり、スフィアは部屋を後にする。残った両親は、そんなスフィアを温かな眼差しで見送った。
「やれやれ、せわしい娘だ」
「そこがスフィアの可愛い所ではありませんか」
「そうだな」
レティシアには興味も向けず、スルグとユノアは談笑している。そんな二人に、レティシアはどうしようもないとわかっていても悲しさが湧き上がった。
「レティシア」
「っ、はい」
突然話しかけられ、レティシアはカップをソーサーに置き顔を上げる。見上げたスルグとユノアの顔は先程までとは打って変わり、険しい表情だった。
「魔導公爵が来る際、出迎えには参加しなさい」
「『不良品』といえど、我が家の一員です。ただし、スフィアよりも目立つことをしたら……わかりますね」
両親からの威圧的な視線に、レティシアは俯き身体を縮こませる。最後の日でも、両親は私を『不良品』と呼ぶのか――。
「……わかりました」
美味しかった筈の紅茶の味がわからなくなる。カップの残りを飲み干し、そっとその場を後にした。