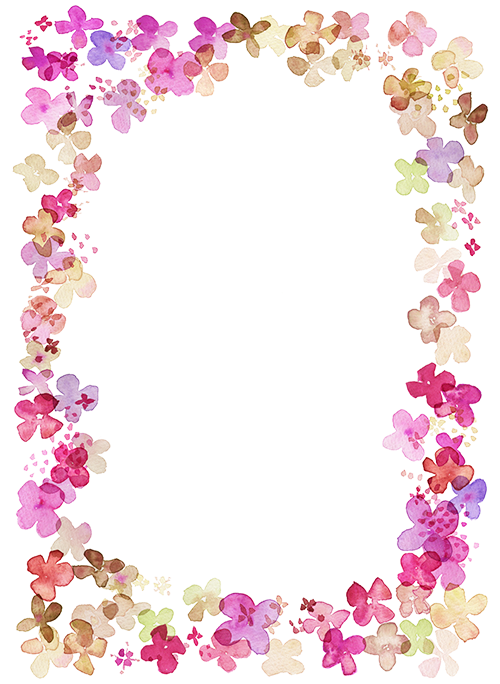その日は、あっという間にやってきた。ジャスミンとオリビアが丹精込めて作ってくれたドレスに身を包み、髪を結われティアラを付けられ、化粧を薄く施される。純白に包まれたレティシアを、双子デザイナーとカイラ、アティカは見つめた。
「お嬢様、綺麗です~っ」
涙ながらに言葉を述べるカイラに、レティシアは薄く口紅の塗られた唇の端を持ち上げ微笑んだ。
「ありがとう、カイラ」
「本当に綺麗です。レティシアお嬢様」
「アティカもありがとう。このドレスを作ってくださったジャスミンさんとオリビアさんのお陰よ」
そう答えるレティシアに、ジャスミンもオリビアも首を横に振った。
「そんなことないわ。レディ」
「そうよ。服は人を更に美しく見せるだけ。綺麗だというのなら、それは着ているレティシアちゃんが綺麗だからよ」
そう言ってくれる二人に、レティシアは「ありがとうございます」と笑みを向けた。
レティシアが身に纏うのは、Aラインのフレンチスリーブタイプのドレス。全体にあしらわれたエンブロイダリ―レースにはレティシアの作った魔糸を使用し、小さな薔薇がたくさん刺しゅうされている。ロングトレーンにも同様に薔薇の刺しゅうが施され、ふんわりと肩を覆うフレンチスリーブを含め、華やかにも可愛らしさを表現した一着となっている。アーム・ロングの手袋のレースの透け感が白磁のような白い肌のレティシアにぴったりだった。
「レティシアお嬢様、そろそろ……」
「そうね」
アティカの言葉に、オリビアとジャスミンが席を立つ。
「じゃあ、席に行ってるわっ」
「レディ、またね」
そう言って、二人は部屋から出て行った。カイラとアティカ、レティシアのみが部屋に残る。オリビア達と入れ替わるように、年老いた神父が入ってきた。
「では、お嬢様。私達も行っております」
「神父様、宜しくお願いいたします」
カイラとアティカ、二人も部屋から出て行く。神父にヴェールを掛けられると手を差し伸べられ、レティシアは皺の多い手にそっと自身の手を添え立ち上がる。
「緊張なさいますか?」
「少し……」
教会の中を歩きながら、神父に問われる。不安はない。でも、どうしても緊張だけは拭えない。大勢の人が教会に詰めかけている。その中を、セシリアスタの元まで歩かなければいけない。何度深呼吸しようが、緊張だけは拭い去ることが出来なかった。
「安心なさい。この老いぼれが共に歩きます。緊張なさらず、新郎の元に向かえばいいのです」
「神父様……」
神父の微笑みに、レティシアは少しずつ緊張が解れていく。ゆっくりと深呼吸をし、教会の扉の前に立つ。
「さあ、行きましょう」
「はい」
扉が開けられ、ゆっくりと、新郎の元へと歩き出した。
不安も、緊張も忘れ、神父様の手を取りゆっくりと歩く。神父様と共にセシル様の側までくると、神父様は所定の位置に着く。ヴェール越しに見るセシル様は、何処か驚いている様な、でも幸せそうな表情をうかべていた――。
「汝、セシリアスタ・ユグドラス。ここにレティシア・クォークを生涯愛すると誓うならば、この書に名を記しなさい」
神父の言葉の後、セシリアスタは神父の側にある魔道書に、その名を記していく。
「汝、レティシア・クォーク。ここにセシリアスタ・ユグドラスを生涯愛すると誓うならば、この書に名を記しなさい」
問われ、レティシアはセシリアスタ同様に魔道書へとその名を記した。魔道ペンで書かれた文字は、光を発し輝く。スッとセシリアアスタの隣に戻ると、再び神父は言葉を発する。
「魔導契約において、この婚姻を認めます。誓いを」
そう言われ、セシリアスタの方を向くレティシア。セシリアスタと向き合う形になったレティシアの左手を取り、薬指に指輪を嵌める。嵌めて貰った後、セシリアスタの指に同様に指輪を嵌めた。互いに生成した魔石の埋め込まれた指輪を嵌め、セシリアスタはレティシアのヴェールを取り、肩にそっと手を乗せた。
「レティシア。生涯を君に捧げよう」
「セシル様……」
そっとセシリアスタの顔が近付いてくる。レティシアはそっと瞼を閉じ、セシリアスタのキスを受け入れた。
静かに、涙が頬を伝った。
式の後、ユグドラス邸では盛大なパーティーが執り行われた。結婚式のお祝いもだが、レティシアの誕生日のお祝いも兼ねてのパーティーだ。レティシアは新緑色のマーメイド・ドレスに身を包み、セシリアスタと共に挨拶やお祝いの言葉をかけてくれる人達に挨拶をしていく。
「やあ、結婚おめでとう」
「イザークさん」
周りとは違い、白を基調とした正装を着たイザークが近付いてくる。そう言えば、とレティシアは疑問を投げかけた。
「イザークさんだけ、格好が違いますが……もしかして、イザークさんは特別な方なのですか?」
レティシアの疑問に、イザークは目を瞬かせ、肩を震わせ笑い出す。隣にいたエドワースはやれやれと肩を落とした。
「えっと……イザークさん?」
「あはは、ごめんごめん。ここまで気付かなかったなんて、逆に驚いちゃってさ」
そう言いながら、イザークは「改めまして」と姿勢を正した。
「アイザック・フェオール・グリスタニア。このグリスタニアの第三王子ってやつだよ」
衝撃の事実に、レティシアは目を見開く。今まで普通に接していた人が、まさかこの国の王子だったなんて――。
「す、すみません殿下っ」
「いいのいいの。気にしないで。何時ものようにイザークって呼んでよ」
呑気に話すイザークに、レティシアはセシリアスタを見上げる。セシリアスタは言葉を発した。
「本人がそう言っているんだ。そう呼んでやれ」
「は、はい……」
頷き、イザークの方を見る。イザークは「これからも宜しくね」と微笑んだ。
夕刻、パーティーも終わり、湯あみをこれでもかと丁寧に済まされると、カイラとアティカに今まで使用してこなかったセシリアスタの部屋とを繋ぐドアへと押しやられた。
「ふ、二人とも、どうしたの?」
「今日はそっちで寝てくださいっ」
にっと笑顔で背中を押すカイラに、首を傾げるしかないレティシア。そんなレティシアを見ながら、アティカはドアを開けた。
「では、お休みなさいませ」
「おやすみなさい、お嬢様」
静かにドアを閉められ、レティシアはセシリアスタの寝室へと足を踏み入れることとなってしまった。シンプルながら綺麗に片付けられた部屋はセシリアスタの焚く香の香りが充満しており、思わずドキドキしてしまう。
(ここが、セシル様のベッド……)
ベッドに近付くと、更に匂いが増していく。思わず布団に顔を埋めたくなってしまうが、それははしたないと我慢する。
「……レティシア?」
突然背後からかけられた声に、レティシアは肩を震わす。恐る恐る振り返ると、バスローブ姿のセシリアスタが立っていた。鎖骨から胸元に流れる汗に、思わずコクリと喉が鳴ってしまう。そうだ、結婚したのだから、初夜を迎えなければいけないのだ。だから、丁寧に体を磨かれ、こんな可愛らしいネグリジェを着せられたのか――。そこでふと、自身の格好に気付く。「セクシーさも可愛らしさもどちらも捉えたわよっ」と言っていたジャスミンの言葉通り、可愛らしいレースたっぷりの上着に、局部の部分以外はレースで出来たパンツ。レティシアは恥ずかしくなり、手で出来る限り覆った。
「その格好……」
「その、ジャスミンさんが、今日の為にと用意してくれたものでっ、えっと……っ」
恥ずかしくて涙交じりに早口で答えるレティシア。セシリアスタを見上げると、セシリアスタの喉が上下に動いたのが見えた。
「セシル、様……?」
レティシアの言葉に我に返ったセシリアスタは、レティシアに着ていたバスローブを羽織らせた。
「私はソファで寝る。君はベッドを使いなさい」
「でも……っ」
突然の言葉に、レティシアは動揺する。恥ずかしがってはいたが、今日は初夜を迎えねばならない。どうしてそんなことを言うのだろう?
「……私、そんなに魅力ないでしょうか?」
涙ながらに呟くレティシアに、セシリアスタは慌てて返答する。
「そんなことはない」
「でも、ならどうして抱いてはくださらないのですかっ」
下唇を噛み締めながら、レティシアはセシリアスタを見上げる。ぎゅっと羽織らせてもらったバスローブを掴み、言葉を続ける。
「結婚したのですから、私達はもう夫婦です。セシル様には沢山のことをして貰ってますが……夫婦の営みも、して欲しいです……」
言いながら恥ずかしくなり、顔を俯かせるレティシア。そんなレティシアの元に、セシリアスタは足早に近付いてきた。
「レティシア」
名を呼ばれ、横抱きに抱き上げられる。涙の溜まった目尻にキスを落とされ、頬が紅潮する。
「女性である君に気を使わせてしまったな……済まない」
「いいえ。大丈夫です、セシル様」
そっとベッドに下ろされ、セシリアスタがにじり寄ってくる。髪を一房、摘まみ上げるとそこに唇を落とした。
「……いいんだな?」
最後の確認のように、セシリアスタは訊ねる。レティシアは頷き、両手を広げた。
「はい、来てください……セシル様」
微笑みながら、セシリアスタを受け入れる。セシリアスタはレティシアを抱き締め唇を重ねると、そっとベッドに横たえた。
「そういえば、あの時のは魔法だったのでしょうか……?」
気だるげにセシリアスタの胸に背を預けながら、レティシアは訊ねる。セシリアスタはレティシアの髪を梳きながら考え、言葉を発した。
「恐らくはそうだろう。あれから魔法は?」
「全くです」
苦笑しながら答えるレティシアに、セシリアスタは微笑みかける。そう、あの時の光の柱を形成した以来、全く使えないのだ。
「レティシア、昼間話すのを躊躇ったのだが……君の家族の処遇が決まった」
その言葉に、息を飲む。家族は、どうなるのだろう――。
「三人とも魔法封じの首輪を義務づけることが決まった。スルグ・クォークは尋問の後、セグスタ領の炭鉱に収監される。したことが大きいからな……ユノア・クォークとスフィア・クォークはガルクト領の別々の修道院に送られる」
魔法封じの首輪。一見、綺麗なアクセサリーのように見えるが、大気中のマナとの干渉を封じる魔道具だ。そして、何よりこの魔法封じの首輪は、付けられると一生外すことは出来ない罪人の証だ。また、ガルクト領というのはとても厳しい戒律のある修道院が多く点在することで有名でもある。そこで一生、二人は罪人としてのレッテルを貼られ生涯を送ることとなる。
父が送られるセグスタ領の炭鉱も、主に大きな罪を侵した罪人が送られる収容所だ。炭鉱で魔法が使えない中、一生をそこで炭鉱夫として重労働を課せられ過ごしていくことになるのだろう。
「……済まない。こんな時に言う話題ではなかった」
暗い表情を浮かべながら背後から抱き締められ、レティシアは「いいえ」と首を振る。
「セシル様はちゃんと教えてくださいました。私は、それで十分です」
だから、そんな顔をしないで欲しい――。そう思いながら微笑み返すと、セシリアスタは抱き締める腕に力を籠めた。
背中から伝わるセシリアスタの温もりが、落ち込んだ心を癒してくれる。それだけで、今は十分だった。
「今度、カイラ達と共に教会に礼拝に行ってもいいですか?」
「礼拝?」
「ええ。魔力の質を高めたいのです」
サグサに言われた通り、魔力の容量を確保したい。レティシアがそう言うと、セシリアスタは「構わないよ」と了承してくれた。
あの一回以降、私は魔法は相変わらず使えない『不良品』のままだ。セシル様達はそんなことはないと否定してくれるが、長年そう思ってきた自分の考えを変えるのは容易ではない。だが、それでもいいと言ってくださる。それでも愛してくださる人がいる。
「レティシア。愛しているよ」
「私もです、セシル様」
今はそれで十分だ。そう、レティシアは思い、セシリアスタの胸に体を預けた。
「お嬢様、綺麗です~っ」
涙ながらに言葉を述べるカイラに、レティシアは薄く口紅の塗られた唇の端を持ち上げ微笑んだ。
「ありがとう、カイラ」
「本当に綺麗です。レティシアお嬢様」
「アティカもありがとう。このドレスを作ってくださったジャスミンさんとオリビアさんのお陰よ」
そう答えるレティシアに、ジャスミンもオリビアも首を横に振った。
「そんなことないわ。レディ」
「そうよ。服は人を更に美しく見せるだけ。綺麗だというのなら、それは着ているレティシアちゃんが綺麗だからよ」
そう言ってくれる二人に、レティシアは「ありがとうございます」と笑みを向けた。
レティシアが身に纏うのは、Aラインのフレンチスリーブタイプのドレス。全体にあしらわれたエンブロイダリ―レースにはレティシアの作った魔糸を使用し、小さな薔薇がたくさん刺しゅうされている。ロングトレーンにも同様に薔薇の刺しゅうが施され、ふんわりと肩を覆うフレンチスリーブを含め、華やかにも可愛らしさを表現した一着となっている。アーム・ロングの手袋のレースの透け感が白磁のような白い肌のレティシアにぴったりだった。
「レティシアお嬢様、そろそろ……」
「そうね」
アティカの言葉に、オリビアとジャスミンが席を立つ。
「じゃあ、席に行ってるわっ」
「レディ、またね」
そう言って、二人は部屋から出て行った。カイラとアティカ、レティシアのみが部屋に残る。オリビア達と入れ替わるように、年老いた神父が入ってきた。
「では、お嬢様。私達も行っております」
「神父様、宜しくお願いいたします」
カイラとアティカ、二人も部屋から出て行く。神父にヴェールを掛けられると手を差し伸べられ、レティシアは皺の多い手にそっと自身の手を添え立ち上がる。
「緊張なさいますか?」
「少し……」
教会の中を歩きながら、神父に問われる。不安はない。でも、どうしても緊張だけは拭えない。大勢の人が教会に詰めかけている。その中を、セシリアスタの元まで歩かなければいけない。何度深呼吸しようが、緊張だけは拭い去ることが出来なかった。
「安心なさい。この老いぼれが共に歩きます。緊張なさらず、新郎の元に向かえばいいのです」
「神父様……」
神父の微笑みに、レティシアは少しずつ緊張が解れていく。ゆっくりと深呼吸をし、教会の扉の前に立つ。
「さあ、行きましょう」
「はい」
扉が開けられ、ゆっくりと、新郎の元へと歩き出した。
不安も、緊張も忘れ、神父様の手を取りゆっくりと歩く。神父様と共にセシル様の側までくると、神父様は所定の位置に着く。ヴェール越しに見るセシル様は、何処か驚いている様な、でも幸せそうな表情をうかべていた――。
「汝、セシリアスタ・ユグドラス。ここにレティシア・クォークを生涯愛すると誓うならば、この書に名を記しなさい」
神父の言葉の後、セシリアスタは神父の側にある魔道書に、その名を記していく。
「汝、レティシア・クォーク。ここにセシリアスタ・ユグドラスを生涯愛すると誓うならば、この書に名を記しなさい」
問われ、レティシアはセシリアスタ同様に魔道書へとその名を記した。魔道ペンで書かれた文字は、光を発し輝く。スッとセシリアアスタの隣に戻ると、再び神父は言葉を発する。
「魔導契約において、この婚姻を認めます。誓いを」
そう言われ、セシリアスタの方を向くレティシア。セシリアスタと向き合う形になったレティシアの左手を取り、薬指に指輪を嵌める。嵌めて貰った後、セシリアスタの指に同様に指輪を嵌めた。互いに生成した魔石の埋め込まれた指輪を嵌め、セシリアスタはレティシアのヴェールを取り、肩にそっと手を乗せた。
「レティシア。生涯を君に捧げよう」
「セシル様……」
そっとセシリアスタの顔が近付いてくる。レティシアはそっと瞼を閉じ、セシリアスタのキスを受け入れた。
静かに、涙が頬を伝った。
式の後、ユグドラス邸では盛大なパーティーが執り行われた。結婚式のお祝いもだが、レティシアの誕生日のお祝いも兼ねてのパーティーだ。レティシアは新緑色のマーメイド・ドレスに身を包み、セシリアスタと共に挨拶やお祝いの言葉をかけてくれる人達に挨拶をしていく。
「やあ、結婚おめでとう」
「イザークさん」
周りとは違い、白を基調とした正装を着たイザークが近付いてくる。そう言えば、とレティシアは疑問を投げかけた。
「イザークさんだけ、格好が違いますが……もしかして、イザークさんは特別な方なのですか?」
レティシアの疑問に、イザークは目を瞬かせ、肩を震わせ笑い出す。隣にいたエドワースはやれやれと肩を落とした。
「えっと……イザークさん?」
「あはは、ごめんごめん。ここまで気付かなかったなんて、逆に驚いちゃってさ」
そう言いながら、イザークは「改めまして」と姿勢を正した。
「アイザック・フェオール・グリスタニア。このグリスタニアの第三王子ってやつだよ」
衝撃の事実に、レティシアは目を見開く。今まで普通に接していた人が、まさかこの国の王子だったなんて――。
「す、すみません殿下っ」
「いいのいいの。気にしないで。何時ものようにイザークって呼んでよ」
呑気に話すイザークに、レティシアはセシリアスタを見上げる。セシリアスタは言葉を発した。
「本人がそう言っているんだ。そう呼んでやれ」
「は、はい……」
頷き、イザークの方を見る。イザークは「これからも宜しくね」と微笑んだ。
夕刻、パーティーも終わり、湯あみをこれでもかと丁寧に済まされると、カイラとアティカに今まで使用してこなかったセシリアスタの部屋とを繋ぐドアへと押しやられた。
「ふ、二人とも、どうしたの?」
「今日はそっちで寝てくださいっ」
にっと笑顔で背中を押すカイラに、首を傾げるしかないレティシア。そんなレティシアを見ながら、アティカはドアを開けた。
「では、お休みなさいませ」
「おやすみなさい、お嬢様」
静かにドアを閉められ、レティシアはセシリアスタの寝室へと足を踏み入れることとなってしまった。シンプルながら綺麗に片付けられた部屋はセシリアスタの焚く香の香りが充満しており、思わずドキドキしてしまう。
(ここが、セシル様のベッド……)
ベッドに近付くと、更に匂いが増していく。思わず布団に顔を埋めたくなってしまうが、それははしたないと我慢する。
「……レティシア?」
突然背後からかけられた声に、レティシアは肩を震わす。恐る恐る振り返ると、バスローブ姿のセシリアスタが立っていた。鎖骨から胸元に流れる汗に、思わずコクリと喉が鳴ってしまう。そうだ、結婚したのだから、初夜を迎えなければいけないのだ。だから、丁寧に体を磨かれ、こんな可愛らしいネグリジェを着せられたのか――。そこでふと、自身の格好に気付く。「セクシーさも可愛らしさもどちらも捉えたわよっ」と言っていたジャスミンの言葉通り、可愛らしいレースたっぷりの上着に、局部の部分以外はレースで出来たパンツ。レティシアは恥ずかしくなり、手で出来る限り覆った。
「その格好……」
「その、ジャスミンさんが、今日の為にと用意してくれたものでっ、えっと……っ」
恥ずかしくて涙交じりに早口で答えるレティシア。セシリアスタを見上げると、セシリアスタの喉が上下に動いたのが見えた。
「セシル、様……?」
レティシアの言葉に我に返ったセシリアスタは、レティシアに着ていたバスローブを羽織らせた。
「私はソファで寝る。君はベッドを使いなさい」
「でも……っ」
突然の言葉に、レティシアは動揺する。恥ずかしがってはいたが、今日は初夜を迎えねばならない。どうしてそんなことを言うのだろう?
「……私、そんなに魅力ないでしょうか?」
涙ながらに呟くレティシアに、セシリアスタは慌てて返答する。
「そんなことはない」
「でも、ならどうして抱いてはくださらないのですかっ」
下唇を噛み締めながら、レティシアはセシリアスタを見上げる。ぎゅっと羽織らせてもらったバスローブを掴み、言葉を続ける。
「結婚したのですから、私達はもう夫婦です。セシル様には沢山のことをして貰ってますが……夫婦の営みも、して欲しいです……」
言いながら恥ずかしくなり、顔を俯かせるレティシア。そんなレティシアの元に、セシリアスタは足早に近付いてきた。
「レティシア」
名を呼ばれ、横抱きに抱き上げられる。涙の溜まった目尻にキスを落とされ、頬が紅潮する。
「女性である君に気を使わせてしまったな……済まない」
「いいえ。大丈夫です、セシル様」
そっとベッドに下ろされ、セシリアスタがにじり寄ってくる。髪を一房、摘まみ上げるとそこに唇を落とした。
「……いいんだな?」
最後の確認のように、セシリアスタは訊ねる。レティシアは頷き、両手を広げた。
「はい、来てください……セシル様」
微笑みながら、セシリアスタを受け入れる。セシリアスタはレティシアを抱き締め唇を重ねると、そっとベッドに横たえた。
「そういえば、あの時のは魔法だったのでしょうか……?」
気だるげにセシリアスタの胸に背を預けながら、レティシアは訊ねる。セシリアスタはレティシアの髪を梳きながら考え、言葉を発した。
「恐らくはそうだろう。あれから魔法は?」
「全くです」
苦笑しながら答えるレティシアに、セシリアスタは微笑みかける。そう、あの時の光の柱を形成した以来、全く使えないのだ。
「レティシア、昼間話すのを躊躇ったのだが……君の家族の処遇が決まった」
その言葉に、息を飲む。家族は、どうなるのだろう――。
「三人とも魔法封じの首輪を義務づけることが決まった。スルグ・クォークは尋問の後、セグスタ領の炭鉱に収監される。したことが大きいからな……ユノア・クォークとスフィア・クォークはガルクト領の別々の修道院に送られる」
魔法封じの首輪。一見、綺麗なアクセサリーのように見えるが、大気中のマナとの干渉を封じる魔道具だ。そして、何よりこの魔法封じの首輪は、付けられると一生外すことは出来ない罪人の証だ。また、ガルクト領というのはとても厳しい戒律のある修道院が多く点在することで有名でもある。そこで一生、二人は罪人としてのレッテルを貼られ生涯を送ることとなる。
父が送られるセグスタ領の炭鉱も、主に大きな罪を侵した罪人が送られる収容所だ。炭鉱で魔法が使えない中、一生をそこで炭鉱夫として重労働を課せられ過ごしていくことになるのだろう。
「……済まない。こんな時に言う話題ではなかった」
暗い表情を浮かべながら背後から抱き締められ、レティシアは「いいえ」と首を振る。
「セシル様はちゃんと教えてくださいました。私は、それで十分です」
だから、そんな顔をしないで欲しい――。そう思いながら微笑み返すと、セシリアスタは抱き締める腕に力を籠めた。
背中から伝わるセシリアスタの温もりが、落ち込んだ心を癒してくれる。それだけで、今は十分だった。
「今度、カイラ達と共に教会に礼拝に行ってもいいですか?」
「礼拝?」
「ええ。魔力の質を高めたいのです」
サグサに言われた通り、魔力の容量を確保したい。レティシアがそう言うと、セシリアスタは「構わないよ」と了承してくれた。
あの一回以降、私は魔法は相変わらず使えない『不良品』のままだ。セシル様達はそんなことはないと否定してくれるが、長年そう思ってきた自分の考えを変えるのは容易ではない。だが、それでもいいと言ってくださる。それでも愛してくださる人がいる。
「レティシア。愛しているよ」
「私もです、セシル様」
今はそれで十分だ。そう、レティシアは思い、セシリアスタの胸に体を預けた。