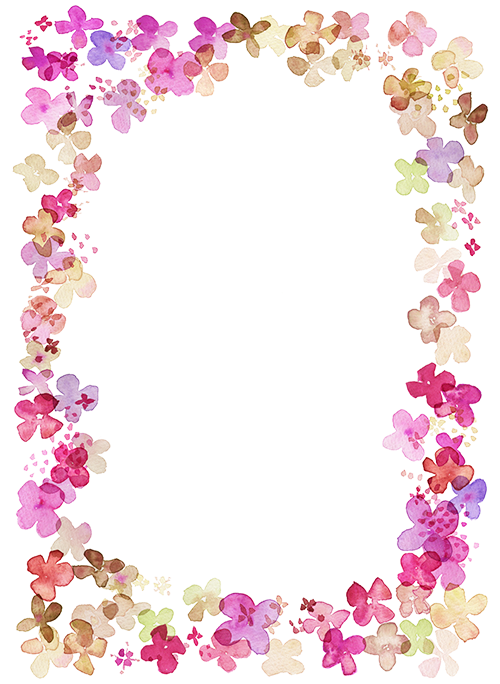ディシアドとディアナの後に続き、屋敷の中を歩いていくレティシアとセシリアスタ。客間と思しき部屋に着くと、ディシアドはドアを開けた。
「わあ……」
テーブルの上には、ドリンクと可愛らしいティースタンド、アミューズが置かれていた。ティースタンドにはサンドイッチやスコーン、色とりどりのデザートがふんだんに乗せられており、レティシアの食欲をそそった。
香り豊かな紅茶の匂いも部屋いっぱいに広がっている。
「さあ、座って」
「は、はいっ」
ディシアドの言葉の後、使用人に椅子を引かれ、レティシアは席に着く。近づくと仄かな果物の香りが鼻腔を擽った。
「それじゃあ、乾杯!」
ディアナの掛け声に合わせ、カップを軽く持ち上げ乾杯をした。
「セシル、生活はどうだい?」
「普通です」
ディシアドに簡単に話すセシリアスタを見ながら、レティシアは向かいに座るディアナを見やる。綺麗にナイフとフォークを使いサンドイッチを食べる姿は、同性のレティシアでも綺麗だと思えた。
「お味、いかがかしら?」
「はい、とても美味しいです」
小さく切り分けながら、サンドイッチを口に運ぶ。ハムとチーズの香ばしさが口いっぱいに広がり、思わず顔が綻びそうになる。そんなレティシアを、ディアナは微笑ましく見ていた。
「レティシア嬢、君はセシルの所に来て、どのくらい経ったんだい?」
「一ヶ月になりました」
ディシアドの問いに、レティシアは微笑みながら答える。その言葉を聞き、ディアナが尋ねてくる。
「となると……成人まではまだかかるの?」
「後三週間あります」
そう、レティシアは後三週間で成人を迎えるのだ。そうしたら、はれてレティシアはユグドラスの姓を名乗れることとなる。
「そういえば、ディシアド様とセシル様はご兄弟ですが、名字が違うのはどうしてでしょうか?」
「私が公爵の爵位を賜った際、国王陛下から新たに家名を授かったんだ」
「そうだったんですね」
知らなかった――。セシリアスタの言葉に、レティシアは驚く。そんなレティシアに、ディアナは抱き着いた。
「ああ、もうっ! 早く結婚してほしいわ!」
「きゃっ」
「こらディアナ、行儀が悪いぞ」
そう言いながら微笑むディシアドに、ディアナは「だって」と頬を膨らます。
「こんなに可愛い子、早く妹になって欲しいんだもの! セシル、どうやってこんな可愛い子を見付けたのよっ」
急に話を振られて、戸惑うセシリアスタ。そんなセシリアスタの代わりに、レティシアが言葉を発する。
「セシル様のパーティーに参加した際に、セシル様にお声を掛けていただいたんです」
本当は、妹のおまけだったのだが……敢えて言わないでおこう――。
そう言うと、何故かディシアドは目を瞬かせ、隣に座るディアナはにっと笑顔を浮かべた。
「セシル、やるじゃないっ」
「……ノーコメントで」
そう言って、紅茶のカップを口に運ぶセシリアスタ。レティシアは微笑ましい光景に、笑顔を浮かべた。
デザートの木苺をふんだんに使ったタルトに舌鼓を打ちつつ談笑を交わしていく。セシリアスタも時々返事を返しながら、お茶会を楽しんでいた。
「セシル、ちょっといいかい?」
「はい」
席を立ち、ディシアドがセシリアスタを別の部屋に連れて行く。ディアナと二人きりになったレティシアは、何を話せばいいか悩んだ。
(どうしましょう……私から話しかけるのは失礼に値するかもしれないし……)
悩むレティシア。そんなレティシアを見かねて、ディアナは話しかけてきた。
「ねえ、レティシアちゃん、セシルとの出会い、もっと詳しく話しを聞かせて頂戴な」
「は、はいっ」
ディアナの気遣いに感謝しつつ、レティシアは一ヶ月前のあの日のことを思い出した。
「ディアナ様もご存知かと思いますが、私は魔法の使えない『不良品』なんです。セシル様のパーティーにも、妹のおまけで参加したんです。そんな時、セシル様だけが、私に話しかけてくださいました」
レティシアの言葉を、ディアナは静かに聞いていく。レティシアはそのまま言葉を続けた。
「どんな方も、私を見ると去って行きました。ですが、セシル様だけが、私に話しかけてくださり、会話をして下さいました。その時、セシル様が婚約者にと話してくださったんです」
最初は冗談だと思い、信じていなかった。だが、向けられる視線が嘘を言っているとも思えなかった。
「本気で、私を婚約者にしてくださると言ってくださり、嬉しかったです。でもその時、私には既に婚約が決められかけていて……でもセシル様は約束だと、必ず迎えに行くと言ってくださり、本当に迎えに来てくださいました。それが何よりも嬉しかったです」
ハッとし、話が逸れてしまったことに気付く。慌ててディアナに謝罪をする。
「すみませんっ、話が逸れてしまって……」
「構わないわ。でもレティシアちゃん、一つだけ、文句を言わさせて頂戴」
「はい……」
何だろうか――。少しだけ表情の険しくなったディアナに、レティシアは体を竦めた。
「自分のことを『不良品』なんて、言っては絶対にダメ」
「え?」
思いもよらなかった言葉に、レティシアは目を瞬かせる。ディアナは溜息を吐きながら、レティシアに指を突き出した。
「ずっとそんな風に言われてきたのね……だからそんな風に自分を卑下してしまうのよ。でもね、ここにはあなたを『不良品』だなんて思っている人は居ないわ。自分に自信を持ちなさいっ」
その言葉に、レティシアは困惑する。今までずっと、『不良品』と家族からも周りからも言われ続けてきた。今更、自分は『不良品』じゃない。だなんて、思える訳がない。
「あなたは、セシルが選んだ婚約者なのよ。もっと自信を持ちなさいな」
そうだ。自分は『不良品』だ。だが、セシル様が選んでくれたのだ。
「……今すぐは無理ですが、少しずつ、努力してみます」
「うん! 偉いわっ、レティシアちゃん!」
レティシアの言葉に、ディアナはぎゅっと抱き締めた。誰かにこうして抱き締められるなんて、今までなかったことだ。今は本当に幸せだ――。そう思いながら、レティシアはディアナの背にそっと手を回した。
「わあ……」
テーブルの上には、ドリンクと可愛らしいティースタンド、アミューズが置かれていた。ティースタンドにはサンドイッチやスコーン、色とりどりのデザートがふんだんに乗せられており、レティシアの食欲をそそった。
香り豊かな紅茶の匂いも部屋いっぱいに広がっている。
「さあ、座って」
「は、はいっ」
ディシアドの言葉の後、使用人に椅子を引かれ、レティシアは席に着く。近づくと仄かな果物の香りが鼻腔を擽った。
「それじゃあ、乾杯!」
ディアナの掛け声に合わせ、カップを軽く持ち上げ乾杯をした。
「セシル、生活はどうだい?」
「普通です」
ディシアドに簡単に話すセシリアスタを見ながら、レティシアは向かいに座るディアナを見やる。綺麗にナイフとフォークを使いサンドイッチを食べる姿は、同性のレティシアでも綺麗だと思えた。
「お味、いかがかしら?」
「はい、とても美味しいです」
小さく切り分けながら、サンドイッチを口に運ぶ。ハムとチーズの香ばしさが口いっぱいに広がり、思わず顔が綻びそうになる。そんなレティシアを、ディアナは微笑ましく見ていた。
「レティシア嬢、君はセシルの所に来て、どのくらい経ったんだい?」
「一ヶ月になりました」
ディシアドの問いに、レティシアは微笑みながら答える。その言葉を聞き、ディアナが尋ねてくる。
「となると……成人まではまだかかるの?」
「後三週間あります」
そう、レティシアは後三週間で成人を迎えるのだ。そうしたら、はれてレティシアはユグドラスの姓を名乗れることとなる。
「そういえば、ディシアド様とセシル様はご兄弟ですが、名字が違うのはどうしてでしょうか?」
「私が公爵の爵位を賜った際、国王陛下から新たに家名を授かったんだ」
「そうだったんですね」
知らなかった――。セシリアスタの言葉に、レティシアは驚く。そんなレティシアに、ディアナは抱き着いた。
「ああ、もうっ! 早く結婚してほしいわ!」
「きゃっ」
「こらディアナ、行儀が悪いぞ」
そう言いながら微笑むディシアドに、ディアナは「だって」と頬を膨らます。
「こんなに可愛い子、早く妹になって欲しいんだもの! セシル、どうやってこんな可愛い子を見付けたのよっ」
急に話を振られて、戸惑うセシリアスタ。そんなセシリアスタの代わりに、レティシアが言葉を発する。
「セシル様のパーティーに参加した際に、セシル様にお声を掛けていただいたんです」
本当は、妹のおまけだったのだが……敢えて言わないでおこう――。
そう言うと、何故かディシアドは目を瞬かせ、隣に座るディアナはにっと笑顔を浮かべた。
「セシル、やるじゃないっ」
「……ノーコメントで」
そう言って、紅茶のカップを口に運ぶセシリアスタ。レティシアは微笑ましい光景に、笑顔を浮かべた。
デザートの木苺をふんだんに使ったタルトに舌鼓を打ちつつ談笑を交わしていく。セシリアスタも時々返事を返しながら、お茶会を楽しんでいた。
「セシル、ちょっといいかい?」
「はい」
席を立ち、ディシアドがセシリアスタを別の部屋に連れて行く。ディアナと二人きりになったレティシアは、何を話せばいいか悩んだ。
(どうしましょう……私から話しかけるのは失礼に値するかもしれないし……)
悩むレティシア。そんなレティシアを見かねて、ディアナは話しかけてきた。
「ねえ、レティシアちゃん、セシルとの出会い、もっと詳しく話しを聞かせて頂戴な」
「は、はいっ」
ディアナの気遣いに感謝しつつ、レティシアは一ヶ月前のあの日のことを思い出した。
「ディアナ様もご存知かと思いますが、私は魔法の使えない『不良品』なんです。セシル様のパーティーにも、妹のおまけで参加したんです。そんな時、セシル様だけが、私に話しかけてくださいました」
レティシアの言葉を、ディアナは静かに聞いていく。レティシアはそのまま言葉を続けた。
「どんな方も、私を見ると去って行きました。ですが、セシル様だけが、私に話しかけてくださり、会話をして下さいました。その時、セシル様が婚約者にと話してくださったんです」
最初は冗談だと思い、信じていなかった。だが、向けられる視線が嘘を言っているとも思えなかった。
「本気で、私を婚約者にしてくださると言ってくださり、嬉しかったです。でもその時、私には既に婚約が決められかけていて……でもセシル様は約束だと、必ず迎えに行くと言ってくださり、本当に迎えに来てくださいました。それが何よりも嬉しかったです」
ハッとし、話が逸れてしまったことに気付く。慌ててディアナに謝罪をする。
「すみませんっ、話が逸れてしまって……」
「構わないわ。でもレティシアちゃん、一つだけ、文句を言わさせて頂戴」
「はい……」
何だろうか――。少しだけ表情の険しくなったディアナに、レティシアは体を竦めた。
「自分のことを『不良品』なんて、言っては絶対にダメ」
「え?」
思いもよらなかった言葉に、レティシアは目を瞬かせる。ディアナは溜息を吐きながら、レティシアに指を突き出した。
「ずっとそんな風に言われてきたのね……だからそんな風に自分を卑下してしまうのよ。でもね、ここにはあなたを『不良品』だなんて思っている人は居ないわ。自分に自信を持ちなさいっ」
その言葉に、レティシアは困惑する。今までずっと、『不良品』と家族からも周りからも言われ続けてきた。今更、自分は『不良品』じゃない。だなんて、思える訳がない。
「あなたは、セシルが選んだ婚約者なのよ。もっと自信を持ちなさいな」
そうだ。自分は『不良品』だ。だが、セシル様が選んでくれたのだ。
「……今すぐは無理ですが、少しずつ、努力してみます」
「うん! 偉いわっ、レティシアちゃん!」
レティシアの言葉に、ディアナはぎゅっと抱き締めた。誰かにこうして抱き締められるなんて、今までなかったことだ。今は本当に幸せだ――。そう思いながら、レティシアはディアナの背にそっと手を回した。