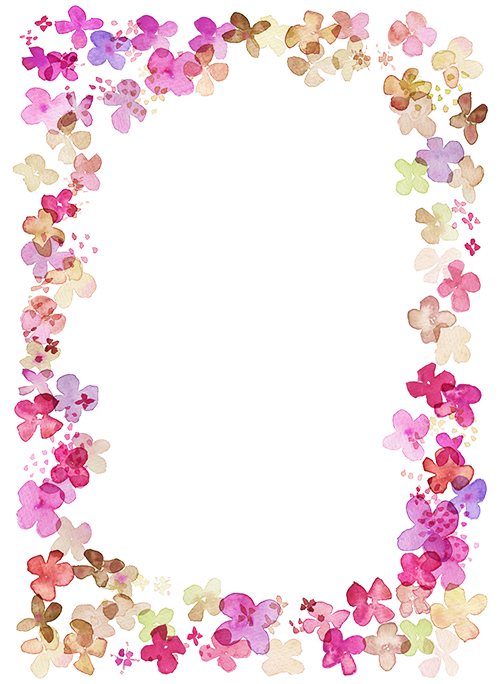「ちょっと」
馬車から降り、玄関ホールでスフィアに呼び止められる。振り向くと、目を細め口元を歪ませ、腕を組んで不機嫌を隠そうともしないスフィアと視線が重なった。
「何?」
「あの男、誰よ」
あの男とは、セシルのことを指しているのだろう。レティシアはギュッと胸元に当てた右手を握り締めながら淡々と答える。
「今日会ったばかりの方よ。私のことを知らなかったから話しかけてきただけ」
そう答えるレティシアに、スフィアは鼻で笑いながら肩を竦めた。
「あんたみたいな『不良品』を知らない? 馬鹿なんじゃないのそいつ」
「っ」
スフィアの言葉に、レティシアはきつく睨み付けた。自身のことを悪く言われるのは構わない。だが、セシルのことを悪く言われるのは許せなかった。
「何よ、睨んだってあんたみたいな『不良品』、怖くもないわよ。それに、あんたは明日にはもう嫁ぎ先が決まる筈よ。残念だったわねえ、素敵な彼と一緒になれないなんて」
「っ、わかってるわよ!」
レティシアらしからぬ大きな声に、スフィアは驚く。周りにいた使用人達の視線も、今だけは辛く感じる。一緒になれないのなんて、誰よりもわかってる。言葉にされるのも苦しい。
「用はそれだけ? なら部屋に戻るわ」
スフィアの返事も聞かず、レティシアは踵を返し自室へと足を向ける。スフィアは呆気に取られていたが、我に返りレティシアの肩を掴もうとする。
「っ、待ちなさいよ!」
「お嬢様、お帰りなさいませ」
スフィアの手がレティシアの肩に振れる瞬間、主を迎えに来たカイラが表れた。にっこりとスフィアに笑顔を向け、言葉を続ける。
「スフィアお嬢様。レティシアお嬢様はお疲れのようですので、自室にお連れします。宜しいですね?」
うっすらと目を開け、カイラが微笑む。カイラを苦手としているスフィアは何も言えず、フン、と鼻を鳴らし自分の自室のある階段を駆け上がっていった。
「カイラ……ありがとう」
「お嬢様のお役に立てたならメイド冥利に尽きますっ」
カイラの元気で明るい表情を見て、安心する。先程までの刺々した感情も凪いでいく。カイラの手を取りながら、ゆっくりと自室へと戻っていった。
「えっ、お嬢様に婚約を申し込んできた!?」
脱いだドレスをクローゼットに仕舞いながら、目を見開き驚くカイラ。カイラの驚く声に、湯あみを済ませナイトドレスに着替えたレティシアは慌てて人差し指を口元に当てた。カイラもつられて口元に人差し指を当てる。小声で話を再開しだす。
「本当に本当ですかっ」
「うん、冗談半分だったのだろうけど……」
恥ずかしそうに俯きながら答えるレティシアに、カイラはにっこりと笑みを向けた。
「いやいや、お嬢様に冗談で婚約なんてしてきたら燃やしますよ?」
「カイラ、落ち着いてっ」
目が笑っていない微笑みに、カイラの本気の色が窺える。再び慌てて静まるよう説得する。
(冗談ではないさ。嘘を言っても意味がないだろう)
そう言っていたセシル。セシルのことを考えると、胸が熱くなった。
きっと、これが恋というものなのだろう。プロポーズされて惚れてしまうなんて、単純すぎるとは自分でも思う。でも、それが恋というものなのかもしれない。
でも……。
「きっと、明日にはお父様に呼ばれるわ」
ほぼ確実に、今夜中に嫁ぎ先を決める筈だ。そうなれば、この恋も報われることなく終わるだろう。
「お嬢様……」
「そんな悲しい顔をしないで、カイラ。私は大丈夫だから」
「でも……っ」
納得が出来ないと言いそうなカイラに、レティシアは小さく頭を振り微笑んで見せる。『不良品』の自分には、過ぎた願いなのだ。
「っ、絶対、私もついて行きますからね!」
ギュッと抱き締めてくるカイラに、レティシアは腕を背に回し抱きしめ返した。
「ありがとう、カイラ」
カイラの存在が、こんなにも心強いなんて……。改めて、カイラの存在の大きさを実感するレティシア。今日という日を、セシルとの出会いを、絶対に忘れない。そう、強く思った。
「夜分失礼します、お嬢様」
ノックの後、突然ドアが開く。訪問者であるクラリックは慌てたような表情をしていた。
「ちょっとクラリック! レディの部屋を勝手に開けるな!」
慌ててカイラはレティシアから離れ、ガウンを取り出すとレティシアの肩に羽織らせる。珍しい表情のクラリックに、レティシアは何があったか尋ねた。
「どうかしたの、クラリック」
「旦那様が至急、書斎に来るようにと」
「お父様が?」
嫁ぎ先を選ぶにしても、早すぎる。何かあったのかしら? 疑問は残るが、今は早急に書斎に行くしかない。レティシアはガウンに袖を通し、クラリックと共に書斎へと向かった。
「喜べ! お前達!」
書斎に入って早々、父スルグは歓喜に舞い上がる勢いで声を発した。スルグの隣にいる母ユノアも、満足げな表情だ。父のあまりの喜びように、レティシアは何があったのか検討もつかず首を傾げる。レティシアの後からやって来たスフィアも、何があったのかわからないらしく首を傾げていた。
「あの、お父様、何があったのでしょうか?」
疑問を投げかけるレティシアに、普段ならば険しい形相を向けるスルグが笑みを向けてくる。
「これが喜ばずにいられるかっ、喜べスフィア、お前に輿入れの話が出たぞ! それも魔導公爵からだ!」
「本当に!?」
スルグの言葉に、スフィアの表情が明るくなった。両手を口元に当て、喜びを噛み締めている。レティシアとしては、なぜ自分が呼ばれたのかわからない。幸せを噛み締めるスフィアを見せつけたかったのだろうか……。帰ってきてから、スフィアに関しては嫌なことばかりだ。
「ああ。先程、魔導公爵直々の書簡が魔法便で届いた。明日、クォーク家の娘を嫁に貰い受けるとな」
「良かったわね、スフィア」
「ええっ、本当に嬉しいわ! お姉さまも喜んでくれるでしょう?」
振り向かれ、家族三人から一斉に視線を向けられる。一瞬どう反応していいか躊躇ったが、すぐさまレティシアはにこりと笑みを向けた。
「……ええ、おめでとう。スフィア」
うまく笑えたかわからない。だが、そんなの気にもしないのか、両親もスフィアも喜びを露にしながら会話を続ける。
「やはりスフィアはいい子だな」
「ええ。スフィアは私達の期待に応えてくださいましたものね」
「そんなことないわ。お父さまとお母さまのお陰よ」
両親に褒めちぎられ、スフィアは笑みを浮かべた。レティシアに当て付けるかのようなやり取りに、レティシア本人は小さく溜息を吐く。
「ん? レティシア、まだいたのですか。もうお前には用はありません。自室へ帰りなさい」
ユノアもスフィアも、レティシアを見て表情を歪ませる。あからさまな態度の急変に、レティシアは胸が苦しくなった。そこまで、『不良品』の私はどうでもいいというのか。
「……わかりました。失礼します」
踵を返し、部屋を後にしようとドアノブに手を掛ける。すると、スルグが「待ちなさい」とレティシアを呼び止めた。
「何でしょうか? お父様」
呼び止められると思わなかったレティシアは、振り返りスルグへと視線を向ける。
「明日、グスタット辺境伯が迎えに来ることになっている。魔導公爵を出迎え終えたらすぐさま迎えの馬車に乗ってグスタットに行け」
「っ」
グスタット……代々マーキス辺境伯爵が統治している、王都から遠く離れた土地だ。迎えの馬車が来るということは、そこに嫁げと言うことだろう。グスタットにはクォーク家のタウンハウスがある。現当主はスルグの知人で、確か跡継ぎの息子がいた筈。パーティーの前から、もうレティシアの既に嫁ぎ先は決まっていたのだ。悲しいような、悔しいような言葉に出来ない感情が渦巻いた。
「もうお前に用はない。さっさと部屋に戻れ」
そう言うや否や、スフィアへと顔を向け楽しそうに会話をしだすスルグ。言葉の通り、もうレティシアに用はないのだ。レティシアは深く頭を垂れると、静かに書斎を後にした。
馬車から降り、玄関ホールでスフィアに呼び止められる。振り向くと、目を細め口元を歪ませ、腕を組んで不機嫌を隠そうともしないスフィアと視線が重なった。
「何?」
「あの男、誰よ」
あの男とは、セシルのことを指しているのだろう。レティシアはギュッと胸元に当てた右手を握り締めながら淡々と答える。
「今日会ったばかりの方よ。私のことを知らなかったから話しかけてきただけ」
そう答えるレティシアに、スフィアは鼻で笑いながら肩を竦めた。
「あんたみたいな『不良品』を知らない? 馬鹿なんじゃないのそいつ」
「っ」
スフィアの言葉に、レティシアはきつく睨み付けた。自身のことを悪く言われるのは構わない。だが、セシルのことを悪く言われるのは許せなかった。
「何よ、睨んだってあんたみたいな『不良品』、怖くもないわよ。それに、あんたは明日にはもう嫁ぎ先が決まる筈よ。残念だったわねえ、素敵な彼と一緒になれないなんて」
「っ、わかってるわよ!」
レティシアらしからぬ大きな声に、スフィアは驚く。周りにいた使用人達の視線も、今だけは辛く感じる。一緒になれないのなんて、誰よりもわかってる。言葉にされるのも苦しい。
「用はそれだけ? なら部屋に戻るわ」
スフィアの返事も聞かず、レティシアは踵を返し自室へと足を向ける。スフィアは呆気に取られていたが、我に返りレティシアの肩を掴もうとする。
「っ、待ちなさいよ!」
「お嬢様、お帰りなさいませ」
スフィアの手がレティシアの肩に振れる瞬間、主を迎えに来たカイラが表れた。にっこりとスフィアに笑顔を向け、言葉を続ける。
「スフィアお嬢様。レティシアお嬢様はお疲れのようですので、自室にお連れします。宜しいですね?」
うっすらと目を開け、カイラが微笑む。カイラを苦手としているスフィアは何も言えず、フン、と鼻を鳴らし自分の自室のある階段を駆け上がっていった。
「カイラ……ありがとう」
「お嬢様のお役に立てたならメイド冥利に尽きますっ」
カイラの元気で明るい表情を見て、安心する。先程までの刺々した感情も凪いでいく。カイラの手を取りながら、ゆっくりと自室へと戻っていった。
「えっ、お嬢様に婚約を申し込んできた!?」
脱いだドレスをクローゼットに仕舞いながら、目を見開き驚くカイラ。カイラの驚く声に、湯あみを済ませナイトドレスに着替えたレティシアは慌てて人差し指を口元に当てた。カイラもつられて口元に人差し指を当てる。小声で話を再開しだす。
「本当に本当ですかっ」
「うん、冗談半分だったのだろうけど……」
恥ずかしそうに俯きながら答えるレティシアに、カイラはにっこりと笑みを向けた。
「いやいや、お嬢様に冗談で婚約なんてしてきたら燃やしますよ?」
「カイラ、落ち着いてっ」
目が笑っていない微笑みに、カイラの本気の色が窺える。再び慌てて静まるよう説得する。
(冗談ではないさ。嘘を言っても意味がないだろう)
そう言っていたセシル。セシルのことを考えると、胸が熱くなった。
きっと、これが恋というものなのだろう。プロポーズされて惚れてしまうなんて、単純すぎるとは自分でも思う。でも、それが恋というものなのかもしれない。
でも……。
「きっと、明日にはお父様に呼ばれるわ」
ほぼ確実に、今夜中に嫁ぎ先を決める筈だ。そうなれば、この恋も報われることなく終わるだろう。
「お嬢様……」
「そんな悲しい顔をしないで、カイラ。私は大丈夫だから」
「でも……っ」
納得が出来ないと言いそうなカイラに、レティシアは小さく頭を振り微笑んで見せる。『不良品』の自分には、過ぎた願いなのだ。
「っ、絶対、私もついて行きますからね!」
ギュッと抱き締めてくるカイラに、レティシアは腕を背に回し抱きしめ返した。
「ありがとう、カイラ」
カイラの存在が、こんなにも心強いなんて……。改めて、カイラの存在の大きさを実感するレティシア。今日という日を、セシルとの出会いを、絶対に忘れない。そう、強く思った。
「夜分失礼します、お嬢様」
ノックの後、突然ドアが開く。訪問者であるクラリックは慌てたような表情をしていた。
「ちょっとクラリック! レディの部屋を勝手に開けるな!」
慌ててカイラはレティシアから離れ、ガウンを取り出すとレティシアの肩に羽織らせる。珍しい表情のクラリックに、レティシアは何があったか尋ねた。
「どうかしたの、クラリック」
「旦那様が至急、書斎に来るようにと」
「お父様が?」
嫁ぎ先を選ぶにしても、早すぎる。何かあったのかしら? 疑問は残るが、今は早急に書斎に行くしかない。レティシアはガウンに袖を通し、クラリックと共に書斎へと向かった。
「喜べ! お前達!」
書斎に入って早々、父スルグは歓喜に舞い上がる勢いで声を発した。スルグの隣にいる母ユノアも、満足げな表情だ。父のあまりの喜びように、レティシアは何があったのか検討もつかず首を傾げる。レティシアの後からやって来たスフィアも、何があったのかわからないらしく首を傾げていた。
「あの、お父様、何があったのでしょうか?」
疑問を投げかけるレティシアに、普段ならば険しい形相を向けるスルグが笑みを向けてくる。
「これが喜ばずにいられるかっ、喜べスフィア、お前に輿入れの話が出たぞ! それも魔導公爵からだ!」
「本当に!?」
スルグの言葉に、スフィアの表情が明るくなった。両手を口元に当て、喜びを噛み締めている。レティシアとしては、なぜ自分が呼ばれたのかわからない。幸せを噛み締めるスフィアを見せつけたかったのだろうか……。帰ってきてから、スフィアに関しては嫌なことばかりだ。
「ああ。先程、魔導公爵直々の書簡が魔法便で届いた。明日、クォーク家の娘を嫁に貰い受けるとな」
「良かったわね、スフィア」
「ええっ、本当に嬉しいわ! お姉さまも喜んでくれるでしょう?」
振り向かれ、家族三人から一斉に視線を向けられる。一瞬どう反応していいか躊躇ったが、すぐさまレティシアはにこりと笑みを向けた。
「……ええ、おめでとう。スフィア」
うまく笑えたかわからない。だが、そんなの気にもしないのか、両親もスフィアも喜びを露にしながら会話を続ける。
「やはりスフィアはいい子だな」
「ええ。スフィアは私達の期待に応えてくださいましたものね」
「そんなことないわ。お父さまとお母さまのお陰よ」
両親に褒めちぎられ、スフィアは笑みを浮かべた。レティシアに当て付けるかのようなやり取りに、レティシア本人は小さく溜息を吐く。
「ん? レティシア、まだいたのですか。もうお前には用はありません。自室へ帰りなさい」
ユノアもスフィアも、レティシアを見て表情を歪ませる。あからさまな態度の急変に、レティシアは胸が苦しくなった。そこまで、『不良品』の私はどうでもいいというのか。
「……わかりました。失礼します」
踵を返し、部屋を後にしようとドアノブに手を掛ける。すると、スルグが「待ちなさい」とレティシアを呼び止めた。
「何でしょうか? お父様」
呼び止められると思わなかったレティシアは、振り返りスルグへと視線を向ける。
「明日、グスタット辺境伯が迎えに来ることになっている。魔導公爵を出迎え終えたらすぐさま迎えの馬車に乗ってグスタットに行け」
「っ」
グスタット……代々マーキス辺境伯爵が統治している、王都から遠く離れた土地だ。迎えの馬車が来るということは、そこに嫁げと言うことだろう。グスタットにはクォーク家のタウンハウスがある。現当主はスルグの知人で、確か跡継ぎの息子がいた筈。パーティーの前から、もうレティシアの既に嫁ぎ先は決まっていたのだ。悲しいような、悔しいような言葉に出来ない感情が渦巻いた。
「もうお前に用はない。さっさと部屋に戻れ」
そう言うや否や、スフィアへと顔を向け楽しそうに会話をしだすスルグ。言葉の通り、もうレティシアに用はないのだ。レティシアは深く頭を垂れると、静かに書斎を後にした。