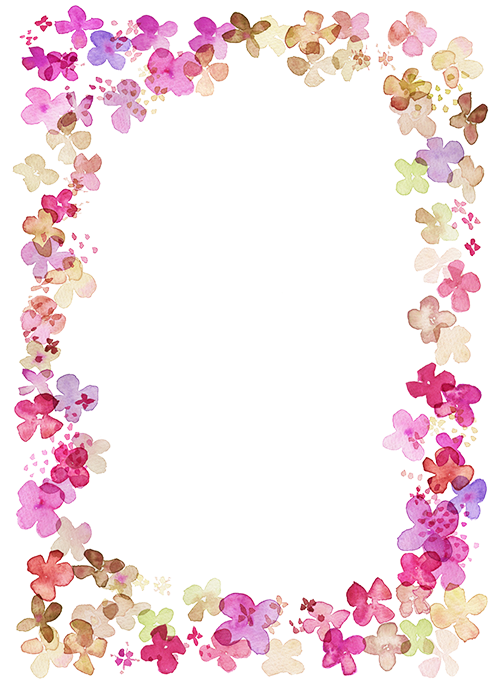「すみません……急に泣き出したりして……」
小さく鼻を啜りながら謝るレティシアに、セシリアスタは「構わない」と告げた。
「少しでも気が晴れるのならば、何時でも胸を貸そう」
「……ありがとうございます。セシル様」
そっと腕を背に回し、セシリアスタに抱き着く。するとぎゅっと強く抱きしめ返され、レティシアはセシリアスタの胸に顔を寄せた。セシリアスタの心音が心地よく、思わず顔を摺り寄せる。
「……お二人さ~ん、そろそろ本題に入りましょうよ」
「ッ」
「~~~~っ」
エドワースの声に我に返り、セシリアスタとレティシアは勢いよく離れた。ひ、人前でなんてことをしてしまったのかしら――。恥ずかしさに両手で頬を隠すが、レティシアの頬はどんどん赤みを増していった。セシリアスタの方を見れば、表情こそ平然としているが、微かに横髪に隠れる耳が真っ赤に染まっていた。
「エド、もう少し二人の空間というものに浸らせてあげればよかったのに……」
「いやいや、あのままだったら何時まで経っても話が進まねえって」
イザークとエドワースがそんなやり取りをしていると、セシリアスタは大きく咳払いをする。
「話を戻す。先程も言ったが、魔石の色は使える属性によって違う色になる。そこは理解したな?」
「は、はいっ」
紅潮する頬をそのままに、レティシアは返事をする。そこでふと、疑問が生じた。
「あの、白は何なのでしょうか……?」
「そう、それなんだよね」
レティシアの疑問に、イザークが言葉を合わせる。
「白い魔石なんて、王都でも見たことないんだよ」
他国との交易も盛んな王都でも、白い魔石は見たことがないらしい。レティシアは不安げに三人の青年を見渡した。
「一つだけ、可能性はある」
セシリアスタの言葉に、レティシアを含め三人はセシリアスタを見やる。
「何だよ。勿体ぶるなよ」
エドワースの言葉に、セシリアスタはゆっくりと口を開いた。
「古代魔法だ」
「……は?」
突然の発言に、エドワースは開いた口が塞がらなかった。すぐ隣に座るイザークも、セシリアスタの言葉に目を見開く。
「……古代魔法というと、未知の魔法ですよね?」
レティシアの言葉に、セシリアスタは静かに頷いた。イザークの表情が険しくなる。
「私が魔石生成すると、四大属性の色の魔石とこの色の魔石が出来る」
そう言って、セシリアスタは魔力を手のひらに集中させた。すると、手のひらの上に光が集まり次第に光が収束していく。そうすると、藍色よりも深い色合いの丸い魔石が生成された。
「あ、これって……」
見覚えのある魔石に、レティシアは付けている髪飾りに手を伸ばす。髪飾りの花へと形を変えている魔石は、確かにセシリアスタの手のひらに乗っている魔石と同じ色だった。
「そして、もう一つがこれだ」
言いながら、セシリアスタは反対の手のひらを差し出し、再び魔力を集中させる。光が収束した手のひらの上には、白い魔石が出来上がっていた。
「あっ」
私の魔石と同じだ――。そう思ったレティシアの向かいで、エドワースは言葉を発する。
「これも古代魔法の一種か?」
「ああ。これらは古代魔法を使用する際と同様に四大属性全てとオドを組み合わせている。恐らく、レティシアの魔石の色を見るに古代魔法の一種だと思うが……」
そう言うセシリアスタに、レティシアは不安げに胸に手を当てた。
「これって、何か魔法の発動にも違いがあるのかい?」
「古代魔法には光と闇の二つが存在する。光属性は他の四大属性と同様にプラスの魔力操作で出来る。闇属性は逆にマイナスの魔力操作を必要とする」
イザークの質問に、セシリアスタは淡々と答える。二つの魔石はテーブルの上に置かれ、小さく転がった。
「プラスの魔力操作と、マイナスの魔力操作とは……?」
聞いたこともない言葉に、レティシアは首を傾げた。セシリアスタはレティシアに振り返り、言葉を続ける。
「プラスの魔力操作というのは普段、人々が魔法を行使する際に用いる魔力の操作方法だ。体内のオドを操作すると、放出される魔力はプラスの回転が起きている。一般的に知られているのは此方の方だ。逆に魔力の流れを逆向きに操作すればマイナスの回転となる。操作は一筋縄では出来ないし、これは闇の古代魔法を行使する際に使われるもだ。魔法学者くらいしか知る者はいない」
「それに、マイナスの魔力操作は国内じゃセシルくらいしか出来ないことなんですよ」
「そうなんですね……」
エドワースの言葉に、セシリアスタの凄さを改めて知るレティシア。イザークはふむ、と考えだす。
「兎に角、確認しなきゃね。レティシア嬢、魔石の生成をしてみて欲しい」
「は、はい」
魔石の生成……カイラ以外の人の前ではしたことが無い分、緊張する――。レティシアはゆっくりと深呼吸をし、目を伏せ手を胸に当てた。淡くレティシアの体が光り、光が胸元の手に集中していく。光が次第に収束すると、レティシアは顔を上げ、手を差し出した。やはり、白い魔石だった。
「……確定、かな」
イザークの言葉に、セシリアスタは考えだす。そんなセシリアスタに、レティシアは不安げな表情を向けた。
「セシル様、私、何かおかしいのでしょうか……?」
「いや、レティシアの魔力の流れもおかしな点は見られなかった」
「となると、レティシア嬢は光属性ってことになるのか?」
エドワースの言葉に、再び考えだすセシリアスタ。イザークはセシリアスタの方を向き言葉を発する。
「仮にレティシア嬢が扱える属性が光属性ならば、他の精霊の属性も使えないとおかしい。ってことかい?」
「ああ……そう、なる筈なんだが……」
顎に指を添え考えだすセシリアスタ。レティシアは自分の手を見つめる。何故、自分には四大属性が使えないのに古代魔法の素質があるのだろうか――。
「……精霊に聞ければいいのに……」
ぽつりと囁くレティシアに、セシリアスタは顔を上げた。
「そうか、その手があったか」
「え?」
「わからないならば直接、精霊に聞けばいい」
セシリアスタの発言に、耳を疑うレティシア。そんなレティシアを置いて、他の二人は納得した。
「そっか。その手を忘れてたね」
「あれ、すっごく疲れるんだけどな……」
「エド、頑張って」
一人話について行けず、三人を見つめるレティシアに、セシリアスタは手を差し伸べた。
「レティシア、手を」
「は、はいっ」
わからないが、取り敢えず従おう。そう考え、レティシアは差し出されたセシリアスタの手を取った。反対の手は向かいに座るエドワースと繋ぎ、四人で円を描くように手を繋いだ。
「いくぞ」
「おう」
「いいよ」
セシリアスタの掛け声に、エドワースとイザークが頷く。セシリアスタが呪文を詠唱すると、辺りが眩く光り出した。あまりの眩しさに、レティシアは目を閉じる。
「レティシア、目を開けて上を見てくれ」
セシリアスタの声に、レティシアはそっと目を開けた。辺りを包み込んでいた眩い光は治まり、言われた通りに上を見上げる。
そこには、それそれ違う光を纏った四体の小さな存在が浮遊していた。
小さく鼻を啜りながら謝るレティシアに、セシリアスタは「構わない」と告げた。
「少しでも気が晴れるのならば、何時でも胸を貸そう」
「……ありがとうございます。セシル様」
そっと腕を背に回し、セシリアスタに抱き着く。するとぎゅっと強く抱きしめ返され、レティシアはセシリアスタの胸に顔を寄せた。セシリアスタの心音が心地よく、思わず顔を摺り寄せる。
「……お二人さ~ん、そろそろ本題に入りましょうよ」
「ッ」
「~~~~っ」
エドワースの声に我に返り、セシリアスタとレティシアは勢いよく離れた。ひ、人前でなんてことをしてしまったのかしら――。恥ずかしさに両手で頬を隠すが、レティシアの頬はどんどん赤みを増していった。セシリアスタの方を見れば、表情こそ平然としているが、微かに横髪に隠れる耳が真っ赤に染まっていた。
「エド、もう少し二人の空間というものに浸らせてあげればよかったのに……」
「いやいや、あのままだったら何時まで経っても話が進まねえって」
イザークとエドワースがそんなやり取りをしていると、セシリアスタは大きく咳払いをする。
「話を戻す。先程も言ったが、魔石の色は使える属性によって違う色になる。そこは理解したな?」
「は、はいっ」
紅潮する頬をそのままに、レティシアは返事をする。そこでふと、疑問が生じた。
「あの、白は何なのでしょうか……?」
「そう、それなんだよね」
レティシアの疑問に、イザークが言葉を合わせる。
「白い魔石なんて、王都でも見たことないんだよ」
他国との交易も盛んな王都でも、白い魔石は見たことがないらしい。レティシアは不安げに三人の青年を見渡した。
「一つだけ、可能性はある」
セシリアスタの言葉に、レティシアを含め三人はセシリアスタを見やる。
「何だよ。勿体ぶるなよ」
エドワースの言葉に、セシリアスタはゆっくりと口を開いた。
「古代魔法だ」
「……は?」
突然の発言に、エドワースは開いた口が塞がらなかった。すぐ隣に座るイザークも、セシリアスタの言葉に目を見開く。
「……古代魔法というと、未知の魔法ですよね?」
レティシアの言葉に、セシリアスタは静かに頷いた。イザークの表情が険しくなる。
「私が魔石生成すると、四大属性の色の魔石とこの色の魔石が出来る」
そう言って、セシリアスタは魔力を手のひらに集中させた。すると、手のひらの上に光が集まり次第に光が収束していく。そうすると、藍色よりも深い色合いの丸い魔石が生成された。
「あ、これって……」
見覚えのある魔石に、レティシアは付けている髪飾りに手を伸ばす。髪飾りの花へと形を変えている魔石は、確かにセシリアスタの手のひらに乗っている魔石と同じ色だった。
「そして、もう一つがこれだ」
言いながら、セシリアスタは反対の手のひらを差し出し、再び魔力を集中させる。光が収束した手のひらの上には、白い魔石が出来上がっていた。
「あっ」
私の魔石と同じだ――。そう思ったレティシアの向かいで、エドワースは言葉を発する。
「これも古代魔法の一種か?」
「ああ。これらは古代魔法を使用する際と同様に四大属性全てとオドを組み合わせている。恐らく、レティシアの魔石の色を見るに古代魔法の一種だと思うが……」
そう言うセシリアスタに、レティシアは不安げに胸に手を当てた。
「これって、何か魔法の発動にも違いがあるのかい?」
「古代魔法には光と闇の二つが存在する。光属性は他の四大属性と同様にプラスの魔力操作で出来る。闇属性は逆にマイナスの魔力操作を必要とする」
イザークの質問に、セシリアスタは淡々と答える。二つの魔石はテーブルの上に置かれ、小さく転がった。
「プラスの魔力操作と、マイナスの魔力操作とは……?」
聞いたこともない言葉に、レティシアは首を傾げた。セシリアスタはレティシアに振り返り、言葉を続ける。
「プラスの魔力操作というのは普段、人々が魔法を行使する際に用いる魔力の操作方法だ。体内のオドを操作すると、放出される魔力はプラスの回転が起きている。一般的に知られているのは此方の方だ。逆に魔力の流れを逆向きに操作すればマイナスの回転となる。操作は一筋縄では出来ないし、これは闇の古代魔法を行使する際に使われるもだ。魔法学者くらいしか知る者はいない」
「それに、マイナスの魔力操作は国内じゃセシルくらいしか出来ないことなんですよ」
「そうなんですね……」
エドワースの言葉に、セシリアスタの凄さを改めて知るレティシア。イザークはふむ、と考えだす。
「兎に角、確認しなきゃね。レティシア嬢、魔石の生成をしてみて欲しい」
「は、はい」
魔石の生成……カイラ以外の人の前ではしたことが無い分、緊張する――。レティシアはゆっくりと深呼吸をし、目を伏せ手を胸に当てた。淡くレティシアの体が光り、光が胸元の手に集中していく。光が次第に収束すると、レティシアは顔を上げ、手を差し出した。やはり、白い魔石だった。
「……確定、かな」
イザークの言葉に、セシリアスタは考えだす。そんなセシリアスタに、レティシアは不安げな表情を向けた。
「セシル様、私、何かおかしいのでしょうか……?」
「いや、レティシアの魔力の流れもおかしな点は見られなかった」
「となると、レティシア嬢は光属性ってことになるのか?」
エドワースの言葉に、再び考えだすセシリアスタ。イザークはセシリアスタの方を向き言葉を発する。
「仮にレティシア嬢が扱える属性が光属性ならば、他の精霊の属性も使えないとおかしい。ってことかい?」
「ああ……そう、なる筈なんだが……」
顎に指を添え考えだすセシリアスタ。レティシアは自分の手を見つめる。何故、自分には四大属性が使えないのに古代魔法の素質があるのだろうか――。
「……精霊に聞ければいいのに……」
ぽつりと囁くレティシアに、セシリアスタは顔を上げた。
「そうか、その手があったか」
「え?」
「わからないならば直接、精霊に聞けばいい」
セシリアスタの発言に、耳を疑うレティシア。そんなレティシアを置いて、他の二人は納得した。
「そっか。その手を忘れてたね」
「あれ、すっごく疲れるんだけどな……」
「エド、頑張って」
一人話について行けず、三人を見つめるレティシアに、セシリアスタは手を差し伸べた。
「レティシア、手を」
「は、はいっ」
わからないが、取り敢えず従おう。そう考え、レティシアは差し出されたセシリアスタの手を取った。反対の手は向かいに座るエドワースと繋ぎ、四人で円を描くように手を繋いだ。
「いくぞ」
「おう」
「いいよ」
セシリアスタの掛け声に、エドワースとイザークが頷く。セシリアスタが呪文を詠唱すると、辺りが眩く光り出した。あまりの眩しさに、レティシアは目を閉じる。
「レティシア、目を開けて上を見てくれ」
セシリアスタの声に、レティシアはそっと目を開けた。辺りを包み込んでいた眩い光は治まり、言われた通りに上を見上げる。
そこには、それそれ違う光を纏った四体の小さな存在が浮遊していた。