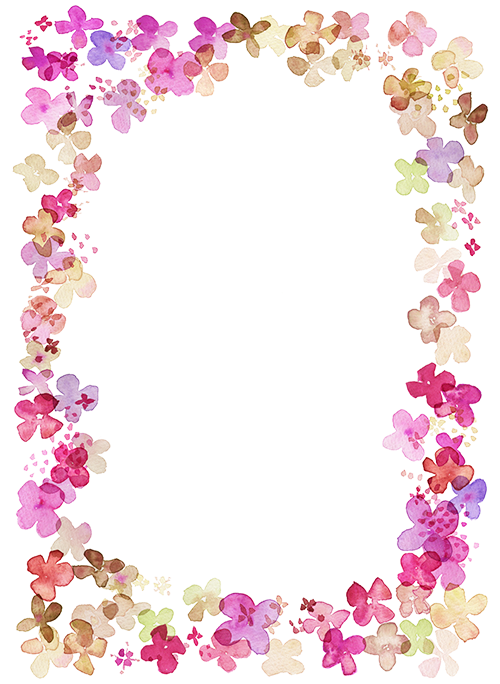食事の後、レティシアは部屋に戻った。セシリアスタはイザーク、エドワースと共に自室へと向かう。エドワースの手にはクラッカー、チーズの盛り付けられたお皿がある。三人は静かに、セシリアスタの自室へと入っていった。
「レティシア嬢、可愛らしい子じゃないか」
イザークの言葉に、ワインセラーから数本のワインを取り出したセシリアスタが視線を向ける。
「正直な感想だよ。噂しか聞いたことがなかったからね」
「噂って、あれか?」
テーブルにつまみを置きグラスを持ってきたエドワースの言葉に、イザークは頷く。
「うん。”王族に勝る程の魔力を宿しながら、魔法の使えない少女”。社交界にも殆ど姿を現さないことでも有名だったんだ」
イザークの一言に、セシリアスタの表情が険しくなる。それを見て、イザークは推測する。
「それも訳アリってことかい?」
「イザーク、あんましセシルを焚き付けるなよ」
エドワースに諫められ、イザークは口を噤む。だが、セシリアスタの表情は真実を告げているようなものだ。
「彼女、作法はとても綺麗だったね」
「そこは家庭教師が教え込ませたらしい」
溜息を吐きながら、セシリアスタはワインのコルクを開けグラスに注ぎだす。三人分注ぎ終えると、一人ずつグラスを手に持つ。
「ということは、アカデミーにも通ってないのかい?」
「ああ……」
頷きながら、セシリアスタは一気にグラスを呷る。空になったグラスを置き、再びワインを注いでいく。
「レティシア嬢、家族から不平等な扱い受けてたみたいでよ……アカデミー所か社交界にも碌に行かせて貰ってねえんだよな、これが」
「姿を現さないんじゃなくて、行かせて貰えなかったのか……サロンを断りたかったのも納得したよ」
クラッカーを口に放り込みながら話すエドワースに、イザークは頷きワインを口に含んだ。
「レティシアは自分を『不良品』と言い卑下する癖がある。……ずっと、家族にそう言われ虐げられてきたんだろう」
「だろうな……って、セシル、飲むスピード早すぎだって。つまみを食え、つまみを」
エドワースに小言を言われ、渋々グラスをテーブルに置くセシリアスタ。珍しい光景に、イザークは目を瞬かせ、一人納得したように頷く。
「なるほど……セシルはレティシア嬢のこと、本当に好きなんだね」
「でなければ婚約直前の娘に対し嫁に貰うなどと手紙は出さん」
そう言いながら、セシリアスタはクラッカーに齧り付いた。
「でもよ~、その家が面倒でさ」
「ん?」
エドワースの悪態に、イザークは振り替える。ワインを飲みながら、エドワースは椅子に大きく体重をかける。
「レティシア嬢の妹をセシルの婚約者にしたかったらしくてよ。今もしつこく婚約者の交換を要求するって手紙が来るんだよ……。妹もセシルに惚れてたみたいで、しつこくて……」
エドワースの悪態というのも珍しく、イザークは顎に指を添えて悩む。エドワースが困っているならば、助けてやりたい。イザークは考える。
「レティシア嬢、成人まで後どれくらいなんだい?」
「えーと、確か二ヶ月は切ったな」
「となると七週間くらいか……。セシル、君の兄君に報告に行ってはどうかな?」
イザークの一言に、セシリアスタは思ってもみなかったことに目を見開いた。
「……兄上に?」
「そう。君のお兄さんであるオズワルト伯爵にパーティーを開いて貰えばいい。そこで婚約者として紹介しちゃいなよ」
イザークの発案に、エドワースはワインを飲み干し考えだした。
「そっか。先に領地を治める伯爵達を集めたパーティーで紹介しちまえば、クォーク伯爵も何も言えねえか」
「うん。その為にはまず君のお兄さんに会って貰おうよ」
「しかし……レティシアがパーティーに参加したがるかどうか……」
セシリアスタの心配を余所に、イザークは話を進める。
「大丈夫だって。君のパーティーに来たくらいの強者だ。伯爵夫人だって気に入るよ」
「セシル、やってみようぜ」
イザークにエドワース、二人の後押しに、セシリアスタは悩む。それで本当に上手くいくのだろうか――。
「兎に角、悩んでも始まらないよ。早速、オズワルト伯爵に手紙を書いちゃいなよ」
「おう! 明日にでも書いてささっと送っちまうぜ! イザークいいこと考えるじゃねえかっ」
喜ぶエドワースに、イザークは照れながら頭を掻いた。そんな二人を、微かに不安の残るセシリアスタは静かに見つめていた。
「よし、んじゃ後はゆっくり酒でも飲むか!」
「だね」
「……そうだな」
エドワースの掛け声に合わせ、グラスを持ち上げる三人。グラスの触れ合う音が小さく響いた。
「レティシア嬢、可愛らしい子じゃないか」
イザークの言葉に、ワインセラーから数本のワインを取り出したセシリアスタが視線を向ける。
「正直な感想だよ。噂しか聞いたことがなかったからね」
「噂って、あれか?」
テーブルにつまみを置きグラスを持ってきたエドワースの言葉に、イザークは頷く。
「うん。”王族に勝る程の魔力を宿しながら、魔法の使えない少女”。社交界にも殆ど姿を現さないことでも有名だったんだ」
イザークの一言に、セシリアスタの表情が険しくなる。それを見て、イザークは推測する。
「それも訳アリってことかい?」
「イザーク、あんましセシルを焚き付けるなよ」
エドワースに諫められ、イザークは口を噤む。だが、セシリアスタの表情は真実を告げているようなものだ。
「彼女、作法はとても綺麗だったね」
「そこは家庭教師が教え込ませたらしい」
溜息を吐きながら、セシリアスタはワインのコルクを開けグラスに注ぎだす。三人分注ぎ終えると、一人ずつグラスを手に持つ。
「ということは、アカデミーにも通ってないのかい?」
「ああ……」
頷きながら、セシリアスタは一気にグラスを呷る。空になったグラスを置き、再びワインを注いでいく。
「レティシア嬢、家族から不平等な扱い受けてたみたいでよ……アカデミー所か社交界にも碌に行かせて貰ってねえんだよな、これが」
「姿を現さないんじゃなくて、行かせて貰えなかったのか……サロンを断りたかったのも納得したよ」
クラッカーを口に放り込みながら話すエドワースに、イザークは頷きワインを口に含んだ。
「レティシアは自分を『不良品』と言い卑下する癖がある。……ずっと、家族にそう言われ虐げられてきたんだろう」
「だろうな……って、セシル、飲むスピード早すぎだって。つまみを食え、つまみを」
エドワースに小言を言われ、渋々グラスをテーブルに置くセシリアスタ。珍しい光景に、イザークは目を瞬かせ、一人納得したように頷く。
「なるほど……セシルはレティシア嬢のこと、本当に好きなんだね」
「でなければ婚約直前の娘に対し嫁に貰うなどと手紙は出さん」
そう言いながら、セシリアスタはクラッカーに齧り付いた。
「でもよ~、その家が面倒でさ」
「ん?」
エドワースの悪態に、イザークは振り替える。ワインを飲みながら、エドワースは椅子に大きく体重をかける。
「レティシア嬢の妹をセシルの婚約者にしたかったらしくてよ。今もしつこく婚約者の交換を要求するって手紙が来るんだよ……。妹もセシルに惚れてたみたいで、しつこくて……」
エドワースの悪態というのも珍しく、イザークは顎に指を添えて悩む。エドワースが困っているならば、助けてやりたい。イザークは考える。
「レティシア嬢、成人まで後どれくらいなんだい?」
「えーと、確か二ヶ月は切ったな」
「となると七週間くらいか……。セシル、君の兄君に報告に行ってはどうかな?」
イザークの一言に、セシリアスタは思ってもみなかったことに目を見開いた。
「……兄上に?」
「そう。君のお兄さんであるオズワルト伯爵にパーティーを開いて貰えばいい。そこで婚約者として紹介しちゃいなよ」
イザークの発案に、エドワースはワインを飲み干し考えだした。
「そっか。先に領地を治める伯爵達を集めたパーティーで紹介しちまえば、クォーク伯爵も何も言えねえか」
「うん。その為にはまず君のお兄さんに会って貰おうよ」
「しかし……レティシアがパーティーに参加したがるかどうか……」
セシリアスタの心配を余所に、イザークは話を進める。
「大丈夫だって。君のパーティーに来たくらいの強者だ。伯爵夫人だって気に入るよ」
「セシル、やってみようぜ」
イザークにエドワース、二人の後押しに、セシリアスタは悩む。それで本当に上手くいくのだろうか――。
「兎に角、悩んでも始まらないよ。早速、オズワルト伯爵に手紙を書いちゃいなよ」
「おう! 明日にでも書いてささっと送っちまうぜ! イザークいいこと考えるじゃねえかっ」
喜ぶエドワースに、イザークは照れながら頭を掻いた。そんな二人を、微かに不安の残るセシリアスタは静かに見つめていた。
「よし、んじゃ後はゆっくり酒でも飲むか!」
「だね」
「……そうだな」
エドワースの掛け声に合わせ、グラスを持ち上げる三人。グラスの触れ合う音が小さく響いた。