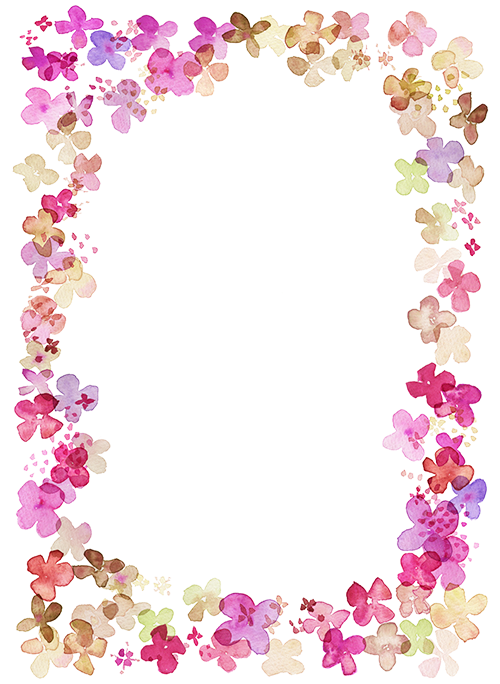「まあ、ということは、三人は親友同士だったのですね」
セシリアスタとレティシア、エドワースにイザークと四人で囲む食事は、発見の連続だった。まず、セシリアスタとエドワース、イザークが同い年で二十三歳だということ。エドワースは一般家庭の出だが、高い魔力を持つということで王都のアカデミーに推薦入学していたこと。そうした沢山のことをイザークは話してくれた。
「うん、今でも仲は良好だよ」
ね? とセシリアスタとエドワースに振り替えるイザーク。セシリアスタは微かに微笑み、エドワースは溜息を吐いた。そんな二人の態度に疑問符を浮かべながら、レティシアはスープを一口飲む。
「イザークさんはどのようなお仕事をなさっておられるのですか?」
「僕かい? そうだね……主に雑務だよ。書類の整理や運搬。後は暇な時は騎士団に顔を出しているかな」
「騎士団ですかっ」
イザークの言葉に、レティシアは驚いた。騎士団は王宮を守護する王宮直属の親衛隊と、魔物を討伐したり国を守護したりする精鋭部隊の二つに分類される。イザークはどちらに所属しているのだろうか――。
「ちなみに、セシルもエドも精鋭部隊の一員だよ」
その言葉に、セシリアスタとエドワースの方へと振り返る。知らなかった――。二人は王宮で魔法に関しての研究、解読を主にしているとばかり思ってしまっていた。知らなかったというより、知ろうとしていなかった自分が恥ずかしくなった。俯くレティシアに、セシリアスタは言葉をかけるか考えあぐねる。
「気にしなくていいよ。レティシア嬢」
イザークの言葉に、顔を上げる。レティシアに微笑むイザークの表情は穏やかだった。付け加えるように、エドワースは口を開く。
「あ~、その……言わなかったのはこっちですから……気にしちゃったらすいません」
エドワースの言葉に、慌てて首を振るレティシア。そんなこと、二人が気にする必要はないのだ。
「そんなっ、私が知ろうとしなかったのが原因です。気になさらないでください」
レティシアの発言に、セシリアスタもエドワースもホッと安堵する。話を変えようと、イザークは言葉を切りだす。
「ちなみに、僕の趣味はエドの観察と勧誘なんだ」
「おいっ」
突然の話の切り替えにも驚いたが、イザークの発言にも驚く。
「勧誘、ですか?」
「エドは僕の使えない水と風の属性が使えるエキスパートなんだ。だから僕の側に置いておきたいんだけど、中々首を縦に振ってはくれないんだよね……」
溜息を吐くイザークはとても美しかった。思わず見とれてしまう。そんなイザークに、エドワースは自身の肩を抱いて震えあがった。
「お前の勧誘は何度言われようともお断りだっ! それにお前の勧誘は個人的な意味合いもあるだろーが!」
「ばれたか~」
笑顔で白状するイザークに、エドワースは上体だけでも後退する。そんな二人を見て、セシリアスタは微笑んでいた。
「セシル様のご趣味を窺っても?」
「私か……?」
レティシアの言葉に、セシリアスタは目を瞬かせた。話を振られるとは思ってもみなかったようで、少し考えだす。
「……魔石の生成、だな。レティシアは?」
「私は魔糸での刺しゅうです。といっても、私が作れる魔石は白くらいなので、白い魔糸しか出来ませんが……」
その一言に、周りの空気が変わった。青年三人に見つめられ、レティシアは困惑する。
「白、だって……?」
「はい。幼い頃から魔石生成で作れる魔石は白ですが……」
それに何か問題でもあるのだろうか――。少しだけ、不安になる。
「イザーク。明日の執務は取り止める」
「いいよ。僕も同伴しよう」
「わかった」
何やら三人の間で話が進んでしまっていくなか、エドワースがレティシアに話しかける。
「レティシア嬢。明日はセシリアスタ様から講義を受けましょうか」
「え!?」
魔導公爵と謳われるセシリアスタから、直接の講義を受けられる!? 突然のことに、頭が追い付かない。
「というかエド。何時も思ってたけどセシルのことを敬称呼びとか変じゃない? 」
「はあ!?」
「確かに。気持ち悪いとは思っていたな」
イザークに続きセシリアスタからも小言を言われ、エドワースは振り替える。
「俺は補佐としてのメンツを考えてだな!」
「別に構わん。寧ろ補佐ならば敬称で呼ばなくてもいいだろう」
「~~~~っ」
セシリアスタの一言に、エドワースは悩みだす。俯き、頭を掻きだした。
「だあああもうっ! わかったよ昔の呼び方で呼ぶ! 周りにどうこう言われても、お前の所為にするからな!」
「そうして構わんよ」
やけくそと言わんばかりのエドワースの行動に、レティシアはつい笑みが零れた。
三人は本当に仲がいいのだろう。自分はアカデミーに通ったことが無いので、友達と呼べる人はいない。そこが少し寂しい気もするが、目の前の三人を見て、心が温まったレティシアだった。
セシリアスタとレティシア、エドワースにイザークと四人で囲む食事は、発見の連続だった。まず、セシリアスタとエドワース、イザークが同い年で二十三歳だということ。エドワースは一般家庭の出だが、高い魔力を持つということで王都のアカデミーに推薦入学していたこと。そうした沢山のことをイザークは話してくれた。
「うん、今でも仲は良好だよ」
ね? とセシリアスタとエドワースに振り替えるイザーク。セシリアスタは微かに微笑み、エドワースは溜息を吐いた。そんな二人の態度に疑問符を浮かべながら、レティシアはスープを一口飲む。
「イザークさんはどのようなお仕事をなさっておられるのですか?」
「僕かい? そうだね……主に雑務だよ。書類の整理や運搬。後は暇な時は騎士団に顔を出しているかな」
「騎士団ですかっ」
イザークの言葉に、レティシアは驚いた。騎士団は王宮を守護する王宮直属の親衛隊と、魔物を討伐したり国を守護したりする精鋭部隊の二つに分類される。イザークはどちらに所属しているのだろうか――。
「ちなみに、セシルもエドも精鋭部隊の一員だよ」
その言葉に、セシリアスタとエドワースの方へと振り返る。知らなかった――。二人は王宮で魔法に関しての研究、解読を主にしているとばかり思ってしまっていた。知らなかったというより、知ろうとしていなかった自分が恥ずかしくなった。俯くレティシアに、セシリアスタは言葉をかけるか考えあぐねる。
「気にしなくていいよ。レティシア嬢」
イザークの言葉に、顔を上げる。レティシアに微笑むイザークの表情は穏やかだった。付け加えるように、エドワースは口を開く。
「あ~、その……言わなかったのはこっちですから……気にしちゃったらすいません」
エドワースの言葉に、慌てて首を振るレティシア。そんなこと、二人が気にする必要はないのだ。
「そんなっ、私が知ろうとしなかったのが原因です。気になさらないでください」
レティシアの発言に、セシリアスタもエドワースもホッと安堵する。話を変えようと、イザークは言葉を切りだす。
「ちなみに、僕の趣味はエドの観察と勧誘なんだ」
「おいっ」
突然の話の切り替えにも驚いたが、イザークの発言にも驚く。
「勧誘、ですか?」
「エドは僕の使えない水と風の属性が使えるエキスパートなんだ。だから僕の側に置いておきたいんだけど、中々首を縦に振ってはくれないんだよね……」
溜息を吐くイザークはとても美しかった。思わず見とれてしまう。そんなイザークに、エドワースは自身の肩を抱いて震えあがった。
「お前の勧誘は何度言われようともお断りだっ! それにお前の勧誘は個人的な意味合いもあるだろーが!」
「ばれたか~」
笑顔で白状するイザークに、エドワースは上体だけでも後退する。そんな二人を見て、セシリアスタは微笑んでいた。
「セシル様のご趣味を窺っても?」
「私か……?」
レティシアの言葉に、セシリアスタは目を瞬かせた。話を振られるとは思ってもみなかったようで、少し考えだす。
「……魔石の生成、だな。レティシアは?」
「私は魔糸での刺しゅうです。といっても、私が作れる魔石は白くらいなので、白い魔糸しか出来ませんが……」
その一言に、周りの空気が変わった。青年三人に見つめられ、レティシアは困惑する。
「白、だって……?」
「はい。幼い頃から魔石生成で作れる魔石は白ですが……」
それに何か問題でもあるのだろうか――。少しだけ、不安になる。
「イザーク。明日の執務は取り止める」
「いいよ。僕も同伴しよう」
「わかった」
何やら三人の間で話が進んでしまっていくなか、エドワースがレティシアに話しかける。
「レティシア嬢。明日はセシリアスタ様から講義を受けましょうか」
「え!?」
魔導公爵と謳われるセシリアスタから、直接の講義を受けられる!? 突然のことに、頭が追い付かない。
「というかエド。何時も思ってたけどセシルのことを敬称呼びとか変じゃない? 」
「はあ!?」
「確かに。気持ち悪いとは思っていたな」
イザークに続きセシリアスタからも小言を言われ、エドワースは振り替える。
「俺は補佐としてのメンツを考えてだな!」
「別に構わん。寧ろ補佐ならば敬称で呼ばなくてもいいだろう」
「~~~~っ」
セシリアスタの一言に、エドワースは悩みだす。俯き、頭を掻きだした。
「だあああもうっ! わかったよ昔の呼び方で呼ぶ! 周りにどうこう言われても、お前の所為にするからな!」
「そうして構わんよ」
やけくそと言わんばかりのエドワースの行動に、レティシアはつい笑みが零れた。
三人は本当に仲がいいのだろう。自分はアカデミーに通ったことが無いので、友達と呼べる人はいない。そこが少し寂しい気もするが、目の前の三人を見て、心が温まったレティシアだった。