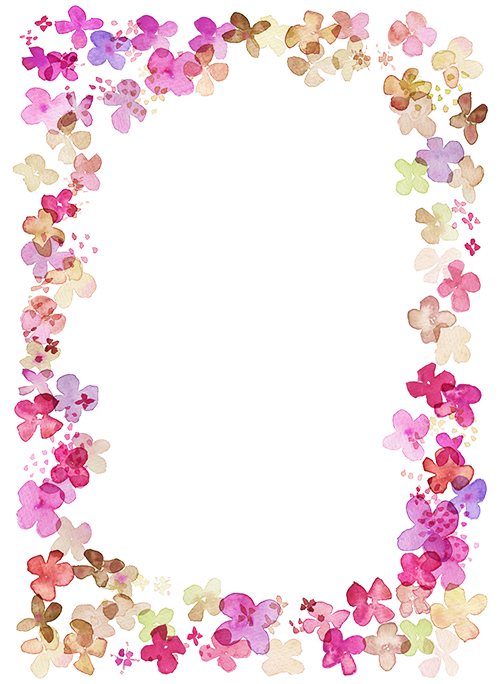試着した服の中で、最後に着た水色のケープレットの付いた白い膝丈のバブル・ドレスをそのまま着ていくことにしたレティシアは、セシリアスタに連れられて次の店に入る。次に入った所は、靴屋だった。
「ヤード、彼女に合う靴を幾つか見繕ってくれ」
セシリアスタの言葉に、店主である初老の男性は「わかりました、若旦那」と言いレティシアの足のサイズを測りだす。
「先程から気になったのですが……『若旦那』とは?」
「行きつけの店の店主は皆、私のことをそう呼ぶのさ」
微笑みながら、セシリアスタは答える。先程の店も、セシリアスタの行きつけらしい。ジャスミンの店には男性物がなかったが、オーダーメイドで頼んでいるのだろうか? そう考えていると、ヤードは店の奥からレティシアの足のサイズと同じ靴を何点か持ってきた。
ブーティーやチャッカ・ブーツ、カッター・ブーツやストラップシューズなど、どの服にも合わせやすい茶色や黒だけでなく、赤や水色などの鮮やかな色の靴も出された。
「うん、全て買おう」
「セシル様っ」
またしてもセシリアスタは全て買うと言い出す。レティシアは困ると言いかけるが、再び「プレゼントしたい」と言われてしまい、言葉を返すことも出来なかった。
「あ」
店の奥側に、可愛らしい赤茶色のレースアップ・ブーツがあった。綺麗に誂えられた靴を見て、つい声が出てしまった。それに気付いたセシリアスタは、その靴を指指した。
「ヤード、その靴でレティシア嬢に合うサイズはあるか」
「そうですね……確かにその靴はお嬢さんに合うサイズですが、あちら一点だけしか残ってなくて」
その言葉を聞き、セシリアスタは悩む。レティシアが気に入った以上、買ってやりたい。そう思ったセシリアスタは、「構わない」と言葉を続ける
「磨いてくれ」
「了解いたしました」
ヤードに丁寧に磨いてもらい、差し出されたブーツ。セシリアスタはそっと跪き、レティシアの足へと履かせる。
「せ、セシル様! 自分で、自分で出来ますからっ」
恥ずかしくなり、慌てて制止させようとするが、セシリアスタはそんなことはお構いなしにとレティシアの白磁のような足へ履かせる。靴紐を締め、小さく頷く。
「きつくはないか?」
「だ、大丈夫です……」
恥ずかしくて、顔を両手で覆うレティシア。そんなレティシアの反応を首を傾げてみるセシリアスタに、ヤードはやれやれと溜息を吐いた。
その後も、帽子屋にも寄り何点か見繕われた。自分のものだけでどれくらいセシリアスタが散財したのか、考えたくもない。レティシアは先程購入して貰った白いスラウチ・ハットで顔を隠しながら、肩を抱くセシリアスタへ小さく溜息を吐いた。
「ここが最後だ」
そう言って、セシリアスタが連れてきたのはジャスミンの店の向かいにあるジュエリー店だった。
「そんな、これ以上はもう大丈夫ですよっ」
「大事なものを受け取りに来ただけだ」
言いながら、セシリアスタは店のドアを開けた。可愛らしいベルが鳴り響く。
「いらっしゃ~い」
「え、ジャスミンさん!?」
店の奥から出てきたのは、二の腕と胸筋の逞しい大柄な男性だった。唇には淡い口紅が塗られ、ライトブラウンの髪をオールバックに纏めた薄いライトグリーンの瞳をした男性。最初に出会ったジャスミンとそっくりな男性に、レティシアは目を見開いた。
「あら。それ、ジャスミンの所の服じゃない。じゃあ自己紹介しなきゃね。私はオリビア。ジャスミンは私の弟よ」
ウインクしながら挨拶をしてくる男性に、レティシアは勘違いをしてしまったと気付く。
「す、すみませんっ。勘違いしてしまって……」
「しかたがないわ~。双子だもの。瞳の色と使える魔法属性は違うから、そこで見分けて頂戴な」
確かに、ジャスミンはライトブルーの瞳だった。オリビアはライトグリーン。それ以外は外見では見分けがつかないくらいそっくりだ。
(私とスフィアとは大違いね……)
今、スフィアはどうしているのだろうか。その場の勢いで家を出てきてしまったから、心配でならない。
「オリビア、頼んでいたものは出来たか?」
「言われた通り、超特急でしあげましたよ苦労したんですからね~」
文句を言いながら、オリビアは鍵のかかった棚の鍵を開け、小さな箱を取り出す。セシリアスタはそれを受け取り、レティシアへと向き直る。
「レティシア嬢、最後にこれを、君に」
開けられた箱からは、髪飾りが出てきた。真ん中には光の反射によって虹色にも見える大きな花があしらわれ、その花の両隣には藍色よりも深い色の小さな花が一輪ずつあしらわれている。
「これは……」
あまりにも綺麗な髪飾りを、レティシアはじっと見つめる。微かにだが魔力の感じられるそれをセシリアスタは静かに取り出した。
「指輪はサイズがわからなくてね……私が生成した魔石を加工して貰った」
そっとレティシアの背後に回り、帽子を取る。今付けている薔薇の髪飾りを外し、セシリアスタは持っていた髪飾りを付けた。
「婚約指輪の代わり、ということにしておいてくれ」
「セシル様……」
付けられた髪飾りに、手を触れる。セシリアスタの魔力が、温かく感じられた。パーティーの時に見た、あの時レティシアの手を掴んだ時と同じ顔を向けられ、レティシアは涙が零れそうになった。『不良品』の自分に、ここまでしてくれた人は今までいなかった。両親でさえ、レティシアに服もアクセサリーも買ってはくれなかった。なのに、セシリアスタはこうも自分を見てくれる。それがどれだけ嬉しいことか。
レティシアは涙を手で拭い、セシリアスタへと顔を向ける。
「……ありがとうございます、セシル様」
今出来る最大の感謝を。そう思いながら、レティシアは微笑んだ。
「ヤード、彼女に合う靴を幾つか見繕ってくれ」
セシリアスタの言葉に、店主である初老の男性は「わかりました、若旦那」と言いレティシアの足のサイズを測りだす。
「先程から気になったのですが……『若旦那』とは?」
「行きつけの店の店主は皆、私のことをそう呼ぶのさ」
微笑みながら、セシリアスタは答える。先程の店も、セシリアスタの行きつけらしい。ジャスミンの店には男性物がなかったが、オーダーメイドで頼んでいるのだろうか? そう考えていると、ヤードは店の奥からレティシアの足のサイズと同じ靴を何点か持ってきた。
ブーティーやチャッカ・ブーツ、カッター・ブーツやストラップシューズなど、どの服にも合わせやすい茶色や黒だけでなく、赤や水色などの鮮やかな色の靴も出された。
「うん、全て買おう」
「セシル様っ」
またしてもセシリアスタは全て買うと言い出す。レティシアは困ると言いかけるが、再び「プレゼントしたい」と言われてしまい、言葉を返すことも出来なかった。
「あ」
店の奥側に、可愛らしい赤茶色のレースアップ・ブーツがあった。綺麗に誂えられた靴を見て、つい声が出てしまった。それに気付いたセシリアスタは、その靴を指指した。
「ヤード、その靴でレティシア嬢に合うサイズはあるか」
「そうですね……確かにその靴はお嬢さんに合うサイズですが、あちら一点だけしか残ってなくて」
その言葉を聞き、セシリアスタは悩む。レティシアが気に入った以上、買ってやりたい。そう思ったセシリアスタは、「構わない」と言葉を続ける
「磨いてくれ」
「了解いたしました」
ヤードに丁寧に磨いてもらい、差し出されたブーツ。セシリアスタはそっと跪き、レティシアの足へと履かせる。
「せ、セシル様! 自分で、自分で出来ますからっ」
恥ずかしくなり、慌てて制止させようとするが、セシリアスタはそんなことはお構いなしにとレティシアの白磁のような足へ履かせる。靴紐を締め、小さく頷く。
「きつくはないか?」
「だ、大丈夫です……」
恥ずかしくて、顔を両手で覆うレティシア。そんなレティシアの反応を首を傾げてみるセシリアスタに、ヤードはやれやれと溜息を吐いた。
その後も、帽子屋にも寄り何点か見繕われた。自分のものだけでどれくらいセシリアスタが散財したのか、考えたくもない。レティシアは先程購入して貰った白いスラウチ・ハットで顔を隠しながら、肩を抱くセシリアスタへ小さく溜息を吐いた。
「ここが最後だ」
そう言って、セシリアスタが連れてきたのはジャスミンの店の向かいにあるジュエリー店だった。
「そんな、これ以上はもう大丈夫ですよっ」
「大事なものを受け取りに来ただけだ」
言いながら、セシリアスタは店のドアを開けた。可愛らしいベルが鳴り響く。
「いらっしゃ~い」
「え、ジャスミンさん!?」
店の奥から出てきたのは、二の腕と胸筋の逞しい大柄な男性だった。唇には淡い口紅が塗られ、ライトブラウンの髪をオールバックに纏めた薄いライトグリーンの瞳をした男性。最初に出会ったジャスミンとそっくりな男性に、レティシアは目を見開いた。
「あら。それ、ジャスミンの所の服じゃない。じゃあ自己紹介しなきゃね。私はオリビア。ジャスミンは私の弟よ」
ウインクしながら挨拶をしてくる男性に、レティシアは勘違いをしてしまったと気付く。
「す、すみませんっ。勘違いしてしまって……」
「しかたがないわ~。双子だもの。瞳の色と使える魔法属性は違うから、そこで見分けて頂戴な」
確かに、ジャスミンはライトブルーの瞳だった。オリビアはライトグリーン。それ以外は外見では見分けがつかないくらいそっくりだ。
(私とスフィアとは大違いね……)
今、スフィアはどうしているのだろうか。その場の勢いで家を出てきてしまったから、心配でならない。
「オリビア、頼んでいたものは出来たか?」
「言われた通り、超特急でしあげましたよ苦労したんですからね~」
文句を言いながら、オリビアは鍵のかかった棚の鍵を開け、小さな箱を取り出す。セシリアスタはそれを受け取り、レティシアへと向き直る。
「レティシア嬢、最後にこれを、君に」
開けられた箱からは、髪飾りが出てきた。真ん中には光の反射によって虹色にも見える大きな花があしらわれ、その花の両隣には藍色よりも深い色の小さな花が一輪ずつあしらわれている。
「これは……」
あまりにも綺麗な髪飾りを、レティシアはじっと見つめる。微かにだが魔力の感じられるそれをセシリアスタは静かに取り出した。
「指輪はサイズがわからなくてね……私が生成した魔石を加工して貰った」
そっとレティシアの背後に回り、帽子を取る。今付けている薔薇の髪飾りを外し、セシリアスタは持っていた髪飾りを付けた。
「婚約指輪の代わり、ということにしておいてくれ」
「セシル様……」
付けられた髪飾りに、手を触れる。セシリアスタの魔力が、温かく感じられた。パーティーの時に見た、あの時レティシアの手を掴んだ時と同じ顔を向けられ、レティシアは涙が零れそうになった。『不良品』の自分に、ここまでしてくれた人は今までいなかった。両親でさえ、レティシアに服もアクセサリーも買ってはくれなかった。なのに、セシリアスタはこうも自分を見てくれる。それがどれだけ嬉しいことか。
レティシアは涙を手で拭い、セシリアスタへと顔を向ける。
「……ありがとうございます、セシル様」
今出来る最大の感謝を。そう思いながら、レティシアは微笑んだ。