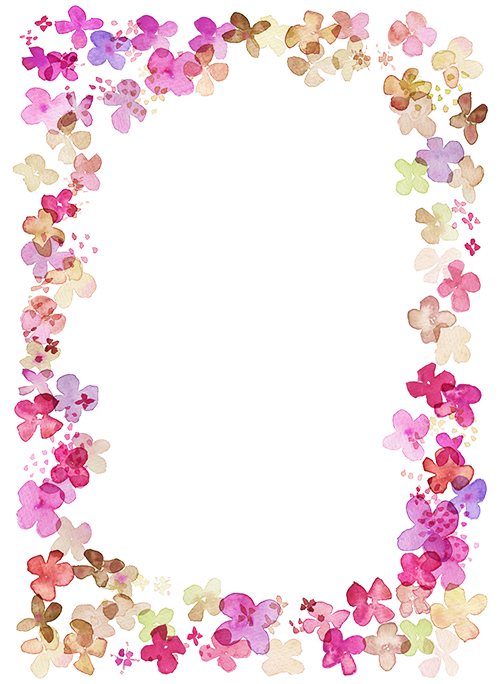部屋に戻り、先程隠していたティーセットを片していたカイラに背後から抱き着く。
「お、お嬢様っ!?」
突然の主の行動に驚きつつ、カイラはレティシアの好きにさせる。そんなカイラの優しさが嬉しくて、でも逆に辛くて、暫くの間ギュッと抱き付いていた。
「ごめんなさい、急に抱き着いて……」
「大丈夫ですよ。でも、お買い物は?」
カイラの言葉に、微かに目を伏せ小さく微笑む。レティシアのその行動で察したカイラは、怒りに魔力を放出しだす。火属性特有の赤い魔力がカイラから燃え盛るように噴き出した。
「あんの糞餓鬼! 今日という今日は許さないっ」
「カイラ、いいの」
「いい訳ないですよっ! お嬢様のドレスなんて、一度も新調されたことがないのに……あっ」
言った直後、カイラは顔を顰め「すみません……」と謝罪する。レティシアは目を瞑り首を横に振った。
「気にしないで。私にはお下がりだけどドレスは沢山あるわ」
「でも……」
自分の過ぎた言葉で主であるレティシアを傷つけてしまったと悲しむカイラに、レティシアは大丈夫だと微笑んでみせる。
「そんなことより、ドレスの直しをしましょう。少し補修が必要なものもあるけれど、どれも素敵なものばかりだわ」
双子とはいえ、多少なりとも成長に差が出る年頃だ。補修が必要なドレスもある。すぐ側のクローゼットを開け、ドレスを確認しだす。カイラも隣に立ち、どれを補修するか考える。
「やっぱり一番はこのドレスですかね? お嬢様の髪色にも合いますし、他のドレスより直し易いかと思います」
カイラが取り出したのは、新緑色のネックラインが大きくカットされたフルレングスタイプのドレスだった。袖口は薄い白のレースとギャザーが寄せられ、ふんだんにフリルがあしらわれている。腰にはワンポイントのように大きなリボンが付けられており、スカートの裾にはスフィアの好みに合わせ小さなリボンが沢山あしらわれてあった。
スフィアには色合いが気に入らないとの理由で寄越されたドレスだ。
「そうね……これを直しましょう」
そう言うと、レティシアはドレスを手に取り椅子に座り、胸に手を当てて静かに目を閉じた。小さく息を吐き、意識を集中させていく。すると、レティシアの体が淡く光り輝きだした。
「綺麗……」
光を纏うレティシアの姿に、カイラは目を輝かせ小さく呟く。煌々と輝く光は静かに胸元に収束していき、レティシアはゆっくりと目を開けた。
「うん、上出来ね」
胸元に当てていた手の中には、直径五センチ程の白い丸型の魔石が生み出されていた。レティシアが唯一出来る、魔石の生成だ。魔法は地、水、火、風の四大属性から派生している。レティシアはその四大属性のどれも使うことが出来ないが、自身の魔力を結晶化させる魔石生成だけならば簡単に出来るのだ。
(スフィアは確か地と風が使えると言っていたわね……)
スフィアは二つの属性が扱える。といっても、複数の属性を使いこなすのは相当の修練が必要となるので、スフィアは未だ中級の魔法までしか使えないと他の従者達から聞いていた。だが、それでも二大属性を使えるのは事実である。どちらかと言えば得意なのが風属性というのもあり、相性の不利なカイラを苦手としている節があった。
(そういえば、魔導公爵様は全ての属性が使える御方なのよね)
魔導公爵――。来週のパーティーの主催者であり、このグリスタニア最強の魔導士だ。四大魔法だけでなく、過去に失われたとされる古代魔法をも使用することが出来ると耳にしたことがある。若干十六歳にして公爵の地位を授かった天才。魔導以外は興味がなく、婚姻にも関心がなかった為に王宮が何度も婚姻を打診していた筈だ。
「だからパーティーを開くという話になったのね……」
「何か言いましたか?」
「ううん、何でもないわ」
カイラがサイドチェストの一番下の引き戸から、小さな機械を持ってくる。それを受け取ると、端の窪みに魔石を嵌め込んだ。反対側には、今回生成した魔石よりも大きな白い丸型の魔石が嵌め込まれてある。
「さて、今回もお願いね」
機械を優しく撫で、大きな魔石に魔力を送る。すると機械が動き出し、カラカラと音を立てながら魔石から糸を紡ぎ出し始めた。
「もう何年も使ってるのに壊れないですね」
「それだけこの糸紡ぎが頑丈なのよ」
目の前で魔石から魔糸を紡ぎ出す糸紡ぎ機に感心するカイラに、レティシアは微笑む。これは社交界にデビューしたての頃、こっそり魔石を生成し、それをカイラに売って来て貰ったお金で買った魔道具だ。その頃からドレスは全てお下がりだったレティシアは、少しでもものを大切にしようと考え、カイラに相談してこの機械の存在を知ったのである。これは魔力の少ない者の為に開発されたものであり、魔法で栄えたグリスタニアだからこそ生み出された代物だ。補修や刺しゅうは他のメイド達からこっそり教わり、今ではレティシアの趣味の一つになっている程でもあった。
「うん、今回もちゃんと出来てるわね」
紡がれた白い魔糸を伸ばし、しっかりと出来ているのを確認するレティシア。これだけあれば十分だろう。早速、膝に置かれたドレスに手を伸ばした。
まずはスカートの裾にふんだんに付けられたリボンを取り外していく。ドレスの裾を切らないよう、慎重に切り取っていった。全てのリボンを取り外すと、今度は針を取り出し魔糸を針の穴に通す。一定の長さに切り、リボンの付けられていた所を隠すように薔薇の刺しゅうを施していく。一週間で完成させなくてはならない。間に合わせるように、慎重に、それでいて手早く、針を布地に刺していった。
そんなレティシアの邪魔にならないよう、カイラは静かに部屋を出る。
「さてっ、私はお嬢様にお出しするお茶を用意しなくちゃ!」
鼻歌交じりに、カイラは主に出すお茶を用意し出すのだった。
数刻後、スフィアとユノアは買い物から帰ってくると、父スルグの元に向かったようだ。嫌な予感がするが、どうしようも出来ないことだろうと内心溜息を吐く。案の定、使用人のクラリックが父の元へ行くようにと伝えてきた。
「申し訳ございません、お嬢様……」
心底申し訳なさそうに謝罪してくるクラリックに、レティシアは微笑みかける。
「あなたが謝罪する必要はないわ。ありがとう、心配してくれて」
笑顔を向けると、ホッとしたように安堵の表情を浮かべるクラリック。彼もカイラ同様、幼い頃からこの家に仕えてくれている従者だ。亜麻色の髪が特徴的で、何時も遠回しにだがサポートしてくれる存在。そんな彼について行く為、ドレスを椅子に置き部屋を後にした。
「お嬢様、どちらに?」
部屋を出てすぐに、ティーセットを持ってきたカイラと遭遇する。きっとお父様に呼ばれている間にスフィアが部屋に来る筈。杞憂に終わって欲しいが、確証がない以上カイラに頼るしかない。
「カイラ、お父様に呼ばれたから行ってくるわ。部屋の方をお願い」
「了解しました。お嬢様の部屋には誰一人立ち入らせませんっ」
「ありがとう、カイラ」
カイラの言葉が、こんなにも頼もしいと思うのは気の所為ではないだろう。レティシアは感謝の言葉を述べ、父の居る書斎へと歩を進めた。
「お父様、レティシアです」
ノックをして、スルグの返事を待つ。寸刻すると「入りなさい」と声がかかった。
「失礼します」
書斎に入ると、母ユノアと共にスルグが立って此方を睨んでいた。やはり、スフィアの姿がない。
「レティシア、お前はまたスフィアに対して嫌がらせをしたそうだな」
「お言葉ですがお父様、私は何もしては……」
「お前の言葉など聞いていない!」
言葉を遮られ、大声で怒鳴り散らされる。ビクリと体が震えた。
「不良品のお前なぞ、何時でも追い出すことは出来る! それをしないのはスフィアがお前を憐れんでいるからだ! それなのにお前という奴は……なんて恩知らずなんだ!」
『不良品』。親の口から発せられると、どうしてここまで痛みが大きいのだろうか。レティシアは小さく唇を噛み締めながら、言葉の暴力に耐えた。
「本来ならば何時も同様に体に教え込ませたい所だが、来週のパーティーに支障が出る。感謝するのだな」
「はい……」
何時も同様に、か……。握りしめている手を見る限り、本当ならば今この場で頬を殴り付けたい所なのだろう。レティシアは内心ホッと息を吐いた。
「お前は今日は食事は抜きだ。明日まで自室から出るのを禁じる。その間スフィアへの暴言を反省していなさい」
「……わかりました」
話は終わったとばかりに、レティシアに背を向けるスルグ。レティシアは深々と頭を垂れると、書斎を後にした。
「お嬢様、大丈夫でしたかっ」
自室へ戻ると、カイラが部屋の入り口で待っていてくれた。カイラの顔を見るとホッと安堵してしまうのは何故だろうか。二人で自室に入り、扉を閉める。
「大丈夫よ。今晩は食事抜きと言われてしまったくらいで、特に問題ないわ」
「問題ありまくりですよ! あの爺……もう勘弁ならんっ」
「カイラ、落ち着いて……っ」
何時ものパターンになりかけ、慌てて部屋の扉の前に立つレティシア。
「今日は叩かれてもいないわ。だから落ち着いて」
「ぐううううっ、お嬢様がそう言うならば、もの凄く、本当にもの凄く嫌ですが言う通りにします……」
「ありがとう」
ホッと安堵し、レティシアは微笑んだ。父に叩かれなかったのは本当に良かった。もし叩かれていたら、怪我の具合によってはドレスの補修が間に合わなくなったかもしれない。
「さあ、補修しなきゃ。今日は食事のことも考えずに作業に没頭できるから助かるわ」
「うううっ、お夜食絶対に持ってきますからね! お嬢様っ」
涙ながらに約束するカイラに、レティシアは満面の笑みを向ける。使用人達が味方で、本当に良かった。
「何時もありがとうね、カイラ」
椅子に座り針を手に取りながら、レティシアは笑みを浮かべた。スフィアはカイラが部屋にいたからか、来なかったようで、それが救いだった。
それからというもの、レティシアは部屋に籠りきった。スフィアから遠ざかるのも半分あったが、何よりドレスを完成させるのが目的だったからだ。補修を始めて五日が経ち、漸く、ドレスの刺しゅうが終わりを迎える。
「良かった……やっと終わった」
針を針刺しに通し、糸の始末をする。ドレスのスカートの裾には全体に薔薇の刺しゅうが施され、新たな装いへと姿を変えた。
少し前に貰ったばかりというのもあり、他に直す所はない。レティシアは深く息を吐き、疲れた眼を労わり目頭を押さえ安堵する。
「良かったです本当にっ」
「カイラの補助があったから出来たのよ」
ありがとう、と言葉をかけると、カイラは力強く首を横に振った。
「お嬢様のお力ですよ!」
「そう言って貰えると頑張った甲斐があったわ」
互いに笑みを浮かべ、微笑みあう。直しの終えたドレスをクローゼットに仕舞い、鍵を閉めた。
信用していない訳ではないが、スフィアが何もして来ないとは限らない。用心に越したことはない筈だ。
「後は何も起きないといいのだけど……」
この五日間、スフィアが何もしてこなかったのが不思議でならない。きっと、毎日私に行っていた嫌がらせが出来ていないからストレスが溜まっていてもおかしくはないのだ。一抹の不安を抱えながら、部屋を出る。
久方ぶりに食事以外で自室から出たが、特に変わったことはなさそうだ。使用人達の顔色を窺っても、何か変化があったとは感じられない。
「――あら、お姉さま」
「スフィア……」
まるで張り込んでいたかのようなタイミングで、スフィアと遭遇してしまう。嫌な予感しかしない。
「お嬢様はお疲れなので、失礼しても宜しいでしょうか」
レティシアを庇うように、カイラがスフィアの前に立つ。スフィアはフン、と鼻を鳴らし、手であしらった。
「私はお姉さまに用があるの……使用人の分際で私の前に立つんじゃないわよ」
「ありがとう、カイラ」
「お嬢様っ」
庇ってくれていたカイラの腕に手を添え、礼を述べるレティシア。これ以上スフィアを刺激すれば、確実にカイラに悪いことが起こる。それだけは嫌だ。カイラの前に立ち、スフィアと対峙する。
「私に用ってなにかしら」
「お姉さまに差し上げた緑のドレス、返してくださらない?」
「!?」
突然の言葉に、目を見開いた。大方、風魔法で室内を覗いていたのだわ……。レティシアはスフィアを刺激しないよう、丁寧に断った。
「悪いのだけど、あのドレスは私のサイズに手直ししてしまったの。スフィアの体型に合わせて直すにはパーティーに間に合わないわ」
「は? 双子なんだからサイズなんて大して変わらないでしょ。いいから返して。元は私のドレスよ」
「あれは私がパーティーに着ていくドレスなの。スフィアにはお母様と買い物に行って選んだドレスがあるでしょう?」
宥めるように話を進めていくが、どうにもあのドレスを返して欲しいらしい。大方、嫌がらせの口実に使われているのだろうが、それでもカイラと共に頑張って手直ししたドレスだ。渡す訳にはいかない。レティシアはスフィアにキッときつく視線を合わせた。
「な、何よ……『不良品』のお姉さまが、私にたてつこうっていうの!?」
「そんなことはしないわ。でもあのドレスだけは渡せない。お願いだから諦めてちょうだい」
普段なら抵抗も反抗もしてこないに……! スフィアは下唇を噛み締め怒りに顔を歪ませた。
「そんなにいうなら要らないわよ! あんな『不良品』のドレス、『不良品』のお姉さまにお似合いだわ!」
「っ」
廊下に、乾いた音が響く。スフィアの言葉についカッとなってしまい、頬を叩いてしまった。私が『不良品』と言われるのは我慢できるが、丹精込めて作られたあの素敵なドレスを『不良品』扱いするのは、製作者への暴言だ。そう思ったら、考えることよりも先に体が動いてしまった。
頬を叩かれたスフィアは、叩かれた方の頬に手を当てる。一瞬呆気に取られたが、すぐさま口角を上げ、深い嫌な笑みを浮かべた。
「きゃああああああ!」
突然叫び、その場に蹲った。しまった、そう思ったが時既に遅く、母がスフィアの声を聞きつけ走ってきた。
「スフィア! 一体どうしたのっ」
駆けつけてみれば、母ユノアの目にはには頬を押さえて蹲るスフィアと目の前に居るレティシアの姿が映るだろう。そうなれば、言わずもがなスフィアを優遇する両親のとる行動は一つだ。
「レティシア、またお前ですか」
「っ」
母ユノアの声と共に、魔力が放出される。風属性特有の緑の光がユノアを包み込む。
「お母さまっ、お姉さまが私を叩いたの! お前ばかりドレスを新調して貰って生意気なんだってっ」
「ちがっ、私はそんなこと言ってない!」
頭を振りながら、無実を訴えるレティシア。だがレティシアの言葉を信じないユノアは、スフィアの肩を抱き締め赤くなった頬に手を添えた。
「可哀想に、こんなに赤くなるくらいの力で叩くなんて……レティシア」
「お母様、話を聞いてください」
「お前の話など聞きたくもありません」
ピシャリと言い切られ、レティシアは言葉を詰まらせる。どうして、私の言葉は聞いてくれないの?
「レティシア」
突然の父の声に、背後を振り返る。振り返った瞬間、頬に強い衝撃が走り気付いた時には床に倒れていた。
「っ……」
倒れてから、父スルグに頬を殴られたのだと理解する。殴られた頬がジンジンと熱を持ち、口内は血の味がした。
「お嬢様っ」
カイラが駆け寄ろうとするのを、クラリックが制する。今ここで動いたら危険だ。クラリックの行動に感謝した。
髪を掴まれ、顔を無理矢理上げさせられる。殴られた痛みからして、父は拳にエンチャント魔法を付与して殴ってきたようだ。未だ痛む頬に、表情が歪む。
「今日まで耐えてきたが、スフィアに手を出したことには堪忍袋の緒が切れるわ。この『不良品』が!」
「っ」
勢いよく髪を引っ張られ、何本か髪が千切れる音がした。痛みに歪む顔で父の顔を見ると、怒りで我を失いかけているように見えた。
「まだそんな顔をするか! お前なぞ、こうしてやるわ!」
「っ」
拳を振りかざされ、ぎゅっと目を閉じて衝撃に備える。だが衝撃も痛みも襲ってこない。恐る恐る、目を開けた。
「旦那様、これ以上の騒ぎは明後日のパーティーに支障がでます」
スルグの手を止めていたのは、クラリックだった。
「放せっ、使用人の癖に私に指図するつもりか!」
「招待状には既にスフィアお嬢様だけでなくレティシアお嬢様の名前も記載してお返事を返しておいでです。それなのにお二方の顔に傷があるのは旦那様としても困るのでは?」
クラリックの言葉に、スルグは唸り歯軋りしながら拳を下ろす。レティシアの髪を掴んでいた手も解かれ、レティシアは床に尻もちをついた。
「クラリック、その『不良品』の手当てでもしておけ」
「はい」
ユノアがスフィアを支えながら起こし、三人はその場を去っていく。ホッとしたレティシアに、カイラが急いで駆け寄ってきた。
「お嬢様っ」
ぐしゃぐしゃになった髪の毛、大きく腫れた頬。主のあまりの酷い姿に、カイラは涙を零した。
「うう……っ、あんまりですよぉ……お嬢様は何も悪いことしてないのにっ」
「カイラ……」
自分は、痛みにも慣れてしまった。涙も堪えられる。そんな自分の代わりに、カイラは何時も泣いたり怒ったりしてくれる。カイラがいてくれたから、自分はここまでやってこれたんだ。
「……ありがとう、カイラ」
「お嬢様っ」
カイラの背に腕を回し、ぎゅっと抱き締める。両親も妹もくれない愛情を、カイラを始めとした使用人達がくれた。私は幸せ者なんだ。レティシアは涙を堪えながら、抱き締める手に力を籠めた。
「お嬢様、カイラ。部屋に戻りましょう。傷の手当てをします」
「そうね、クラリック」
クラリックの言葉に、カイラと共に立ち上がる。すぐ側の自室に入り、ドアを閉めた。
「いたっ……」
クラリックの手が頬に触れる。触れただけで痛むということは、相当に腫れているのだろう。普段ならば鏡を持ってくるカイラが鏡を持ってこないのもそれを裏付ける。クラリックは小さく呪文を詠唱すると、頬に水の塊がスライムの様に張り付いた。暫くはこれで腫れが引くのを待つしかない。
「痛みますが、パーティーまでには腫れは引くかと思います」
「ありがとう」
「後は薬草ティーを飲んで治るのを待ちましょう」
クラリックは、何時も父や母に叩かれたりした時に治療をしてくれている。父の従者でありながら、何かと面倒を看てくれているのだ。
「申し訳ないですお嬢様っ、私が水属性なら少しはお役に立てるのに……っ」
「カイラが謝る必要はないわ。カイラにはカイラの良さがあるもの」
この世界には、完全なる魔法での治療は不可能だ。風属性や水属性は薬草を応用して大々的な治療が出来、地属性ならば効果の高い薬草を育てることは可能である。だが、魔法だけでの治癒は多くの魔法使いが研究をしても成されていないことだ。
カイラの扱える火属性は治療には向いていない。それが歯がゆいらしい。カイラには何時も救われている。そんなに気にしないで欲しい。レティシアはそう思いを込めて微笑んだ。
「っ、薬草ティー、今すぐ作ってきます!!」
いてもたってもいられなかったのか、カイラは勢いよく立ち上ががり室内から出て行った。あの元気に救われる。そう、思えた。
「お嬢様」
「何かしら」
すぐ側で立って待機しているクラリックを見上げる。クラリックは表情を曇らせ、深々と頭を垂れた。
「クラリック!」
「先程の主の無礼、本当に申し訳ありません」
「顔を上げてっ、もしスフィアがこの部屋を覗いていたらあなたが大変な目に遭うわ」
慌てて、レティシアは顔を上げさせる。だが、クラリックの表情は変わらなかった。悔しさを押し殺しているような、そんな表情にも見える。
「ですが、私は目の前でお嬢様が虐げられているのにも関わらず……」
「ううん、最後は止めてくれたでしょ。それで十分よ」
だから、そんな顔をしないで欲しい――。レティシアは大丈夫と伝えるように、微笑んで見せた。
「……ありがとう、ございます」
クラリックは再び頭を垂れ、感謝を述べたのだった。
「お、お嬢様っ!?」
突然の主の行動に驚きつつ、カイラはレティシアの好きにさせる。そんなカイラの優しさが嬉しくて、でも逆に辛くて、暫くの間ギュッと抱き付いていた。
「ごめんなさい、急に抱き着いて……」
「大丈夫ですよ。でも、お買い物は?」
カイラの言葉に、微かに目を伏せ小さく微笑む。レティシアのその行動で察したカイラは、怒りに魔力を放出しだす。火属性特有の赤い魔力がカイラから燃え盛るように噴き出した。
「あんの糞餓鬼! 今日という今日は許さないっ」
「カイラ、いいの」
「いい訳ないですよっ! お嬢様のドレスなんて、一度も新調されたことがないのに……あっ」
言った直後、カイラは顔を顰め「すみません……」と謝罪する。レティシアは目を瞑り首を横に振った。
「気にしないで。私にはお下がりだけどドレスは沢山あるわ」
「でも……」
自分の過ぎた言葉で主であるレティシアを傷つけてしまったと悲しむカイラに、レティシアは大丈夫だと微笑んでみせる。
「そんなことより、ドレスの直しをしましょう。少し補修が必要なものもあるけれど、どれも素敵なものばかりだわ」
双子とはいえ、多少なりとも成長に差が出る年頃だ。補修が必要なドレスもある。すぐ側のクローゼットを開け、ドレスを確認しだす。カイラも隣に立ち、どれを補修するか考える。
「やっぱり一番はこのドレスですかね? お嬢様の髪色にも合いますし、他のドレスより直し易いかと思います」
カイラが取り出したのは、新緑色のネックラインが大きくカットされたフルレングスタイプのドレスだった。袖口は薄い白のレースとギャザーが寄せられ、ふんだんにフリルがあしらわれている。腰にはワンポイントのように大きなリボンが付けられており、スカートの裾にはスフィアの好みに合わせ小さなリボンが沢山あしらわれてあった。
スフィアには色合いが気に入らないとの理由で寄越されたドレスだ。
「そうね……これを直しましょう」
そう言うと、レティシアはドレスを手に取り椅子に座り、胸に手を当てて静かに目を閉じた。小さく息を吐き、意識を集中させていく。すると、レティシアの体が淡く光り輝きだした。
「綺麗……」
光を纏うレティシアの姿に、カイラは目を輝かせ小さく呟く。煌々と輝く光は静かに胸元に収束していき、レティシアはゆっくりと目を開けた。
「うん、上出来ね」
胸元に当てていた手の中には、直径五センチ程の白い丸型の魔石が生み出されていた。レティシアが唯一出来る、魔石の生成だ。魔法は地、水、火、風の四大属性から派生している。レティシアはその四大属性のどれも使うことが出来ないが、自身の魔力を結晶化させる魔石生成だけならば簡単に出来るのだ。
(スフィアは確か地と風が使えると言っていたわね……)
スフィアは二つの属性が扱える。といっても、複数の属性を使いこなすのは相当の修練が必要となるので、スフィアは未だ中級の魔法までしか使えないと他の従者達から聞いていた。だが、それでも二大属性を使えるのは事実である。どちらかと言えば得意なのが風属性というのもあり、相性の不利なカイラを苦手としている節があった。
(そういえば、魔導公爵様は全ての属性が使える御方なのよね)
魔導公爵――。来週のパーティーの主催者であり、このグリスタニア最強の魔導士だ。四大魔法だけでなく、過去に失われたとされる古代魔法をも使用することが出来ると耳にしたことがある。若干十六歳にして公爵の地位を授かった天才。魔導以外は興味がなく、婚姻にも関心がなかった為に王宮が何度も婚姻を打診していた筈だ。
「だからパーティーを開くという話になったのね……」
「何か言いましたか?」
「ううん、何でもないわ」
カイラがサイドチェストの一番下の引き戸から、小さな機械を持ってくる。それを受け取ると、端の窪みに魔石を嵌め込んだ。反対側には、今回生成した魔石よりも大きな白い丸型の魔石が嵌め込まれてある。
「さて、今回もお願いね」
機械を優しく撫で、大きな魔石に魔力を送る。すると機械が動き出し、カラカラと音を立てながら魔石から糸を紡ぎ出し始めた。
「もう何年も使ってるのに壊れないですね」
「それだけこの糸紡ぎが頑丈なのよ」
目の前で魔石から魔糸を紡ぎ出す糸紡ぎ機に感心するカイラに、レティシアは微笑む。これは社交界にデビューしたての頃、こっそり魔石を生成し、それをカイラに売って来て貰ったお金で買った魔道具だ。その頃からドレスは全てお下がりだったレティシアは、少しでもものを大切にしようと考え、カイラに相談してこの機械の存在を知ったのである。これは魔力の少ない者の為に開発されたものであり、魔法で栄えたグリスタニアだからこそ生み出された代物だ。補修や刺しゅうは他のメイド達からこっそり教わり、今ではレティシアの趣味の一つになっている程でもあった。
「うん、今回もちゃんと出来てるわね」
紡がれた白い魔糸を伸ばし、しっかりと出来ているのを確認するレティシア。これだけあれば十分だろう。早速、膝に置かれたドレスに手を伸ばした。
まずはスカートの裾にふんだんに付けられたリボンを取り外していく。ドレスの裾を切らないよう、慎重に切り取っていった。全てのリボンを取り外すと、今度は針を取り出し魔糸を針の穴に通す。一定の長さに切り、リボンの付けられていた所を隠すように薔薇の刺しゅうを施していく。一週間で完成させなくてはならない。間に合わせるように、慎重に、それでいて手早く、針を布地に刺していった。
そんなレティシアの邪魔にならないよう、カイラは静かに部屋を出る。
「さてっ、私はお嬢様にお出しするお茶を用意しなくちゃ!」
鼻歌交じりに、カイラは主に出すお茶を用意し出すのだった。
数刻後、スフィアとユノアは買い物から帰ってくると、父スルグの元に向かったようだ。嫌な予感がするが、どうしようも出来ないことだろうと内心溜息を吐く。案の定、使用人のクラリックが父の元へ行くようにと伝えてきた。
「申し訳ございません、お嬢様……」
心底申し訳なさそうに謝罪してくるクラリックに、レティシアは微笑みかける。
「あなたが謝罪する必要はないわ。ありがとう、心配してくれて」
笑顔を向けると、ホッとしたように安堵の表情を浮かべるクラリック。彼もカイラ同様、幼い頃からこの家に仕えてくれている従者だ。亜麻色の髪が特徴的で、何時も遠回しにだがサポートしてくれる存在。そんな彼について行く為、ドレスを椅子に置き部屋を後にした。
「お嬢様、どちらに?」
部屋を出てすぐに、ティーセットを持ってきたカイラと遭遇する。きっとお父様に呼ばれている間にスフィアが部屋に来る筈。杞憂に終わって欲しいが、確証がない以上カイラに頼るしかない。
「カイラ、お父様に呼ばれたから行ってくるわ。部屋の方をお願い」
「了解しました。お嬢様の部屋には誰一人立ち入らせませんっ」
「ありがとう、カイラ」
カイラの言葉が、こんなにも頼もしいと思うのは気の所為ではないだろう。レティシアは感謝の言葉を述べ、父の居る書斎へと歩を進めた。
「お父様、レティシアです」
ノックをして、スルグの返事を待つ。寸刻すると「入りなさい」と声がかかった。
「失礼します」
書斎に入ると、母ユノアと共にスルグが立って此方を睨んでいた。やはり、スフィアの姿がない。
「レティシア、お前はまたスフィアに対して嫌がらせをしたそうだな」
「お言葉ですがお父様、私は何もしては……」
「お前の言葉など聞いていない!」
言葉を遮られ、大声で怒鳴り散らされる。ビクリと体が震えた。
「不良品のお前なぞ、何時でも追い出すことは出来る! それをしないのはスフィアがお前を憐れんでいるからだ! それなのにお前という奴は……なんて恩知らずなんだ!」
『不良品』。親の口から発せられると、どうしてここまで痛みが大きいのだろうか。レティシアは小さく唇を噛み締めながら、言葉の暴力に耐えた。
「本来ならば何時も同様に体に教え込ませたい所だが、来週のパーティーに支障が出る。感謝するのだな」
「はい……」
何時も同様に、か……。握りしめている手を見る限り、本当ならば今この場で頬を殴り付けたい所なのだろう。レティシアは内心ホッと息を吐いた。
「お前は今日は食事は抜きだ。明日まで自室から出るのを禁じる。その間スフィアへの暴言を反省していなさい」
「……わかりました」
話は終わったとばかりに、レティシアに背を向けるスルグ。レティシアは深々と頭を垂れると、書斎を後にした。
「お嬢様、大丈夫でしたかっ」
自室へ戻ると、カイラが部屋の入り口で待っていてくれた。カイラの顔を見るとホッと安堵してしまうのは何故だろうか。二人で自室に入り、扉を閉める。
「大丈夫よ。今晩は食事抜きと言われてしまったくらいで、特に問題ないわ」
「問題ありまくりですよ! あの爺……もう勘弁ならんっ」
「カイラ、落ち着いて……っ」
何時ものパターンになりかけ、慌てて部屋の扉の前に立つレティシア。
「今日は叩かれてもいないわ。だから落ち着いて」
「ぐううううっ、お嬢様がそう言うならば、もの凄く、本当にもの凄く嫌ですが言う通りにします……」
「ありがとう」
ホッと安堵し、レティシアは微笑んだ。父に叩かれなかったのは本当に良かった。もし叩かれていたら、怪我の具合によってはドレスの補修が間に合わなくなったかもしれない。
「さあ、補修しなきゃ。今日は食事のことも考えずに作業に没頭できるから助かるわ」
「うううっ、お夜食絶対に持ってきますからね! お嬢様っ」
涙ながらに約束するカイラに、レティシアは満面の笑みを向ける。使用人達が味方で、本当に良かった。
「何時もありがとうね、カイラ」
椅子に座り針を手に取りながら、レティシアは笑みを浮かべた。スフィアはカイラが部屋にいたからか、来なかったようで、それが救いだった。
それからというもの、レティシアは部屋に籠りきった。スフィアから遠ざかるのも半分あったが、何よりドレスを完成させるのが目的だったからだ。補修を始めて五日が経ち、漸く、ドレスの刺しゅうが終わりを迎える。
「良かった……やっと終わった」
針を針刺しに通し、糸の始末をする。ドレスのスカートの裾には全体に薔薇の刺しゅうが施され、新たな装いへと姿を変えた。
少し前に貰ったばかりというのもあり、他に直す所はない。レティシアは深く息を吐き、疲れた眼を労わり目頭を押さえ安堵する。
「良かったです本当にっ」
「カイラの補助があったから出来たのよ」
ありがとう、と言葉をかけると、カイラは力強く首を横に振った。
「お嬢様のお力ですよ!」
「そう言って貰えると頑張った甲斐があったわ」
互いに笑みを浮かべ、微笑みあう。直しの終えたドレスをクローゼットに仕舞い、鍵を閉めた。
信用していない訳ではないが、スフィアが何もして来ないとは限らない。用心に越したことはない筈だ。
「後は何も起きないといいのだけど……」
この五日間、スフィアが何もしてこなかったのが不思議でならない。きっと、毎日私に行っていた嫌がらせが出来ていないからストレスが溜まっていてもおかしくはないのだ。一抹の不安を抱えながら、部屋を出る。
久方ぶりに食事以外で自室から出たが、特に変わったことはなさそうだ。使用人達の顔色を窺っても、何か変化があったとは感じられない。
「――あら、お姉さま」
「スフィア……」
まるで張り込んでいたかのようなタイミングで、スフィアと遭遇してしまう。嫌な予感しかしない。
「お嬢様はお疲れなので、失礼しても宜しいでしょうか」
レティシアを庇うように、カイラがスフィアの前に立つ。スフィアはフン、と鼻を鳴らし、手であしらった。
「私はお姉さまに用があるの……使用人の分際で私の前に立つんじゃないわよ」
「ありがとう、カイラ」
「お嬢様っ」
庇ってくれていたカイラの腕に手を添え、礼を述べるレティシア。これ以上スフィアを刺激すれば、確実にカイラに悪いことが起こる。それだけは嫌だ。カイラの前に立ち、スフィアと対峙する。
「私に用ってなにかしら」
「お姉さまに差し上げた緑のドレス、返してくださらない?」
「!?」
突然の言葉に、目を見開いた。大方、風魔法で室内を覗いていたのだわ……。レティシアはスフィアを刺激しないよう、丁寧に断った。
「悪いのだけど、あのドレスは私のサイズに手直ししてしまったの。スフィアの体型に合わせて直すにはパーティーに間に合わないわ」
「は? 双子なんだからサイズなんて大して変わらないでしょ。いいから返して。元は私のドレスよ」
「あれは私がパーティーに着ていくドレスなの。スフィアにはお母様と買い物に行って選んだドレスがあるでしょう?」
宥めるように話を進めていくが、どうにもあのドレスを返して欲しいらしい。大方、嫌がらせの口実に使われているのだろうが、それでもカイラと共に頑張って手直ししたドレスだ。渡す訳にはいかない。レティシアはスフィアにキッときつく視線を合わせた。
「な、何よ……『不良品』のお姉さまが、私にたてつこうっていうの!?」
「そんなことはしないわ。でもあのドレスだけは渡せない。お願いだから諦めてちょうだい」
普段なら抵抗も反抗もしてこないに……! スフィアは下唇を噛み締め怒りに顔を歪ませた。
「そんなにいうなら要らないわよ! あんな『不良品』のドレス、『不良品』のお姉さまにお似合いだわ!」
「っ」
廊下に、乾いた音が響く。スフィアの言葉についカッとなってしまい、頬を叩いてしまった。私が『不良品』と言われるのは我慢できるが、丹精込めて作られたあの素敵なドレスを『不良品』扱いするのは、製作者への暴言だ。そう思ったら、考えることよりも先に体が動いてしまった。
頬を叩かれたスフィアは、叩かれた方の頬に手を当てる。一瞬呆気に取られたが、すぐさま口角を上げ、深い嫌な笑みを浮かべた。
「きゃああああああ!」
突然叫び、その場に蹲った。しまった、そう思ったが時既に遅く、母がスフィアの声を聞きつけ走ってきた。
「スフィア! 一体どうしたのっ」
駆けつけてみれば、母ユノアの目にはには頬を押さえて蹲るスフィアと目の前に居るレティシアの姿が映るだろう。そうなれば、言わずもがなスフィアを優遇する両親のとる行動は一つだ。
「レティシア、またお前ですか」
「っ」
母ユノアの声と共に、魔力が放出される。風属性特有の緑の光がユノアを包み込む。
「お母さまっ、お姉さまが私を叩いたの! お前ばかりドレスを新調して貰って生意気なんだってっ」
「ちがっ、私はそんなこと言ってない!」
頭を振りながら、無実を訴えるレティシア。だがレティシアの言葉を信じないユノアは、スフィアの肩を抱き締め赤くなった頬に手を添えた。
「可哀想に、こんなに赤くなるくらいの力で叩くなんて……レティシア」
「お母様、話を聞いてください」
「お前の話など聞きたくもありません」
ピシャリと言い切られ、レティシアは言葉を詰まらせる。どうして、私の言葉は聞いてくれないの?
「レティシア」
突然の父の声に、背後を振り返る。振り返った瞬間、頬に強い衝撃が走り気付いた時には床に倒れていた。
「っ……」
倒れてから、父スルグに頬を殴られたのだと理解する。殴られた頬がジンジンと熱を持ち、口内は血の味がした。
「お嬢様っ」
カイラが駆け寄ろうとするのを、クラリックが制する。今ここで動いたら危険だ。クラリックの行動に感謝した。
髪を掴まれ、顔を無理矢理上げさせられる。殴られた痛みからして、父は拳にエンチャント魔法を付与して殴ってきたようだ。未だ痛む頬に、表情が歪む。
「今日まで耐えてきたが、スフィアに手を出したことには堪忍袋の緒が切れるわ。この『不良品』が!」
「っ」
勢いよく髪を引っ張られ、何本か髪が千切れる音がした。痛みに歪む顔で父の顔を見ると、怒りで我を失いかけているように見えた。
「まだそんな顔をするか! お前なぞ、こうしてやるわ!」
「っ」
拳を振りかざされ、ぎゅっと目を閉じて衝撃に備える。だが衝撃も痛みも襲ってこない。恐る恐る、目を開けた。
「旦那様、これ以上の騒ぎは明後日のパーティーに支障がでます」
スルグの手を止めていたのは、クラリックだった。
「放せっ、使用人の癖に私に指図するつもりか!」
「招待状には既にスフィアお嬢様だけでなくレティシアお嬢様の名前も記載してお返事を返しておいでです。それなのにお二方の顔に傷があるのは旦那様としても困るのでは?」
クラリックの言葉に、スルグは唸り歯軋りしながら拳を下ろす。レティシアの髪を掴んでいた手も解かれ、レティシアは床に尻もちをついた。
「クラリック、その『不良品』の手当てでもしておけ」
「はい」
ユノアがスフィアを支えながら起こし、三人はその場を去っていく。ホッとしたレティシアに、カイラが急いで駆け寄ってきた。
「お嬢様っ」
ぐしゃぐしゃになった髪の毛、大きく腫れた頬。主のあまりの酷い姿に、カイラは涙を零した。
「うう……っ、あんまりですよぉ……お嬢様は何も悪いことしてないのにっ」
「カイラ……」
自分は、痛みにも慣れてしまった。涙も堪えられる。そんな自分の代わりに、カイラは何時も泣いたり怒ったりしてくれる。カイラがいてくれたから、自分はここまでやってこれたんだ。
「……ありがとう、カイラ」
「お嬢様っ」
カイラの背に腕を回し、ぎゅっと抱き締める。両親も妹もくれない愛情を、カイラを始めとした使用人達がくれた。私は幸せ者なんだ。レティシアは涙を堪えながら、抱き締める手に力を籠めた。
「お嬢様、カイラ。部屋に戻りましょう。傷の手当てをします」
「そうね、クラリック」
クラリックの言葉に、カイラと共に立ち上がる。すぐ側の自室に入り、ドアを閉めた。
「いたっ……」
クラリックの手が頬に触れる。触れただけで痛むということは、相当に腫れているのだろう。普段ならば鏡を持ってくるカイラが鏡を持ってこないのもそれを裏付ける。クラリックは小さく呪文を詠唱すると、頬に水の塊がスライムの様に張り付いた。暫くはこれで腫れが引くのを待つしかない。
「痛みますが、パーティーまでには腫れは引くかと思います」
「ありがとう」
「後は薬草ティーを飲んで治るのを待ちましょう」
クラリックは、何時も父や母に叩かれたりした時に治療をしてくれている。父の従者でありながら、何かと面倒を看てくれているのだ。
「申し訳ないですお嬢様っ、私が水属性なら少しはお役に立てるのに……っ」
「カイラが謝る必要はないわ。カイラにはカイラの良さがあるもの」
この世界には、完全なる魔法での治療は不可能だ。風属性や水属性は薬草を応用して大々的な治療が出来、地属性ならば効果の高い薬草を育てることは可能である。だが、魔法だけでの治癒は多くの魔法使いが研究をしても成されていないことだ。
カイラの扱える火属性は治療には向いていない。それが歯がゆいらしい。カイラには何時も救われている。そんなに気にしないで欲しい。レティシアはそう思いを込めて微笑んだ。
「っ、薬草ティー、今すぐ作ってきます!!」
いてもたってもいられなかったのか、カイラは勢いよく立ち上ががり室内から出て行った。あの元気に救われる。そう、思えた。
「お嬢様」
「何かしら」
すぐ側で立って待機しているクラリックを見上げる。クラリックは表情を曇らせ、深々と頭を垂れた。
「クラリック!」
「先程の主の無礼、本当に申し訳ありません」
「顔を上げてっ、もしスフィアがこの部屋を覗いていたらあなたが大変な目に遭うわ」
慌てて、レティシアは顔を上げさせる。だが、クラリックの表情は変わらなかった。悔しさを押し殺しているような、そんな表情にも見える。
「ですが、私は目の前でお嬢様が虐げられているのにも関わらず……」
「ううん、最後は止めてくれたでしょ。それで十分よ」
だから、そんな顔をしないで欲しい――。レティシアは大丈夫と伝えるように、微笑んで見せた。
「……ありがとう、ございます」
クラリックは再び頭を垂れ、感謝を述べたのだった。