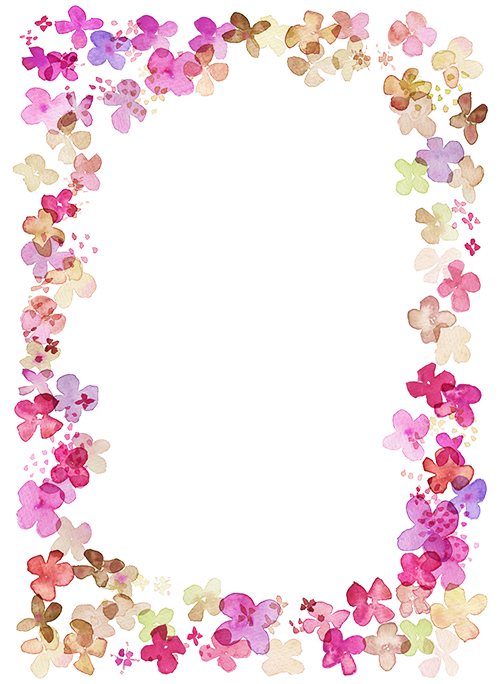あの後、食堂に向かい昼食をとったレティシアは、そこでも驚きが沢山あった。
一つは提供された料理の数々だ。クォーク家も伯爵家だ。それなりに豪勢な食事をとっていたと思っていた。だが、ユグドラス家の昼食はそれ以上の豪勢さと品数だった。
脂ののった大きな魚のムニエル、焼き立てのパン、色とりどりの野菜の煮込まれたスープ。どれをとっても美味だった。
もう一つは、目の前の屋敷の主、セシリアスタの食欲だ。細身の体の何処に入るのだろうかというほどの量を、黙々と平らげていく。丁寧なテーブルマナーに見惚れながら、つい消えていくテーブルの上の食事を見てしまった。
食休みも兼ねて、部屋に持ってきた鞄の中身を整頓していく。アティカとカイラはもう仲良くなったのか、カイラはアティカに此処での作法を聞きながら片付けをしている。
(良かった……これも壊れてないわね)
小さな鞄から取り出した糸紡ぎ。どこも壊れている箇所が無いのを確認すると、机の上にそっと置いた。
「レティシアお嬢様は刺しゅうが趣味なのですか?」
「ふふーん! お嬢様は凄い刺しゅうが上手なのよ! 魔糸から作っちゃうんだからっ」
アティカの声に、カイラは自分のことのように自慢をする。ふと、アティカは糸紡ぎを覗き込んだ。
「……白い魔石?」
「これは小さい頃に生成した魔石なの。その頃から動力源として使ってるわ」
魔道具の糸紡ぎには、魔糸にする為の魔石と動力源となる魔石と最低二つは魔石が必要になる。レティシアの使う糸紡ぎは購入した当時に生成した魔石をずっと使用していた。
「私が生成する魔石はどれも白くなってしまうから、白の魔糸でしか刺しゅうはしたことがないのだけれどね」
「そう、ですか……」
アティカはジッと糸紡ぎを見ながら、クローゼットにドレスを仕舞っていった。
レティシアは最後に机に写真立てを飾り、片づけを終えた。
「坊ちゃん、元気にしてますかね」
「そうね……」
写真に写る少年を見ながら、ライカと共に話す。
「その方は?」
「従兄弟のフレンよ。今は全寮制のアカデミーに通っているから、もう何年も会っていないの」
金髪でアメジストの瞳の少年を指差し、レティシアは答える。幼少期はよくクォーク邸に遊びに来て楽しく過ごしていた。魔法が使えない『不良品』とわかった後も、「スフィアとは相性が悪い」と言ってレティシアと遊んでいた。今は確か、アカデミーの最高学年にまでなっている筈だ。後で落ち着いたら、手紙でも書いて送ろう、そう思った。
「レティシア嬢、そろそろいいか?」
「はい」
ドアの向こうから、セシリアスタが声をかけてくる。写真を置き、レティシアはカイラ、アティカと共に部屋を出た。
王都メイシャルト。王宮のそびえるこの都市は、交易が盛んだ。売られている魔石の数も他の領地とは比べ物にもならないし、何より魔道具の取り扱いが盛んな場所でもある。レティシアは馬車に揺られながら、目を輝かせつつ街を見渡していた。
馬車が目的の場所に到着する。其処はブティックが立ち並ぶ、いわゆる紳士淑女のたまり場だ。
「アティカ、時間になったらここで待て」
「了解しました」
セシリアスタからお金の入った巾着を受け取り、アティカは会釈する。カイラも慌てて会釈して、その場を離れていった。残されたレティシアは、場違いな服装をしているのではないかと不安になった。周りからの視線も、やけに痛い。そんなレティシアに、セシリアスタはそっと肩に触れた。
「私達も行こう」
「は、はい……」
促されるままに、レティシアはセシリアスタと共に歩き出した。
まず立ち寄ったのはすぐ側にあったブティック。ドアを開けると、可愛らしいベルの音が響いた。
「わあ……」
店内の可愛らしい服の数々に、目を奪われる。レティシアお気に入りのシフォンタイプのワンピースや、テール・スカートタイプのワンピース。シュミーズ・ドレスや膝丈のツーピースなど、彩り豊かな服が飾られていた。
「あら若旦那さま、いらっしゃ~い」
店の奥から、逞しい二の腕と胸筋を称えた大柄な男性が出てきた。唇には淡く口紅が塗られ、ライトブラウンのかみはオールバックに纏められている。ライトブルーの瞳はとても美しく、真っすぐこちらを見てきた。
「ジャスミン。彼女の服を誂えて欲しい」
手を差し伸べられ、前に出る。ジャスミンと言われた男性は、じっとレティシアを見つめた。
「この子……綺麗な銀髪ね~! 若旦那さまとお揃い、羨ましいわっ」
くねくねと腰を揺らしながら、レティシアの背後に回る。髪を持ち上げられ、何度か頷く。
「この子、姿勢もいいしスタイルもいいわね……最初から作るとなると、最低でも三日はかかるけど、どうします?」
「頼む。後何着か試着していく。気に入ったのがあれば買ってその場で着ていかせる」
「はいは~い。じゃあお嬢さん、こっちに来て採寸をしちゃいましょう」
「は、はいっ」
初めてのことに、レティシアはたじたじだ。店の奥に入り、服を脱ぐ。ビスチェとドロワーズだけになると、手早く採寸されていく。
「そうそう、若旦那ご婚約の話はどうなったんです? お相手、決まりました?」
「彼女が婚約者だ」
ジャスミンの一言に、店内に居るセシリアスタは淡々と答える。ジャスミンは「まあ!」と言い目を見開いた。
やはり、文不相応だろうか……。そう思ってしまうレティシアに、ジャスミンは目を輝かせ顔を近付けた。
「あの若旦那さまにこんな可愛い子が!? やだわ若旦那さま、こんな可愛い子を捕まえるなんて……エッチね!」
「え、エッチ……?」
セシリアスタがエッチ? 想像も出来ず、レティシアは首を傾げる。セシリアスタはジャスミンの言葉に深く息を吐いた。
「ジャスミン……」
「だってこんな発展途上な女の子をお嫁さんにでしょ? 自分色に染め上げられるんだから、エッチと言ってもおかしくはないわ」
自分色に染め上げられる――。その一言に、頬が次第に赤く染まっていくレティシア。そんなレティシアを見て、ジャスミンは「初心ねえ」と微笑んだ。
採寸が終わり、服を着る。店に戻ると、早速と言わんばかりにジャスミンが服を誂えだした。
「さあて! レディに似合うのはこれとこれと……あとこれもいいかしらね!」
飾られていた服を何着か取り、試着室へと案内される。水色のシフォンワンピース、スカートの裾に刺しゅうの施された紺色のシュミーズ・ドレス、淡いピンクのテール・スカートタイプのワンピースや、黄色のカシュクール・ワンピース、ベルト・カラーの茶色の軍服を模した膝丈のツーピースなど、何着も試着させられた。
「ふむ……全部買おう」
「まいど~♪」
「セシル様!?」
試着したドレス全部となると、相当な額になる。レティシアは慌てて止めようとしたが、それよりも先にセシリアスタに制される。
「君に似合うものばかりだ。幾つあっても損はない」
「ですが……っ」
「私から、君への贈り物として受け取って欲しい」
そう言われれば、断ることが出来ない。レティシアは諦めるしかなかった。
一つは提供された料理の数々だ。クォーク家も伯爵家だ。それなりに豪勢な食事をとっていたと思っていた。だが、ユグドラス家の昼食はそれ以上の豪勢さと品数だった。
脂ののった大きな魚のムニエル、焼き立てのパン、色とりどりの野菜の煮込まれたスープ。どれをとっても美味だった。
もう一つは、目の前の屋敷の主、セシリアスタの食欲だ。細身の体の何処に入るのだろうかというほどの量を、黙々と平らげていく。丁寧なテーブルマナーに見惚れながら、つい消えていくテーブルの上の食事を見てしまった。
食休みも兼ねて、部屋に持ってきた鞄の中身を整頓していく。アティカとカイラはもう仲良くなったのか、カイラはアティカに此処での作法を聞きながら片付けをしている。
(良かった……これも壊れてないわね)
小さな鞄から取り出した糸紡ぎ。どこも壊れている箇所が無いのを確認すると、机の上にそっと置いた。
「レティシアお嬢様は刺しゅうが趣味なのですか?」
「ふふーん! お嬢様は凄い刺しゅうが上手なのよ! 魔糸から作っちゃうんだからっ」
アティカの声に、カイラは自分のことのように自慢をする。ふと、アティカは糸紡ぎを覗き込んだ。
「……白い魔石?」
「これは小さい頃に生成した魔石なの。その頃から動力源として使ってるわ」
魔道具の糸紡ぎには、魔糸にする為の魔石と動力源となる魔石と最低二つは魔石が必要になる。レティシアの使う糸紡ぎは購入した当時に生成した魔石をずっと使用していた。
「私が生成する魔石はどれも白くなってしまうから、白の魔糸でしか刺しゅうはしたことがないのだけれどね」
「そう、ですか……」
アティカはジッと糸紡ぎを見ながら、クローゼットにドレスを仕舞っていった。
レティシアは最後に机に写真立てを飾り、片づけを終えた。
「坊ちゃん、元気にしてますかね」
「そうね……」
写真に写る少年を見ながら、ライカと共に話す。
「その方は?」
「従兄弟のフレンよ。今は全寮制のアカデミーに通っているから、もう何年も会っていないの」
金髪でアメジストの瞳の少年を指差し、レティシアは答える。幼少期はよくクォーク邸に遊びに来て楽しく過ごしていた。魔法が使えない『不良品』とわかった後も、「スフィアとは相性が悪い」と言ってレティシアと遊んでいた。今は確か、アカデミーの最高学年にまでなっている筈だ。後で落ち着いたら、手紙でも書いて送ろう、そう思った。
「レティシア嬢、そろそろいいか?」
「はい」
ドアの向こうから、セシリアスタが声をかけてくる。写真を置き、レティシアはカイラ、アティカと共に部屋を出た。
王都メイシャルト。王宮のそびえるこの都市は、交易が盛んだ。売られている魔石の数も他の領地とは比べ物にもならないし、何より魔道具の取り扱いが盛んな場所でもある。レティシアは馬車に揺られながら、目を輝かせつつ街を見渡していた。
馬車が目的の場所に到着する。其処はブティックが立ち並ぶ、いわゆる紳士淑女のたまり場だ。
「アティカ、時間になったらここで待て」
「了解しました」
セシリアスタからお金の入った巾着を受け取り、アティカは会釈する。カイラも慌てて会釈して、その場を離れていった。残されたレティシアは、場違いな服装をしているのではないかと不安になった。周りからの視線も、やけに痛い。そんなレティシアに、セシリアスタはそっと肩に触れた。
「私達も行こう」
「は、はい……」
促されるままに、レティシアはセシリアスタと共に歩き出した。
まず立ち寄ったのはすぐ側にあったブティック。ドアを開けると、可愛らしいベルの音が響いた。
「わあ……」
店内の可愛らしい服の数々に、目を奪われる。レティシアお気に入りのシフォンタイプのワンピースや、テール・スカートタイプのワンピース。シュミーズ・ドレスや膝丈のツーピースなど、彩り豊かな服が飾られていた。
「あら若旦那さま、いらっしゃ~い」
店の奥から、逞しい二の腕と胸筋を称えた大柄な男性が出てきた。唇には淡く口紅が塗られ、ライトブラウンのかみはオールバックに纏められている。ライトブルーの瞳はとても美しく、真っすぐこちらを見てきた。
「ジャスミン。彼女の服を誂えて欲しい」
手を差し伸べられ、前に出る。ジャスミンと言われた男性は、じっとレティシアを見つめた。
「この子……綺麗な銀髪ね~! 若旦那さまとお揃い、羨ましいわっ」
くねくねと腰を揺らしながら、レティシアの背後に回る。髪を持ち上げられ、何度か頷く。
「この子、姿勢もいいしスタイルもいいわね……最初から作るとなると、最低でも三日はかかるけど、どうします?」
「頼む。後何着か試着していく。気に入ったのがあれば買ってその場で着ていかせる」
「はいは~い。じゃあお嬢さん、こっちに来て採寸をしちゃいましょう」
「は、はいっ」
初めてのことに、レティシアはたじたじだ。店の奥に入り、服を脱ぐ。ビスチェとドロワーズだけになると、手早く採寸されていく。
「そうそう、若旦那ご婚約の話はどうなったんです? お相手、決まりました?」
「彼女が婚約者だ」
ジャスミンの一言に、店内に居るセシリアスタは淡々と答える。ジャスミンは「まあ!」と言い目を見開いた。
やはり、文不相応だろうか……。そう思ってしまうレティシアに、ジャスミンは目を輝かせ顔を近付けた。
「あの若旦那さまにこんな可愛い子が!? やだわ若旦那さま、こんな可愛い子を捕まえるなんて……エッチね!」
「え、エッチ……?」
セシリアスタがエッチ? 想像も出来ず、レティシアは首を傾げる。セシリアスタはジャスミンの言葉に深く息を吐いた。
「ジャスミン……」
「だってこんな発展途上な女の子をお嫁さんにでしょ? 自分色に染め上げられるんだから、エッチと言ってもおかしくはないわ」
自分色に染め上げられる――。その一言に、頬が次第に赤く染まっていくレティシア。そんなレティシアを見て、ジャスミンは「初心ねえ」と微笑んだ。
採寸が終わり、服を着る。店に戻ると、早速と言わんばかりにジャスミンが服を誂えだした。
「さあて! レディに似合うのはこれとこれと……あとこれもいいかしらね!」
飾られていた服を何着か取り、試着室へと案内される。水色のシフォンワンピース、スカートの裾に刺しゅうの施された紺色のシュミーズ・ドレス、淡いピンクのテール・スカートタイプのワンピースや、黄色のカシュクール・ワンピース、ベルト・カラーの茶色の軍服を模した膝丈のツーピースなど、何着も試着させられた。
「ふむ……全部買おう」
「まいど~♪」
「セシル様!?」
試着したドレス全部となると、相当な額になる。レティシアは慌てて止めようとしたが、それよりも先にセシリアスタに制される。
「君に似合うものばかりだ。幾つあっても損はない」
「ですが……っ」
「私から、君への贈り物として受け取って欲しい」
そう言われれば、断ることが出来ない。レティシアは諦めるしかなかった。