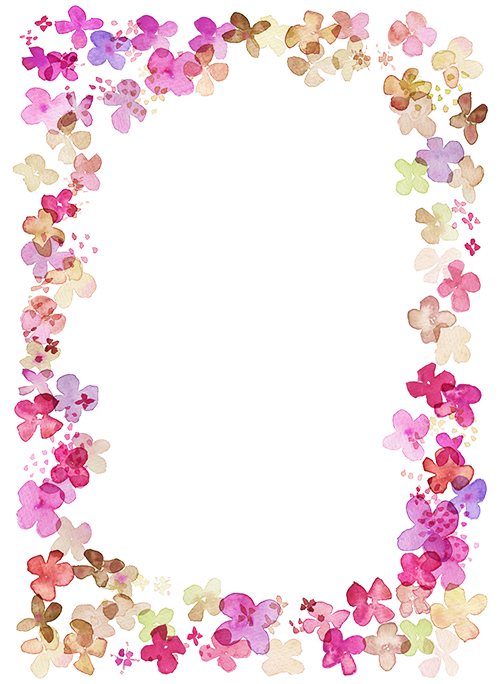クォーク邸が見えなくなり、馬車の中へと戻り姿勢を正すレティシア。そんなレティシアの元に、宙を舞い魔法便が届いた。この魔力からして、母ユノアからだ。手紙の表には特に何も記載されておらず、封を開ける。
手紙は、父スルグからだった。
恩情を与えて今まで家に置いてやった恩を逆に仇で返し、あまつさえ私達に泥を被せるとは……『不良品』でも役に立つともい育てた私達が愚かだった。お前なぞ娘とも思わん。金輪際、我がクォーク領に立ち入ることを禁ずる。二度とその面を見せるな。
書かれていた内容に、レティシアはもう悲しいとも思わなかった。こうなることは婚約書にサインした時点で、わかりきっていたことだ。だが、この手紙を読んで、もう随分前から自分は家族としても見て貰えてなかったのがわかり、胸に穴が開いたような、虚しさだけが残った。
そんなレティシアに、カイラは心配そうに声をかける。
「お嬢様……大丈夫ですか?」
ハッとし、すぐさま手紙を封筒の中に仕舞う。カイラを心配させまいと、レティシアは笑顔を作った。
「大丈夫よ、カイラ」
「でも……」
レティシアの膝に置かれた手紙を見ながら、不安そうに見つめるカイラ。作り笑いもバレてしまっているだろうが、それでも、笑顔を向けた。
「本当に大丈夫。心配してくれてありがとう」
そんな女性二人のやり取りを、セシリアスタは目を閉じ静かに聞いていた。
グリフォンは颯爽と駆け抜け、あっという間にクォーク領の外れまで来てしまう。窓から見える風景も、普段馬車で見ていたものよりも早く過ぎ去っていく。沈黙の続く馬車の中、レティシアは意を決してセシリアスタへと視線を向けた。
「あの……セシリアスタ様」
話しかけると、目を閉じ頬杖をついていたセシリアスタは姿勢を変え足を汲み直す。
「セシルでいい」
「ですが……」
躊躇うレティシアに、セシリアスタは目をゆっくりと開けレティシアを見やった。静かな印象を与えるアイスブルーの瞳は何処か冷たい雰囲気を醸し出している。
「パーティー会場の時と同じ呼び方でいい。それとも、嫌か?」
微かに目尻を下げ、首を傾げるセシリアスタに、レティシアは何も言えなくなった。仕方なく、パーティー会場の時と同様の名でセシリアスタを呼ぶ。
「その……セシル様は何故、私を選んでくださったのですか?」
胸元に手を当てながら、一度言葉を区切った。小さく息を吐き、言葉を続ける。
「パーティーの時にもお話しましたが、私は魔法の使えない『不良品』です。なのに何故……」
「……はあ」
盛大に溜息を吐かれ、アイスブルーの瞳に射抜かれる。レティシアはビクリ、と体が強張った。
「あの時に言った言葉に嘘も偽りもない。冗談を言っても意味がないだろう」
「ですが……っ」
なおも言葉を続けようとするレティシアに、セシリアスタは手を翳し制する。
「魔法が使えないなんて関係ない。俺が、君を気に入った。その容姿も、性格も、その身に宿す魔力も……全てだ。それだけだ」
セシリアスタの言葉に、レティシアは頬が紅潮し、涙が溢れそうになった。そこまで自分を見てくれた人なんて、使用人達くらいしかいなかった。家族は絶対に見てくれなかったレティシアという存在を、気に入ってくれたと、この人は言ってくれたのだ。レティシアは俯き、膝に乗せた拳に力を籠めた。そうでないと、涙が溢れそうになってしまう。
スッと、ハンカチを差し出された。魔草の香が焚かれた、清涼感ある香りのするハンカチ。
「ありがとうございます」
礼を言いながら、レティシアはハンカチを受け取り涙を拭った。視線を上げると、セシリアスタは目を細めレティシアをじっと見つめている。
「君は泣いている顔より、笑顔の方が似合う」
明け透けに物を言うセシリアスタに、レティシアの頬が再び紅潮していく。こうも堂々と言える方だとは思わなかった。レティシアは小さく咳払いし、「ありがとうございます」と笑顔を返した。
手紙は、父スルグからだった。
恩情を与えて今まで家に置いてやった恩を逆に仇で返し、あまつさえ私達に泥を被せるとは……『不良品』でも役に立つともい育てた私達が愚かだった。お前なぞ娘とも思わん。金輪際、我がクォーク領に立ち入ることを禁ずる。二度とその面を見せるな。
書かれていた内容に、レティシアはもう悲しいとも思わなかった。こうなることは婚約書にサインした時点で、わかりきっていたことだ。だが、この手紙を読んで、もう随分前から自分は家族としても見て貰えてなかったのがわかり、胸に穴が開いたような、虚しさだけが残った。
そんなレティシアに、カイラは心配そうに声をかける。
「お嬢様……大丈夫ですか?」
ハッとし、すぐさま手紙を封筒の中に仕舞う。カイラを心配させまいと、レティシアは笑顔を作った。
「大丈夫よ、カイラ」
「でも……」
レティシアの膝に置かれた手紙を見ながら、不安そうに見つめるカイラ。作り笑いもバレてしまっているだろうが、それでも、笑顔を向けた。
「本当に大丈夫。心配してくれてありがとう」
そんな女性二人のやり取りを、セシリアスタは目を閉じ静かに聞いていた。
グリフォンは颯爽と駆け抜け、あっという間にクォーク領の外れまで来てしまう。窓から見える風景も、普段馬車で見ていたものよりも早く過ぎ去っていく。沈黙の続く馬車の中、レティシアは意を決してセシリアスタへと視線を向けた。
「あの……セシリアスタ様」
話しかけると、目を閉じ頬杖をついていたセシリアスタは姿勢を変え足を汲み直す。
「セシルでいい」
「ですが……」
躊躇うレティシアに、セシリアスタは目をゆっくりと開けレティシアを見やった。静かな印象を与えるアイスブルーの瞳は何処か冷たい雰囲気を醸し出している。
「パーティー会場の時と同じ呼び方でいい。それとも、嫌か?」
微かに目尻を下げ、首を傾げるセシリアスタに、レティシアは何も言えなくなった。仕方なく、パーティー会場の時と同様の名でセシリアスタを呼ぶ。
「その……セシル様は何故、私を選んでくださったのですか?」
胸元に手を当てながら、一度言葉を区切った。小さく息を吐き、言葉を続ける。
「パーティーの時にもお話しましたが、私は魔法の使えない『不良品』です。なのに何故……」
「……はあ」
盛大に溜息を吐かれ、アイスブルーの瞳に射抜かれる。レティシアはビクリ、と体が強張った。
「あの時に言った言葉に嘘も偽りもない。冗談を言っても意味がないだろう」
「ですが……っ」
なおも言葉を続けようとするレティシアに、セシリアスタは手を翳し制する。
「魔法が使えないなんて関係ない。俺が、君を気に入った。その容姿も、性格も、その身に宿す魔力も……全てだ。それだけだ」
セシリアスタの言葉に、レティシアは頬が紅潮し、涙が溢れそうになった。そこまで自分を見てくれた人なんて、使用人達くらいしかいなかった。家族は絶対に見てくれなかったレティシアという存在を、気に入ってくれたと、この人は言ってくれたのだ。レティシアは俯き、膝に乗せた拳に力を籠めた。そうでないと、涙が溢れそうになってしまう。
スッと、ハンカチを差し出された。魔草の香が焚かれた、清涼感ある香りのするハンカチ。
「ありがとうございます」
礼を言いながら、レティシアはハンカチを受け取り涙を拭った。視線を上げると、セシリアスタは目を細めレティシアをじっと見つめている。
「君は泣いている顔より、笑顔の方が似合う」
明け透けに物を言うセシリアスタに、レティシアの頬が再び紅潮していく。こうも堂々と言える方だとは思わなかった。レティシアは小さく咳払いし、「ありがとうございます」と笑顔を返した。