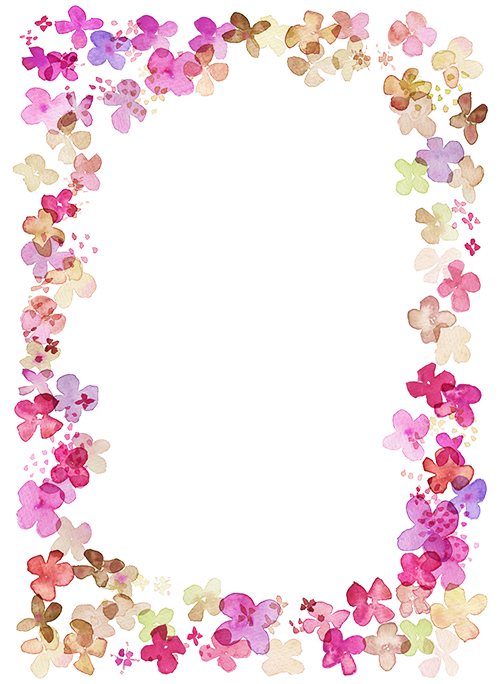「君を迎えに来た。レティシア嬢」
そう言いながら、セシリアスタは微笑んだ。
「迎え? 私を……?」
何が何だかわからない。両手を胸に当て、不安げにセシリアスタへと視線を向ける。セシリアスタは目が合うと、目を細め優し気に微笑んでくれた。その美しさに、頬が紅潮していく。
「お、お待ちください!」
エントランスに、スルグの声が響いた。振り返るセシリアスタは来た時同様、表情が硬くなる。
「なんだ」
「何かの勘違いでは!? スフィアではなく、レティシアだなんてっ」
スルグの発した言葉に、ユノアも頷く。我に返ったスフィアは、くるりと此方へ振り返り笑顔を向けた。
「セシリアスタさまはご冗談がお上手なんですねっ」
スフィアは今のこの状況を受け入れていないらしい。勿論、レティシアもだ。状況がさっぱり飲み込めない。
「冗談? この場で冗談を言っても意味がないだろうが」
セシリアスタの一言に、スフィアの表情が再び固まる。セシリアスタはスルグの方へ視線を向け、言葉を続けた。
「私はクォーク家の娘を嫁に貰うと文を出した筈だが?」
「ええ、ですからスフィアを嫁にと……」
状況の呑み込めていないスルグに、セシリアスタは深く溜息を吐く。そんな仕草でも美しく感じてしまう。
「それで何故、そちらの娘になるんだ……私が嫁にと言ったのは、レティシア嬢の方だ」
「きゃっ」
言いながら、肩を引き寄せられる。力強い、それでいて逞しい手は不快に感じられなかった。胸に当てた両手から、少しだけ力が抜ける。
「ですが公爵、レティシアは既に婚約が決まっています」
ユノアの言葉が重く圧し掛かり、レティシアは目を伏せる。そう、今日中に発たねばならないのだ。仮に今ここで魔導公爵がレティシアを嫁にと言っても、先に約束を交わしてしまっている以上、無下には出来ない。
「――たかが伯爵風情が、公爵の私に指図する気か?」
セシリアスタの表情が冷たいものに変わる。細められた瞳は暗く、物を見るような目つきへと変貌していった。ユノアは喉をひきつらせ、一歩後退る。
「私はレティシア嬢以外はいらん。先方に婚約破棄を伝えろ」
突然のセシリアスタの発言に、スルグ達は顔を青褪めた。困惑の表情でセシリアスタに駆け寄ってくる。
「こ、困ります! 第一、魔導公爵様は我が家の娘を嫁にと言っておりました。ならばスフィアでも十分でしょう」
「何度も言わせるな。私はレティシア嬢以外は嫁に貰うつもりは毛頭ない」
きっぱりと告げられ、スルグもユノアも顔面蒼白だ。午後にはマーキス辺境伯が迎えに来る。その時に嫁ぐ娘が不在でした、なんてことは洒落にならない。どうにかしてスフィアを嫁がせようと考えあぐねいているスルグは、レティシアへと視線を向けた。
「……公爵様、ここはレティシア本人にも窺わなければならないかと」
にっこりと笑みを浮かべながら、スルグはレティシアに決めさせようとさせる。笑ってはいるが、細められた瞳からは激しい怒りが見てとれる。今まで向けられた数々の仕打ちが脳裏に浮かぶ。恐怖で体が強張った。
レティシアは胸に当てた手を握り締めながら、セシリアスタへと視線を向ける。
「セシリアスタ様、お気持ちはとても嬉しいのですが、私は……」
「レティシア嬢」
レティシアの言葉を遮り、セシリアスタが名を呼ぶ。じっと見つめる瞳はレティシアを落ち着かせるように穏やかに、しかし真っ直ぐレティシアを見つめていた。
「約束した筈だ。君を、必ず迎えに行くと」
発せられた言葉に、目を見開く。声も違うし、髪の色も彼とは違う。でも、眼鏡の隙間から垣間見えた瞳と、その約束だけは間違える筈もない。
「セシル、様……?」
名を呼ぶと、セシリアスタは口角を上げた。信じられない。でもあの約束を知っているのは自分と彼だけ。彼は本当に約束を叶えにきてくれたのだ――。そのことが嬉しくて、レティシアは涙が溢れそうになった。
「っ、レティシア!」
スルグの怒声に、体が震える。振り返れば、歯軋りしながら此方を睨み付けるスルグと視線が合った。激しい形相にレティシアの体が強張る。
そんなレティシアを、セシリアスタはぎゅっと肩を抱き締める。セシリアスタを見上げると、セシリアスタはレティシアを安心させるように静かに微笑み返した。
「兎に角、私が選ぶのはレティシア嬢だ。貴殿は私の要求に応じた。ならば約束を果たせ」
振り返り、セシリアスタはスルグ達を睨みつける。スルグもユノアも、決意の固いアイスブルーの瞳にたじろぐ。
「それ以前に、何時までエントランスに居させるつもりだ? クォーク領伯爵は接客態度もなっていないのか」
「し、失礼いたしました……っ」
セシリアスタに急かされ、スルグは客間へと案内する。ユノアは渋々といった表情を浮かべているが、スルグの後に続き客間へ向かう。セシリアスタは小さく溜息を吐くと、肩を抱くレティシアに向き直った。
「さあ、行こう」
「は、はい……」
目を細めながら優しく話しかけられ、レティシアはこくこくと頷く。そのままセシリアスタに肩を抱かれながらエントランスを後にする。
「お前たち」
セシリアスタが連れてきた従者達に振り返り、声をかける。
「此処の使用人と共に、レティシア嬢の荷物を用意しておいてくれ」
「了解いたしました」
命令を受け、従者達は頭を垂れた。すぐさまカイラが従者達の側に駆け寄っていくのが見えた。
視線を感じ、背後を振り返る。
その場に残ったスフィアが、レティシアを嫉妬に駆られた剣幕で睨み付けていた。
そう言いながら、セシリアスタは微笑んだ。
「迎え? 私を……?」
何が何だかわからない。両手を胸に当て、不安げにセシリアスタへと視線を向ける。セシリアスタは目が合うと、目を細め優し気に微笑んでくれた。その美しさに、頬が紅潮していく。
「お、お待ちください!」
エントランスに、スルグの声が響いた。振り返るセシリアスタは来た時同様、表情が硬くなる。
「なんだ」
「何かの勘違いでは!? スフィアではなく、レティシアだなんてっ」
スルグの発した言葉に、ユノアも頷く。我に返ったスフィアは、くるりと此方へ振り返り笑顔を向けた。
「セシリアスタさまはご冗談がお上手なんですねっ」
スフィアは今のこの状況を受け入れていないらしい。勿論、レティシアもだ。状況がさっぱり飲み込めない。
「冗談? この場で冗談を言っても意味がないだろうが」
セシリアスタの一言に、スフィアの表情が再び固まる。セシリアスタはスルグの方へ視線を向け、言葉を続けた。
「私はクォーク家の娘を嫁に貰うと文を出した筈だが?」
「ええ、ですからスフィアを嫁にと……」
状況の呑み込めていないスルグに、セシリアスタは深く溜息を吐く。そんな仕草でも美しく感じてしまう。
「それで何故、そちらの娘になるんだ……私が嫁にと言ったのは、レティシア嬢の方だ」
「きゃっ」
言いながら、肩を引き寄せられる。力強い、それでいて逞しい手は不快に感じられなかった。胸に当てた両手から、少しだけ力が抜ける。
「ですが公爵、レティシアは既に婚約が決まっています」
ユノアの言葉が重く圧し掛かり、レティシアは目を伏せる。そう、今日中に発たねばならないのだ。仮に今ここで魔導公爵がレティシアを嫁にと言っても、先に約束を交わしてしまっている以上、無下には出来ない。
「――たかが伯爵風情が、公爵の私に指図する気か?」
セシリアスタの表情が冷たいものに変わる。細められた瞳は暗く、物を見るような目つきへと変貌していった。ユノアは喉をひきつらせ、一歩後退る。
「私はレティシア嬢以外はいらん。先方に婚約破棄を伝えろ」
突然のセシリアスタの発言に、スルグ達は顔を青褪めた。困惑の表情でセシリアスタに駆け寄ってくる。
「こ、困ります! 第一、魔導公爵様は我が家の娘を嫁にと言っておりました。ならばスフィアでも十分でしょう」
「何度も言わせるな。私はレティシア嬢以外は嫁に貰うつもりは毛頭ない」
きっぱりと告げられ、スルグもユノアも顔面蒼白だ。午後にはマーキス辺境伯が迎えに来る。その時に嫁ぐ娘が不在でした、なんてことは洒落にならない。どうにかしてスフィアを嫁がせようと考えあぐねいているスルグは、レティシアへと視線を向けた。
「……公爵様、ここはレティシア本人にも窺わなければならないかと」
にっこりと笑みを浮かべながら、スルグはレティシアに決めさせようとさせる。笑ってはいるが、細められた瞳からは激しい怒りが見てとれる。今まで向けられた数々の仕打ちが脳裏に浮かぶ。恐怖で体が強張った。
レティシアは胸に当てた手を握り締めながら、セシリアスタへと視線を向ける。
「セシリアスタ様、お気持ちはとても嬉しいのですが、私は……」
「レティシア嬢」
レティシアの言葉を遮り、セシリアスタが名を呼ぶ。じっと見つめる瞳はレティシアを落ち着かせるように穏やかに、しかし真っ直ぐレティシアを見つめていた。
「約束した筈だ。君を、必ず迎えに行くと」
発せられた言葉に、目を見開く。声も違うし、髪の色も彼とは違う。でも、眼鏡の隙間から垣間見えた瞳と、その約束だけは間違える筈もない。
「セシル、様……?」
名を呼ぶと、セシリアスタは口角を上げた。信じられない。でもあの約束を知っているのは自分と彼だけ。彼は本当に約束を叶えにきてくれたのだ――。そのことが嬉しくて、レティシアは涙が溢れそうになった。
「っ、レティシア!」
スルグの怒声に、体が震える。振り返れば、歯軋りしながら此方を睨み付けるスルグと視線が合った。激しい形相にレティシアの体が強張る。
そんなレティシアを、セシリアスタはぎゅっと肩を抱き締める。セシリアスタを見上げると、セシリアスタはレティシアを安心させるように静かに微笑み返した。
「兎に角、私が選ぶのはレティシア嬢だ。貴殿は私の要求に応じた。ならば約束を果たせ」
振り返り、セシリアスタはスルグ達を睨みつける。スルグもユノアも、決意の固いアイスブルーの瞳にたじろぐ。
「それ以前に、何時までエントランスに居させるつもりだ? クォーク領伯爵は接客態度もなっていないのか」
「し、失礼いたしました……っ」
セシリアスタに急かされ、スルグは客間へと案内する。ユノアは渋々といった表情を浮かべているが、スルグの後に続き客間へ向かう。セシリアスタは小さく溜息を吐くと、肩を抱くレティシアに向き直った。
「さあ、行こう」
「は、はい……」
目を細めながら優しく話しかけられ、レティシアはこくこくと頷く。そのままセシリアスタに肩を抱かれながらエントランスを後にする。
「お前たち」
セシリアスタが連れてきた従者達に振り返り、声をかける。
「此処の使用人と共に、レティシア嬢の荷物を用意しておいてくれ」
「了解いたしました」
命令を受け、従者達は頭を垂れた。すぐさまカイラが従者達の側に駆け寄っていくのが見えた。
視線を感じ、背後を振り返る。
その場に残ったスフィアが、レティシアを嫉妬に駆られた剣幕で睨み付けていた。