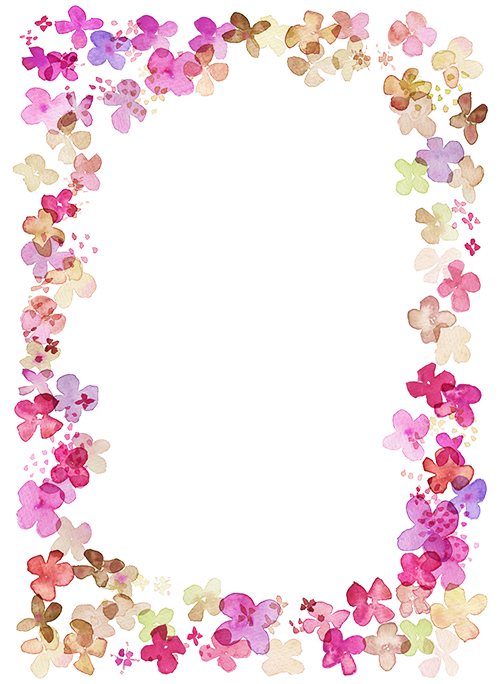この世界では、人の価値は魔力で決まる。――そんな風に言われる程、魔力と魔法が重要な世界だ。
そんな世界の、魔法の力で栄えた国家グリスタニアには多くの貴族が存在している。貴族は元から魔力も魔法にも長け、国家の安定や魔道研究など様々な分野で活躍していく者たちが殆どだ。
クォーク伯爵家の長女レティシアは、そんな魔道に長けた国家で「不良品」として有名な少女だった。
「ちょっと! お姉さま邪魔よ!」
通りがかっただけで、肩をぶつけてくる妹のスフィア。よろめき床に倒れるレティシアに、肩まで長さのある金のウェーブがかかった髪をたなびかせ、フンと鼻を鳴らして文句を言う。
「勝手に倒れないでくれない? そんなか弱く見せたって、誰も「不良品」のお姉さまには関心なんて向けないんだから」
笑みを浮かべながら、スフィアはレティシアに向かって不良品と強調する。レティシアはゆっくりと立ち上がると、腰まである銀のストレートの髪を軽く梳き、静かに頭を垂れた。
「……ごめんなさい、スフィア」
「謝るくらいなら、さっさと部屋に引き籠って。お姉さまを見るだけで気分が悪くなるわ。私はこれからお母さまとブティックに行くの。さっさと私の前から消えて」
去り際に吐かれる言葉に、レティシアは胸が痛んだ。だが、反論なんて出来やしない。レティシアは静かに自室へと歩を進めた。
「はぁ……」
自室に戻るなり、レティシアはベッドに突っ伏す。部屋の中で掃除をしていたレティシア唯一の侍女カイラがオレンジのポニーテールを揺らしながら駆け寄ってくる。
「お嬢様、大丈夫ですか!?」
「カイラ……」
青い目を細めながら心配そうな表情を向けて顔を覗き込んでくるカイラに、大丈夫と笑みだけを返す。だが、幼い頃からレティシアの侍女を務めていたカイラには誤魔化しなんて通じる訳がない。
「またスフィアお嬢様ですね……今度こそ、あの無駄に揃ったウェーブ髪を燃やしてやろうかしら」
「カ、カイラ落ち着いてっ。私がぶつかってしまっただけなの」
「そんなの、あのちんくしゃの方からに決まってます! お嬢様が何かする筈ないです!」
カイラの気迫に負けそうになるが、今ここでカイラを放っておいたら大変なことになる。それだけは避けなければ。レティシアはカイラの手を握り、微笑んだ。
「本当に大したことではないわ。それに、カイラが居なくなるのは私が辛いわ」
「お、お嬢様~っ」
ぎゅっと抱き締められ、レティシアはホッと息を吐いた。このままカイラが何かすれば、必ず父の元に報告される。そうなったら、カイラは解雇されてしまう。それだけは避けたかったが、何とかなったようで良かった。
レティシアは生まれながらにして魔力の量は成人と同等の量を保有しており、何より国内でも珍しい銀髪だった。将来は王族の仲間入りも出来るのではないかと噂されていた程である。実際、王族からも婚約の話も出されたほどだった。だが、三歳から始める魔法の練習を重ねていくうちに、ある問題が発覚したのだ。
レティシアには、魔法が使えなかったのだ。大量のオドをその身に宿しながら、どの属性魔法も使えなかったのである。
その事に嘆いたのは、王族との婚約も視野に入れていた父と、自慢気にサロンで王族との婚姻も夢ではないと言っていた母だ。魔法が使えないとわかった途端、両親の態度が急変した。同時に生まれた双子の妹、スフィアばかりを可愛がるようになったのだ。スフィアもレティシアには劣るが、魔力の量は高かった。何よりレティシアと違い、2属性の魔法を使いこなせた。
それからというもの、同じ屋敷に住んでいながら、レティシアとスフィアの扱いに差が生じだした。使用人もレティシアには魔法訓練前から付き従ってくれていたカイラのみ。服もスフィアのお下がりのみ。食事はまともに与えてくれるが、会話はスフィアとのみでレティシアは無いもの扱いだった。
そんな生活が、十三年も続いた。幸いにしてカイラ以外の使用人もこっそりとだが優しくしてくれるし、侍女のカイラは従者たちの中でも指折りの火属性使い。妹も、属性相性の悪いカイラの前では酷い仕打ちはして来なかった。それだけが救いだった。
(でも、もうそうは言ってられないのよね……)
あと少しで、成人を迎える。そうなれば、邪魔者のレティシアは家の都合のいい所へ嫁がされるだろう。そうなってしまえば、カイラともお別れになってしまう。『不良品』と名高い自分を、受け入れてくれる所なんてそうそうある筈もない。社交界にだって、妹のおまけとして何度か行ったきりで、顔見知りもいない。溜息だけが出てくる。
夕餉の時間。何時も通りのスフィアと両親の会話を聞きながら無言で食事を進めていくレティシア。だが、今日はいつもと父の様子が違っていた。
「レティシア、スフィア。お前たちには来週、あるパーティーに出席してもらう」
「え?」
私も? そんな疑問を、スフィアが聞き逃すはずもなく椅子から立ち上がり、父スルグに詰め寄る。
「お父さま、私だけなら兎も角なんでお姉さまも一緒なの!?」
「落ち着きなさい、スフィア。はしたないですよ」
ついカッとなったスフィアを、母ユノアが諫める。スフィアはレティシアを睨み付けながら、椅子に座り直す。
「今回、やっとあの魔導公爵が婚約者を決める為のパーティーを開くことにしたらしい」
「えっ! 魔導公爵さまが!」
スフィアの喜びの声に、両親はうんうんと頷いた。
「王宮からの再三の要請に、漸く答えたらしい。このパーティー、失敗は許されん」
「その通りですわ。私達の可愛いスフィアが嫁ぐに相応しいお相手。絶対にスフィアが選ばれますわ」
両親の言葉に、合点がいったレティシア。要は私は、スフィアを目立たさせる為のお飾りらしい。
「その為にはレティシア。お前にも行って貰うからな」
父の威圧的な言葉に、拒否権は無いと悟る。何処まで行っても、私は妹の引き立て役になるしかないらしい。
「安心なさい。スフィアの嫁ぎ先が見つかったら、お前にも縁談を持ってきてやる」
「良かったですね、お姉さまっ」
にっこりと笑うスフィアだが、目は笑っていない。父も母も、家に都合のいい相手を適当に選ぶのだろうと思えた。
「……ありがとうございます。お父様、お母様」
それでも、家の為になるならばそれでいい。そう思いながら、笑顔を向けた。
「ふっざけてんですか!? あのくそ爺!」
「カ、カイラ落ち着いて……っ」
自室に戻ると、ご立腹のカイラが紅茶を用意してくれていた。今日はシェフからこっそり作って貰ったクッキーとセットだ。食事の際に出された会話の所為で美味しく感じる事が出来なかった分、堪能しなければ。
「絶対にお嬢様を家の為に利用する気満々じゃないですか!」
クッキーを頬張りながら、カイラは憤慨する。二人だけのティータイムはカイラにも参加して貰っている。何時に増してカイラの機嫌は悪いが、自分の為に怒ってくれるカイラが何より嬉しかった。
「いいのよ、私は『不良品』なのだから。嫁ぎ先を見つけてくれるだけでも嬉しいわ」
「そんなの! 周りが勝手に言っているだけで、お嬢様は決してそんなものじゃありませんっ」
「カイラ……」
子どもの頃から、カイラは姉のような存在だった。小さい頃から住み込みでこの屋敷で働き、レティシアの侍女となってから、ずっとずっと、カイラはレティシアを大切にしてくれた。涙が溢れそうになる。
「お嬢様っ」
「ごめんなさい……なんでもないの、本当よ」
涙を目に溜め込みながら、カイラにほほ笑む。涙を拭い、気を取り直してカイラの淹れてくれた紅茶を一口飲んだ。
「レティシア、入りますよ」
突然の声に、カイラは急ぎ紅茶のカップとクッキーの乗った皿をベッド脇のサイドチェストに隠した。何時もながらの手際の良さに感服する。
「どうぞ、お母様」
レティシアの言葉がかかると同時に、ユノアがレティシアの自室に入ってくる。辺りを見渡し、わざとらしく溜息を吐いた。
「お前の部屋は本当に何もないですね……お前そっくりで、何の変哲もないわ」
扇子で口元を隠しながら、やれやれと再び溜息を吐く。そんなユノアにカイラは笑みを向てはいるが青筋が立っていた。慌てて、レティシアは言葉をかける。
「お母様、何か御用があってきたのでは?」
「そうだったわ。お前のドレスを新調しますから、今すぐ出かけますよ」
「え?」
その言葉に、耳を疑った。何時もはスフィアのお下がりのドレスしか渡されなかったレティシアが、まさかドレスを買って貰える日が来るとは思わなかった。
「何をしていますか。玄関で待ちます。さっさと出かける準備をしなさい」
「は、はい……っ」
慌てて、カイラと共に身支度をし出す。ユノアは伝言を伝え終えると、すぐさま部屋から出て行ってしまった。
「どうゆう風の吹き回しでしょうかね……」
訳がわからないと、カイラは首を傾げながらクローゼットからシフォンタイプのワンピースを取り出す。レティシアからしても不思議でならない。あの母が自分にドレスを新調してやろうと考えるとは。
「兎に角、急ぎましょう」
「はい」
髪を結い、化粧を直し急いで玄関に向かう。玄関には流行りのドレスを身に纏ったスフィアもいた。
「なんでお姉さまが居るのよ」
「私はお母様に言われて此処に来たの」
「はあ!? なにふざけたこと言ってるのよ。お母さまがあんたみたいな『不良品』なんかを買い物に連れて行くものですか!」
不良品と何時ものように強調され、胸が痛む。だが、確かに母はドレスの新調をすると言ったのだ。
「スフィア、貴女が私を嫌いなのは知ってる。でも私はお母様に言われて此処に来たの。それは事実よ」
「ふざけないで! あんたなんて、あたしのお下がりで十分でしょうが!」
「スフィア……」
何を言っても通じないスフィアをどう説得すればいいのか……。周りの従者はレティシアを慕ってくれているのもあり、皆の視線がスフィアに向かっている。背後のカイラに至っては、怒りで魔力が溢れ出しているのが感じられる。このままでは本当に困ったことになる。どうすれば……。
「何をしているの」
ハッと声の方を振り向けば、母ユノアの姿があった。
「お、お母様……」
「お母さまっ」
ユノアの姿を見た瞬間、スフィアはユノアに抱き着く。目には涙を溜め、レティシアを睨んだ。
「酷いのお母さまっ、お姉さまが私に買い物に行くなっていうのよっ」
「えっ」
突然の言葉に、レティシアは言葉が紡げない。それを良いことに、スフィアは言葉を続ける。
「あんたなんか古いドレスでいいでしょって! 私には古臭いドレスがお似合いだなんて言うのっ」
「そんな、私は何も……っ」
「レティシア」
ユノアの冷たい声に、レティシアの体が強張る。魔力をその体に纏ったユノアに睨み付けられ、蛇に睨まれた蛙のような心地になった。
「お前がそんなことをいうとは思いませんでした。お前のドレスの新調は無しにします」
突然の言葉に、ショックが隠せない。レティシアは無実を伝えようと、言葉をかけようとする。
「そんな、お母様っ」
「お黙りなさい」
「っ」
だが、ユノアは聞く気はないようだった。ユノアの腕に縋り付いたスフィアはユノアに見えないように満面の笑みをレティシアへ向けている。悔しくて、見えないように拳をギュッと握りしめた。
「レティシアは家に残りなさい。スフィア、行きますよ」
「はあい♪ お母さまっ」
先に行くユノアに付いていくスフィア。振り返り、べえ、と舌を出し淑女に有るまじき行為をしてきた。しかし、レティシアが何かすれば、再び母に泣きつくのは目に見えている。レティシアはグッと堪えた。
正面玄関の扉が閉まり、近くに居た使用人たちが駆け寄ってくる。
「お嬢様っ」
「大丈夫ですか、お嬢様」
「皆……ありがとう、私は大丈夫よ」
幼い頃からの従者は、皆こうして優しく接してくれる。それだけが救いだった。
「奥様もあんまりですっ、スフィアお嬢様の言葉ばかり聞いてレティシアお嬢様のいうことなんて聞いても下さらないなんて」
「いいの。私には分不相応だっただけの話よ」
「ですがお嬢様っ」
普段ならば引き下がってくれる従者も、今回ばかりは中々静まってくれない。その気持ちだけで、本当に救われているのに。
「もうこの話はおしまいよ。お父様に聞かれてたら、あなた達が不幸になってしまうわ」
「っ……、申し訳ありません」
「皆、本当にありがとう。私は部屋に戻るから、皆も仕事に戻って」
レティシアの言葉を皮切りに、皆が仕事に戻っていく。ホッとしたのも束の間、悲しさが募ってきた。
(部屋に戻りましょ……)
悲しくない、悲しくない――。そう言い聞かせながら、自室へと戻っていった。
そんな世界の、魔法の力で栄えた国家グリスタニアには多くの貴族が存在している。貴族は元から魔力も魔法にも長け、国家の安定や魔道研究など様々な分野で活躍していく者たちが殆どだ。
クォーク伯爵家の長女レティシアは、そんな魔道に長けた国家で「不良品」として有名な少女だった。
「ちょっと! お姉さま邪魔よ!」
通りがかっただけで、肩をぶつけてくる妹のスフィア。よろめき床に倒れるレティシアに、肩まで長さのある金のウェーブがかかった髪をたなびかせ、フンと鼻を鳴らして文句を言う。
「勝手に倒れないでくれない? そんなか弱く見せたって、誰も「不良品」のお姉さまには関心なんて向けないんだから」
笑みを浮かべながら、スフィアはレティシアに向かって不良品と強調する。レティシアはゆっくりと立ち上がると、腰まである銀のストレートの髪を軽く梳き、静かに頭を垂れた。
「……ごめんなさい、スフィア」
「謝るくらいなら、さっさと部屋に引き籠って。お姉さまを見るだけで気分が悪くなるわ。私はこれからお母さまとブティックに行くの。さっさと私の前から消えて」
去り際に吐かれる言葉に、レティシアは胸が痛んだ。だが、反論なんて出来やしない。レティシアは静かに自室へと歩を進めた。
「はぁ……」
自室に戻るなり、レティシアはベッドに突っ伏す。部屋の中で掃除をしていたレティシア唯一の侍女カイラがオレンジのポニーテールを揺らしながら駆け寄ってくる。
「お嬢様、大丈夫ですか!?」
「カイラ……」
青い目を細めながら心配そうな表情を向けて顔を覗き込んでくるカイラに、大丈夫と笑みだけを返す。だが、幼い頃からレティシアの侍女を務めていたカイラには誤魔化しなんて通じる訳がない。
「またスフィアお嬢様ですね……今度こそ、あの無駄に揃ったウェーブ髪を燃やしてやろうかしら」
「カ、カイラ落ち着いてっ。私がぶつかってしまっただけなの」
「そんなの、あのちんくしゃの方からに決まってます! お嬢様が何かする筈ないです!」
カイラの気迫に負けそうになるが、今ここでカイラを放っておいたら大変なことになる。それだけは避けなければ。レティシアはカイラの手を握り、微笑んだ。
「本当に大したことではないわ。それに、カイラが居なくなるのは私が辛いわ」
「お、お嬢様~っ」
ぎゅっと抱き締められ、レティシアはホッと息を吐いた。このままカイラが何かすれば、必ず父の元に報告される。そうなったら、カイラは解雇されてしまう。それだけは避けたかったが、何とかなったようで良かった。
レティシアは生まれながらにして魔力の量は成人と同等の量を保有しており、何より国内でも珍しい銀髪だった。将来は王族の仲間入りも出来るのではないかと噂されていた程である。実際、王族からも婚約の話も出されたほどだった。だが、三歳から始める魔法の練習を重ねていくうちに、ある問題が発覚したのだ。
レティシアには、魔法が使えなかったのだ。大量のオドをその身に宿しながら、どの属性魔法も使えなかったのである。
その事に嘆いたのは、王族との婚約も視野に入れていた父と、自慢気にサロンで王族との婚姻も夢ではないと言っていた母だ。魔法が使えないとわかった途端、両親の態度が急変した。同時に生まれた双子の妹、スフィアばかりを可愛がるようになったのだ。スフィアもレティシアには劣るが、魔力の量は高かった。何よりレティシアと違い、2属性の魔法を使いこなせた。
それからというもの、同じ屋敷に住んでいながら、レティシアとスフィアの扱いに差が生じだした。使用人もレティシアには魔法訓練前から付き従ってくれていたカイラのみ。服もスフィアのお下がりのみ。食事はまともに与えてくれるが、会話はスフィアとのみでレティシアは無いもの扱いだった。
そんな生活が、十三年も続いた。幸いにしてカイラ以外の使用人もこっそりとだが優しくしてくれるし、侍女のカイラは従者たちの中でも指折りの火属性使い。妹も、属性相性の悪いカイラの前では酷い仕打ちはして来なかった。それだけが救いだった。
(でも、もうそうは言ってられないのよね……)
あと少しで、成人を迎える。そうなれば、邪魔者のレティシアは家の都合のいい所へ嫁がされるだろう。そうなってしまえば、カイラともお別れになってしまう。『不良品』と名高い自分を、受け入れてくれる所なんてそうそうある筈もない。社交界にだって、妹のおまけとして何度か行ったきりで、顔見知りもいない。溜息だけが出てくる。
夕餉の時間。何時も通りのスフィアと両親の会話を聞きながら無言で食事を進めていくレティシア。だが、今日はいつもと父の様子が違っていた。
「レティシア、スフィア。お前たちには来週、あるパーティーに出席してもらう」
「え?」
私も? そんな疑問を、スフィアが聞き逃すはずもなく椅子から立ち上がり、父スルグに詰め寄る。
「お父さま、私だけなら兎も角なんでお姉さまも一緒なの!?」
「落ち着きなさい、スフィア。はしたないですよ」
ついカッとなったスフィアを、母ユノアが諫める。スフィアはレティシアを睨み付けながら、椅子に座り直す。
「今回、やっとあの魔導公爵が婚約者を決める為のパーティーを開くことにしたらしい」
「えっ! 魔導公爵さまが!」
スフィアの喜びの声に、両親はうんうんと頷いた。
「王宮からの再三の要請に、漸く答えたらしい。このパーティー、失敗は許されん」
「その通りですわ。私達の可愛いスフィアが嫁ぐに相応しいお相手。絶対にスフィアが選ばれますわ」
両親の言葉に、合点がいったレティシア。要は私は、スフィアを目立たさせる為のお飾りらしい。
「その為にはレティシア。お前にも行って貰うからな」
父の威圧的な言葉に、拒否権は無いと悟る。何処まで行っても、私は妹の引き立て役になるしかないらしい。
「安心なさい。スフィアの嫁ぎ先が見つかったら、お前にも縁談を持ってきてやる」
「良かったですね、お姉さまっ」
にっこりと笑うスフィアだが、目は笑っていない。父も母も、家に都合のいい相手を適当に選ぶのだろうと思えた。
「……ありがとうございます。お父様、お母様」
それでも、家の為になるならばそれでいい。そう思いながら、笑顔を向けた。
「ふっざけてんですか!? あのくそ爺!」
「カ、カイラ落ち着いて……っ」
自室に戻ると、ご立腹のカイラが紅茶を用意してくれていた。今日はシェフからこっそり作って貰ったクッキーとセットだ。食事の際に出された会話の所為で美味しく感じる事が出来なかった分、堪能しなければ。
「絶対にお嬢様を家の為に利用する気満々じゃないですか!」
クッキーを頬張りながら、カイラは憤慨する。二人だけのティータイムはカイラにも参加して貰っている。何時に増してカイラの機嫌は悪いが、自分の為に怒ってくれるカイラが何より嬉しかった。
「いいのよ、私は『不良品』なのだから。嫁ぎ先を見つけてくれるだけでも嬉しいわ」
「そんなの! 周りが勝手に言っているだけで、お嬢様は決してそんなものじゃありませんっ」
「カイラ……」
子どもの頃から、カイラは姉のような存在だった。小さい頃から住み込みでこの屋敷で働き、レティシアの侍女となってから、ずっとずっと、カイラはレティシアを大切にしてくれた。涙が溢れそうになる。
「お嬢様っ」
「ごめんなさい……なんでもないの、本当よ」
涙を目に溜め込みながら、カイラにほほ笑む。涙を拭い、気を取り直してカイラの淹れてくれた紅茶を一口飲んだ。
「レティシア、入りますよ」
突然の声に、カイラは急ぎ紅茶のカップとクッキーの乗った皿をベッド脇のサイドチェストに隠した。何時もながらの手際の良さに感服する。
「どうぞ、お母様」
レティシアの言葉がかかると同時に、ユノアがレティシアの自室に入ってくる。辺りを見渡し、わざとらしく溜息を吐いた。
「お前の部屋は本当に何もないですね……お前そっくりで、何の変哲もないわ」
扇子で口元を隠しながら、やれやれと再び溜息を吐く。そんなユノアにカイラは笑みを向てはいるが青筋が立っていた。慌てて、レティシアは言葉をかける。
「お母様、何か御用があってきたのでは?」
「そうだったわ。お前のドレスを新調しますから、今すぐ出かけますよ」
「え?」
その言葉に、耳を疑った。何時もはスフィアのお下がりのドレスしか渡されなかったレティシアが、まさかドレスを買って貰える日が来るとは思わなかった。
「何をしていますか。玄関で待ちます。さっさと出かける準備をしなさい」
「は、はい……っ」
慌てて、カイラと共に身支度をし出す。ユノアは伝言を伝え終えると、すぐさま部屋から出て行ってしまった。
「どうゆう風の吹き回しでしょうかね……」
訳がわからないと、カイラは首を傾げながらクローゼットからシフォンタイプのワンピースを取り出す。レティシアからしても不思議でならない。あの母が自分にドレスを新調してやろうと考えるとは。
「兎に角、急ぎましょう」
「はい」
髪を結い、化粧を直し急いで玄関に向かう。玄関には流行りのドレスを身に纏ったスフィアもいた。
「なんでお姉さまが居るのよ」
「私はお母様に言われて此処に来たの」
「はあ!? なにふざけたこと言ってるのよ。お母さまがあんたみたいな『不良品』なんかを買い物に連れて行くものですか!」
不良品と何時ものように強調され、胸が痛む。だが、確かに母はドレスの新調をすると言ったのだ。
「スフィア、貴女が私を嫌いなのは知ってる。でも私はお母様に言われて此処に来たの。それは事実よ」
「ふざけないで! あんたなんて、あたしのお下がりで十分でしょうが!」
「スフィア……」
何を言っても通じないスフィアをどう説得すればいいのか……。周りの従者はレティシアを慕ってくれているのもあり、皆の視線がスフィアに向かっている。背後のカイラに至っては、怒りで魔力が溢れ出しているのが感じられる。このままでは本当に困ったことになる。どうすれば……。
「何をしているの」
ハッと声の方を振り向けば、母ユノアの姿があった。
「お、お母様……」
「お母さまっ」
ユノアの姿を見た瞬間、スフィアはユノアに抱き着く。目には涙を溜め、レティシアを睨んだ。
「酷いのお母さまっ、お姉さまが私に買い物に行くなっていうのよっ」
「えっ」
突然の言葉に、レティシアは言葉が紡げない。それを良いことに、スフィアは言葉を続ける。
「あんたなんか古いドレスでいいでしょって! 私には古臭いドレスがお似合いだなんて言うのっ」
「そんな、私は何も……っ」
「レティシア」
ユノアの冷たい声に、レティシアの体が強張る。魔力をその体に纏ったユノアに睨み付けられ、蛇に睨まれた蛙のような心地になった。
「お前がそんなことをいうとは思いませんでした。お前のドレスの新調は無しにします」
突然の言葉に、ショックが隠せない。レティシアは無実を伝えようと、言葉をかけようとする。
「そんな、お母様っ」
「お黙りなさい」
「っ」
だが、ユノアは聞く気はないようだった。ユノアの腕に縋り付いたスフィアはユノアに見えないように満面の笑みをレティシアへ向けている。悔しくて、見えないように拳をギュッと握りしめた。
「レティシアは家に残りなさい。スフィア、行きますよ」
「はあい♪ お母さまっ」
先に行くユノアに付いていくスフィア。振り返り、べえ、と舌を出し淑女に有るまじき行為をしてきた。しかし、レティシアが何かすれば、再び母に泣きつくのは目に見えている。レティシアはグッと堪えた。
正面玄関の扉が閉まり、近くに居た使用人たちが駆け寄ってくる。
「お嬢様っ」
「大丈夫ですか、お嬢様」
「皆……ありがとう、私は大丈夫よ」
幼い頃からの従者は、皆こうして優しく接してくれる。それだけが救いだった。
「奥様もあんまりですっ、スフィアお嬢様の言葉ばかり聞いてレティシアお嬢様のいうことなんて聞いても下さらないなんて」
「いいの。私には分不相応だっただけの話よ」
「ですがお嬢様っ」
普段ならば引き下がってくれる従者も、今回ばかりは中々静まってくれない。その気持ちだけで、本当に救われているのに。
「もうこの話はおしまいよ。お父様に聞かれてたら、あなた達が不幸になってしまうわ」
「っ……、申し訳ありません」
「皆、本当にありがとう。私は部屋に戻るから、皆も仕事に戻って」
レティシアの言葉を皮切りに、皆が仕事に戻っていく。ホッとしたのも束の間、悲しさが募ってきた。
(部屋に戻りましょ……)
悲しくない、悲しくない――。そう言い聞かせながら、自室へと戻っていった。