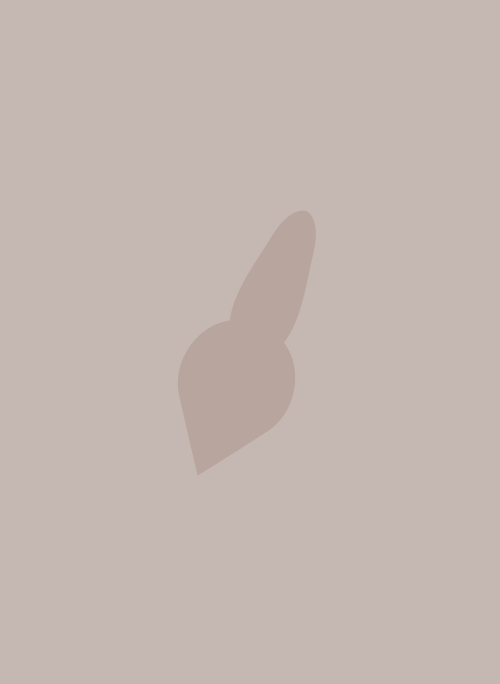クリスティーはさらに考えました。 (このままでは俺までが化け物にされてしまう。 どうしたらいいのだ?」
「スコラディウス殿 迷うことは無いのです。 あなたと私は遥かなる昔からこうして縁を結んできたのですから。」 「とはいっても、、、。」
「心配には及びません。 この船ももうすぐポラニシアの港に着きます。 そうすればあなた様も分かって下さるでしょう。」 「ポラニシア?」
「そう。 カサブラーナ最後の港です。」 「最後の港?」
クリスティーは何が何だか分からなくなってきました。 こうなってはホワイティアに従うより有りません。
料理を二人で拵えた彼はホワイティアを向かい側に座らせて食事を摂りました。 何とも言えぬ懐かしい味の食事です。
「これはいったい、、、?」 「あなた様もこうしてカサブラーナの食事を召し上がっていたのですよ。 それが証拠にザイミールでは食べないカサブランカの花料理までお召し上がりになられたんですね?」
「そうだったのか。 この俺もカサブラーナの、、、。」 「そうです。 少しお判りいただけたようですね。」
船はやがて港らしい入り江に入っていきました。 辺りには草原が鬱蒼と茂っているだけの、、、。
「ここが港であるか?」 「そうです。 古ぼけているように見えますが、カサブラーナではかなり新しい港なのです。」
船は岸壁に接岸しました。 「降りましょう。」
梯子が下ろされ、ホワイティアとクリスティーは岸壁へ恐る恐る降りました。 そこには誰も居ません。
「こんな所でどうやって、、、。」 疑いを深めるクリスティーの口を塞いでホワイティアは口笛を吹きました。
すると、、、。
二人の目の前に宮殿が現れました。
そして何処からともなく煌びやかな衣装をまとった男たちが駆け寄ってきたではありませんか。 「何だ、こいつらは?」
「スコラディウス殿 この人たちは私たちの臣下です。 ここで私たちは住まいを作り暮らしていくのですよ。」 「しかしだなあ、、、。」
「ご納得いただけませんか?」 「いや、、、というかだな、、、、。」
クリスティーは何もかもが出来過ぎていると思ったのです。 「国へ帰ろう。」
「何をおっしゃいます? ここがあなた様と私の国ではないですか。」 「しかし、、、。」
クリスティーが戸惑っているとホワイティアは再び口笛を吹きました。 「ご用でございますか?」
「蜂蜜の壺を持ってきてくださいな。」 「畏まりました。」
髪をきれいに整えた女が花弁がたくさん付いた甘い匂いがする壺を抱えてまいりました。 「ホワイティア殿 お持ちいたしました。」
ホワイティアは蜂蜜の匂いを確かめるとテーブルに置いてあるティーカップに紅茶を注いで蜂蜜を垂らしました。 「喉も乾いたでしょう? お飲みになってくださいな。」
クリスティーは疑いたい気持ちを抑えながらそのティーカップを手に取りました。 何とも懐かしい匂いが漂ってきます。
「これは何と言う懐かしい紅茶だ。 私はかつてこのような紅茶を飲んでいたのか?」 いつの間にか彼もカサブラーナの人間になっていたのです。
というべきか、それとも?
その頃、ザイミールではクリスティーが居なくなったことさえ誰も気付かぬほどに平和過ぎる一日を送っておりました。
あの馬もいつもと変わらず皇帝を乗せては庭を全力で走り、草を食んでは小屋で死んだように眠っております。 警護の兵士たちもいつものように門を見ながらボーっとしているようです。
そしていつの間にか3か月が過ぎ去ってしまいました。
「そういえば馬小屋のあの男はどうしたね?」 「さあ、、、。 今では姿も見掛けませぬ。」
「そうか。 どっかへ行ってしまいおったか。 それでは代わりの者をやろうではないか。」 呑気な皇帝はそう言うとエリカシオンという男を馬小屋にやりました。
馬小屋にはあの男が持っていた弓矢などがそのままに置いてあります。 男たちは中を見てギョッとしました。
矢に目玉が付いていたのです。 「こんなことが有るのか?」
狼狽した一人はそのまま小屋を出て何処かへ行ってしまいました。
「まあいい。 今日からお前はここであの白馬の世話をするのだ。」 新しく連れてこられた男は白馬に目をやりました。
「何という気品の高い馬なんだ?」 「そうであろう。 皇帝がお乗りになる馬だ。 機嫌を損なうことの無いように頼むぞ。」
30年前からこの馬小屋で飼われている牝馬であります。 血統にもこだわった名馬中の名馬だと聞いております。
「この馬を世話しておった男は何処に行ってしまったんじゃろうなあ?」 「まあ、いいではないか。 今日からはお前がここの主人なのだ。」
「そうは言うけれど、、、。」 「クリスティーのことなら何年も前にここから居なくなったんだ。 そういうことしか伝わってないんだよ。」
「そんな男だったのか。 こんな名馬を残して。」 男は馬を見るとやり切れない気持ちになるのでした。
クリスティー、いやいやスコラディウスはホワイティアと二人で宮殿内を散策しております。 見たことも無いほどの広い広い宮殿です。
「この宮殿は何処まで行ったら端っこなのだ?」 「まだまだ先ですわ。 スコラディウス殿。」
スロープが延々と続いています。 その両側に執事や召使 女中たちの部屋が並んでおります。
その最も高く最も端っこに在るのがスコラディウスとホワイティアの寝室なのですが、、、。 そこまで行くのにどれだけ歩けばいいのか、、、?
スロープはグルグルと回っているようにも見えます。 (もしかしてこれは無限回廊の罠ではないのか?)
訝し気に廊下を見回すスコラディウスにホワイティアが笑い掛けました。 「無限回廊ではありません。 私たちの身を守るために敢えてこういう作りになっているのですよ。」
「防備が万全になっておるのだな。」 「そうです。 ザイミールの皇軍は恐ろしく凶悪で何事も恐れぬ軍隊ですから。」
「そんなに非道な軍隊だったのか?」 「あなた様はザイミールのお方でしたからお知りにはならなかったでしょう。 ですがカサブラーナの私どもにとっては、、、。」
そこまで話したホワイティアが突然に泣き崩れたものだからスコラディウスもどうしていいのか分かりません。
「ホワイティア、、、。」 廊下の真ん中で泣き崩れたホワイティアを兎にも角にも抱き寄せて宥めるのですが、、、。 姫の涙は止まりませぬ。
「ああ、この場において私は何をすれば姫の笑顔を取り戻すことが出来るのだ?」 彼の苦悶に気付いたのか一人の執事がやってまいりました。
「姫はカサブランカの香水がお好きであられます。 お部屋には香水の瓶がございますからお早く寝室へ行かれませ。」 「とはいっても寝室は、、、。」
「大丈夫でございます。 子の廊下をずっと進んでその突き当りが寝室ですから。」 スコラディウスはホワイティアを伴ってそれからずっとずっとしばらくしばらく歩き続けてやっとの思いで寝室に辿り着きました。
「ここなのか。 やっと着いたぜよ。」 木の扉を開けると見たことも無い華やかなベッドが置いてあります。
そしてその奥のほうには棚が並んでおりまして、その一つに香水瓶らしい物が並んでおります。 「これはすごいもんだ。 ザイミールの皇帝でもここまではなかったぞ。」
スコラディウスがその棚の前に立つと何処から香ってくるのか、香しいゴージャスな香りが漂ってまいります。 「これはすごい。 早速二もホワイティアの髪に、、、。」
彼が瓶の一つを手に取った時、天上から厳しい声が聞こえてきました。 「ならぬ。 お前はまだカサブラーナの洗礼を受けておらんのだ。 洗礼を受けずしてその瓶に触れるとは不敬であるぞ。」
「では私はどうすれば?」 「その命を投げ出しなさい。 死を持って洗礼とするのだ。」
「死ぬ? 私が?」 「拒むのであればホワイティアをお前には渡さん。 どうするかね?」
「スコラディウス殿 迷うことは無いのです。 あなたと私は遥かなる昔からこうして縁を結んできたのですから。」 「とはいっても、、、。」
「心配には及びません。 この船ももうすぐポラニシアの港に着きます。 そうすればあなた様も分かって下さるでしょう。」 「ポラニシア?」
「そう。 カサブラーナ最後の港です。」 「最後の港?」
クリスティーは何が何だか分からなくなってきました。 こうなってはホワイティアに従うより有りません。
料理を二人で拵えた彼はホワイティアを向かい側に座らせて食事を摂りました。 何とも言えぬ懐かしい味の食事です。
「これはいったい、、、?」 「あなた様もこうしてカサブラーナの食事を召し上がっていたのですよ。 それが証拠にザイミールでは食べないカサブランカの花料理までお召し上がりになられたんですね?」
「そうだったのか。 この俺もカサブラーナの、、、。」 「そうです。 少しお判りいただけたようですね。」
船はやがて港らしい入り江に入っていきました。 辺りには草原が鬱蒼と茂っているだけの、、、。
「ここが港であるか?」 「そうです。 古ぼけているように見えますが、カサブラーナではかなり新しい港なのです。」
船は岸壁に接岸しました。 「降りましょう。」
梯子が下ろされ、ホワイティアとクリスティーは岸壁へ恐る恐る降りました。 そこには誰も居ません。
「こんな所でどうやって、、、。」 疑いを深めるクリスティーの口を塞いでホワイティアは口笛を吹きました。
すると、、、。
二人の目の前に宮殿が現れました。
そして何処からともなく煌びやかな衣装をまとった男たちが駆け寄ってきたではありませんか。 「何だ、こいつらは?」
「スコラディウス殿 この人たちは私たちの臣下です。 ここで私たちは住まいを作り暮らしていくのですよ。」 「しかしだなあ、、、。」
「ご納得いただけませんか?」 「いや、、、というかだな、、、、。」
クリスティーは何もかもが出来過ぎていると思ったのです。 「国へ帰ろう。」
「何をおっしゃいます? ここがあなた様と私の国ではないですか。」 「しかし、、、。」
クリスティーが戸惑っているとホワイティアは再び口笛を吹きました。 「ご用でございますか?」
「蜂蜜の壺を持ってきてくださいな。」 「畏まりました。」
髪をきれいに整えた女が花弁がたくさん付いた甘い匂いがする壺を抱えてまいりました。 「ホワイティア殿 お持ちいたしました。」
ホワイティアは蜂蜜の匂いを確かめるとテーブルに置いてあるティーカップに紅茶を注いで蜂蜜を垂らしました。 「喉も乾いたでしょう? お飲みになってくださいな。」
クリスティーは疑いたい気持ちを抑えながらそのティーカップを手に取りました。 何とも懐かしい匂いが漂ってきます。
「これは何と言う懐かしい紅茶だ。 私はかつてこのような紅茶を飲んでいたのか?」 いつの間にか彼もカサブラーナの人間になっていたのです。
というべきか、それとも?
その頃、ザイミールではクリスティーが居なくなったことさえ誰も気付かぬほどに平和過ぎる一日を送っておりました。
あの馬もいつもと変わらず皇帝を乗せては庭を全力で走り、草を食んでは小屋で死んだように眠っております。 警護の兵士たちもいつものように門を見ながらボーっとしているようです。
そしていつの間にか3か月が過ぎ去ってしまいました。
「そういえば馬小屋のあの男はどうしたね?」 「さあ、、、。 今では姿も見掛けませぬ。」
「そうか。 どっかへ行ってしまいおったか。 それでは代わりの者をやろうではないか。」 呑気な皇帝はそう言うとエリカシオンという男を馬小屋にやりました。
馬小屋にはあの男が持っていた弓矢などがそのままに置いてあります。 男たちは中を見てギョッとしました。
矢に目玉が付いていたのです。 「こんなことが有るのか?」
狼狽した一人はそのまま小屋を出て何処かへ行ってしまいました。
「まあいい。 今日からお前はここであの白馬の世話をするのだ。」 新しく連れてこられた男は白馬に目をやりました。
「何という気品の高い馬なんだ?」 「そうであろう。 皇帝がお乗りになる馬だ。 機嫌を損なうことの無いように頼むぞ。」
30年前からこの馬小屋で飼われている牝馬であります。 血統にもこだわった名馬中の名馬だと聞いております。
「この馬を世話しておった男は何処に行ってしまったんじゃろうなあ?」 「まあ、いいではないか。 今日からはお前がここの主人なのだ。」
「そうは言うけれど、、、。」 「クリスティーのことなら何年も前にここから居なくなったんだ。 そういうことしか伝わってないんだよ。」
「そんな男だったのか。 こんな名馬を残して。」 男は馬を見るとやり切れない気持ちになるのでした。
クリスティー、いやいやスコラディウスはホワイティアと二人で宮殿内を散策しております。 見たことも無いほどの広い広い宮殿です。
「この宮殿は何処まで行ったら端っこなのだ?」 「まだまだ先ですわ。 スコラディウス殿。」
スロープが延々と続いています。 その両側に執事や召使 女中たちの部屋が並んでおります。
その最も高く最も端っこに在るのがスコラディウスとホワイティアの寝室なのですが、、、。 そこまで行くのにどれだけ歩けばいいのか、、、?
スロープはグルグルと回っているようにも見えます。 (もしかしてこれは無限回廊の罠ではないのか?)
訝し気に廊下を見回すスコラディウスにホワイティアが笑い掛けました。 「無限回廊ではありません。 私たちの身を守るために敢えてこういう作りになっているのですよ。」
「防備が万全になっておるのだな。」 「そうです。 ザイミールの皇軍は恐ろしく凶悪で何事も恐れぬ軍隊ですから。」
「そんなに非道な軍隊だったのか?」 「あなた様はザイミールのお方でしたからお知りにはならなかったでしょう。 ですがカサブラーナの私どもにとっては、、、。」
そこまで話したホワイティアが突然に泣き崩れたものだからスコラディウスもどうしていいのか分かりません。
「ホワイティア、、、。」 廊下の真ん中で泣き崩れたホワイティアを兎にも角にも抱き寄せて宥めるのですが、、、。 姫の涙は止まりませぬ。
「ああ、この場において私は何をすれば姫の笑顔を取り戻すことが出来るのだ?」 彼の苦悶に気付いたのか一人の執事がやってまいりました。
「姫はカサブランカの香水がお好きであられます。 お部屋には香水の瓶がございますからお早く寝室へ行かれませ。」 「とはいっても寝室は、、、。」
「大丈夫でございます。 子の廊下をずっと進んでその突き当りが寝室ですから。」 スコラディウスはホワイティアを伴ってそれからずっとずっとしばらくしばらく歩き続けてやっとの思いで寝室に辿り着きました。
「ここなのか。 やっと着いたぜよ。」 木の扉を開けると見たことも無い華やかなベッドが置いてあります。
そしてその奥のほうには棚が並んでおりまして、その一つに香水瓶らしい物が並んでおります。 「これはすごいもんだ。 ザイミールの皇帝でもここまではなかったぞ。」
スコラディウスがその棚の前に立つと何処から香ってくるのか、香しいゴージャスな香りが漂ってまいります。 「これはすごい。 早速二もホワイティアの髪に、、、。」
彼が瓶の一つを手に取った時、天上から厳しい声が聞こえてきました。 「ならぬ。 お前はまだカサブラーナの洗礼を受けておらんのだ。 洗礼を受けずしてその瓶に触れるとは不敬であるぞ。」
「では私はどうすれば?」 「その命を投げ出しなさい。 死を持って洗礼とするのだ。」
「死ぬ? 私が?」 「拒むのであればホワイティアをお前には渡さん。 どうするかね?」