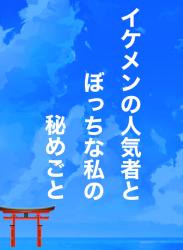「こら、誰か来ちゃうでしょう。次叫んだら、もう一度その可愛い口を塞いじゃうよ?」
咄嗟に両手で自分の口を塞ぐ。
私は声のボリュームを抑えて、八雲くんに抗議する。
「そんな大事なこと、なんではやく言わないんですか!」
「いつもなら、少し我慢すれば症状はおさまる。でも……なぜか、きみの血を飲みたいと思ったんだ」
八雲くんは、先程とはうってかわって、真剣な表情をしている。
「いつもとは違う、酷い喉の渇き。吸血鬼としての本能が、僕を突き動かした。けしてきみが『純潔』の血だからじゃない。これだけは、命にかけても嘘じゃないと誓えるよ」
ひゅっと喉が鳴った。
……あぁ、ついにバレてしまったのだ。
稀血の中でも、最上級に甘い血である『純潔』。
《純潔の血の持ち主は、血を飲み干されて死ぬ運命にある》
私はその『純潔』の血の持ち主だ。
汗ばむくらいだった体温が、急激に無くなっていく感覚に眩暈がした。
「禁断症状なんて、これまで何度か出てる。その度に助けるふりをして、僕を手籠にしようとした人は多いけれど、一度たりとも血を飲んだ事はない」
一瞬、八雲くんの瞳に暗い色が灯ったのは、気のせいじゃないはず。
八雲くんも、今まで自分の体質で色々とあったのかもしれない。
「僕にきみを守らせてほしい。僕じゃ役不足だろうか」
「そんなことはっ! ……ない、ですけど」
後半に行くにつれて、声が小さくなる。
もう自分の判断が正しいのか、信じられなくなってきた。
でもそんな私を見て、八雲くんは笑う。
「ふふっ、可愛い」
「か、可愛くないです!」
「可愛いよ。とても綺麗な瞳だ」
そう言われてやっと、眼鏡をかけていない事に気づく。眼鏡を探せば、ベッドの端に置かれていた。
手を伸ばしたけれど、途中で上から押さえつけられて惜しくも手が届かなかった。
「僕と二人きりの時は、眼鏡を外してほしいな」
「……嫌です」
「外してくれるの? 嬉しい」
「話を聞いてましたか!? と、とにかく! はやく私の上から退いてください!!」