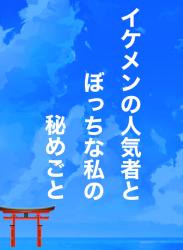鋭い牙が薄い皮膚を突き破り、どくどくと脈打つ血管へと一直線に向かう。
首筋で、はっと小さく息を飲む声が聞こえた気がした。
牙をたてられているのに、不思議と痛みはなかった。
かわりに、甘い痺れが全身を駆け巡っていく。
吸血鬼は、吸血対象の体に負担がないように『甘い毒』である自身の唾液を流し込みながら吸血をする。
けれどそれは、吸血対象を大事に思っていないとしない行為だ。
甘く痺れるそれは、毒の量が多ければ多いほど快楽へと変わる。
頭がぼうっとしてきた事実に、まだ冷静な部分が警鐘を鳴らした。
血を全て飲み干されてしまうぞ! と。
もう十分なはずなのに、まだ八雲くんは血を飲んでいる。
本格的に、まずいかもしれない。
私の体を巡る八雲くんの毒だけじゃなくて、八雲くんにとっても私の血は『甘い毒』だから。
「や、くもっくん……ッ!」
分厚いレンズがなくなり、クリアな視界で目が合った、と思った時には赤く濡れる唇が重ねられた。
自分の血が混ざっているから、けして甘いはずがないのに。
世界で一番甘い果実を食べているのかと錯覚するほどに、甘い、甘すぎるものが口いっぱいに広がる。
離れていく時、寂しさを覚えるほど。
お互いに息が上がり、瞳も潤んでいる。
そんな状態の八雲くんの色気は、凶器と言っていいほど。
女神様だって、裸足で逃げ出してしまうくらい綺麗な笑みを浮かべて、私を見つめる八雲くん。
「──会いたかった、僕の花嫁」
「はな、よめ?」
八雲くんから言われた単語の意味が、咄嗟には理解できなくて、無意識に同じ言葉を繰り返した。
「そう花嫁。──僕は血を飲んだら、生涯その人の血しか飲めない体質なんだ」
またもや凶器のような色気を含む笑みを浮かべられ、私は頬が引きつる。
「…………へ?」
「だから、いま風花ちゃんの血を飲んだから、僕は生涯風花ちゃん以外の血は飲めないってこと」
「ええぇぇぇぇ!?」
思わず叫べば、しーっと人差し指を当てられた。