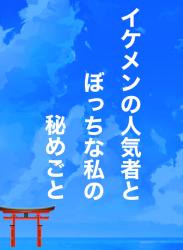「──二度目だ」
「え?」
「俺が人間の血を舐めたのは、これで二度目だ」
真白くんは、ポツリと語り出した。
その顔は暗く、なにか嫌なことを思い出しながら喋っているようだ。
「一度目は、物心がついてから初めて人間の血を舐めた時。母の友達で、指先に針を刺し流れた血を舐めさせられた。けれどそれは、この世の物とは思えないくらい不味かったんだ」
ぎゅっと強く眉が寄せられ、当時のことを追体験しているのか、声音は苦々しい。
「それから俺は血が嫌いになった。匂いをかいだだけでも、気分が悪くなる。あまつさえ、俺に血を吸われたいと乞う人間が近寄れば、吐き気がするようになった」
「そう……だったんですか」
「でも風花が郁人とこの教室に入って来た時、吐き気はしなかった。それはきみが、血を吸われたくないと思っていたからだろう」
たしかに、私は真白くんに血を吸われたいと思いながら、ここに来たわけじゃない。
「この気持ちが、きみが『純潔』の稀血だからなのか。それとも、風花だからなのか。それはまだわからない」
今度は、切なげに眉を寄せ私を見た真白くん。
「でも……きみの血が欲しいと、本能的に思った俺は、パートナーとして相応しくはないのだろうか」
懇願するような表情。
どうしてそう……八雲くんといい真白くんといい、私を絆すのが上手いんだ。
私の血を飲んでも正気を失わず、普通のパートナーとして接して、守ってくれる吸血鬼が他にいるだろうか。
──いつか恋に落ちて、愛し合える相手が。
この機会を逃せば、一生現れないかもしれない。
「そ、その……たまになら、良いですけど」
「君の血を飲んでもいいのか」
「はっきり言わないでください!」
「なら、風花の大切なものを俺にくれると?」
「いやらしい言い方をしないでくださいよ!?」
「そう怒るな。血が不味くなるぞ」
「えっ? ……そ、そうなんですか?」
そんな話、初耳だ。
自分で飲むことはないけれど、自分の体の一部である血が不味くなると言われたら、気になる。
「本当かどうか、いま確かめてやろう」