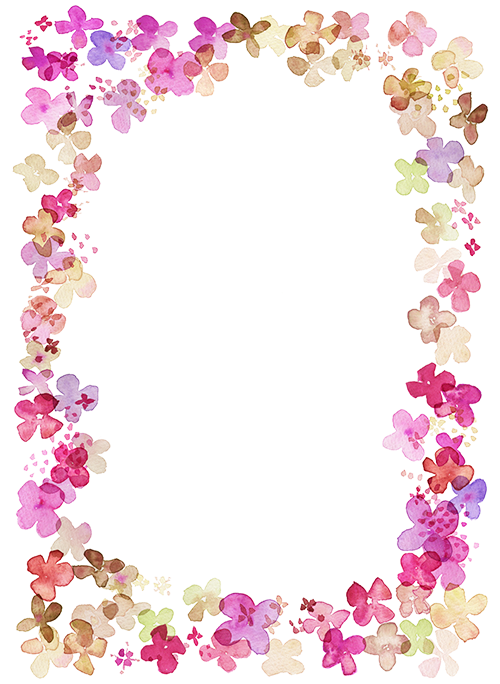「学校を探してもいないし、きっとここまで来てるんじゃないかと思って来たら、案の定この状況だからな。ったく、もっと自分の立場を自覚しろよ」
「ごめんなさい……」
私は素直に謝るしかなかった。
暗くなる前に帰るつもりだったけれども、完全に油断していた。
もし慧くんが来てくれなかったら、と思うと、どうしようもなく怖くなって泣きそうになった。
「本当にごめんなさい……。私が悪いの……」
うなだれる私の頭を慧くんはポンポンと撫でてくれた。
「もう謝るなよ。……悪いのは、俺の方だ。おまえを守るって誓ったのに、今日はそれができなかったんだからな……」
帰ろう。
と言うと、慧くんは私の手をぎゅっと握ってくれた。
見上げると、夕暮れの薄暗い中でも、やっぱりお日様みたいに明るい笑顔が、私を見下ろしていた。
私はぎゅうと慧くんの手を握り返した。