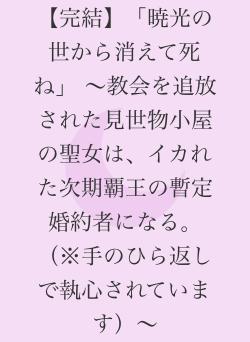今年の二月。祖母が脳卒中により意識を失っていたとき、私は――音楽を聴いていた。
それは強い雨の日。私は逃れるように布団にくるまって、時が過ぎるのをただ待っていた。
窓もカーテンもすべて締め切り、毛布で視界を隠して、音楽によって耳をふさぐ。
そうすることで、そのときだけは世界から切り離されたような心地になった。
だけどそれが、いけなかった。
私は台所で祖母が倒れたことに、まったく気づくことができなかったのだ。
台所で祖母を発見することができたのは、ほんの偶然だった。
こだわりもなく、音楽アプリのすすめるプレイリストがとある曲を流したとき、私は飛び起きた。
耳に流れてきたのは、純太郎が好きだったインディーズバンドの歌で。もうその頃にはメジャーデビューをしていた。
前奏の演出による雨音に驚いてしまい、耳からはイヤホンが落ちてしまって。
外から聞こえるザアザアという雨に恐怖した。同時に、部屋の扉をへだてた先から物音が一切ないことに、おかしく思った。
平屋の一軒家。そこまで広くない祖母の家は、いつも台所か茶の間から生活音が漏れていた。
テレビの音、料理の音。それらが聞こえてこず、私は胸騒ぎを覚えながら扉に手をかけて。
扉を開けた先の台所には――倒れた祖母の背中が見えていた。
祖母が倒れた日を境に、私は雨の日に音楽を聴くことをやめた。
殻に閉じこもって曲を流せば、一時的に私はPTSDの症状から解放されていた。
でも、それではいけなかったんだと、私ははじめて思ったのだ。
「ばあちゃんさっきね、しいちゃんと謙斗くんが話してるの、少し聞こえてたんだよ」
「それって」
「雨、克服したいんだねぇ、しいちゃん」
「そこ、聞こえてたんだ……」
おだやかに微笑む祖母の目じりに、深い皺が刻まれる。
慈愛にあふれる眼差しに、なぜか鼻の奥がつんと痛くなっていた。
「ばあちゃんはね、しいちゃんがしたいようにして欲しいんだよ。雨の日が苦しいなら、しいちゃんが苦しくならない日がくるまで、ゆっくり過ごしていけばいいと思ってるんだ」
「……」
「でも、しいちゃんが自分から克服したいと思っているのなら。ばあちゃんは応援するよ。ゆっくりでもいい、焦らなくてもいいから、頑張るんだよって」
純太郎のことがあってから、祖母はいつも私に寄り添ってくれた。
祖母の家にお世話になることが決まったときも、こころよく引き受けてくれて。
そんな祖母が、こう思ってくれている。
自分のペースでいいからと、私を応援してくれている。
「……おばあちゃん、私……いいのかな」
「うん?」
「雨を克服したいって、PTSDもちゃんと治したいって、思ってもいいのかな」
克服したいとは思っている。
治したいとは思っている。
とは、ではなくて、そうしたいのだと。
「……しいちゃん」
悲しそうな色に染まった祖母の瞳が、じんわりと優しさを帯びてゆく。
祖母は小さな声で、「いいんだよ、そう思っても」と言ってくれた。
「ばあちゃん、謙斗くんなら安心できるよ」
「え?」
「ほら、こんなにきれいな折り鶴を作れる子だもの。しいちゃんのことも、親身になって手伝ってくれると思うよ」
「……たしかに鶴は、きれいだね」
ベッドテーブルに置かれた、折り鶴。
出来栄えだけで作り手の人間性が、本当にすべて決まるとは思っていないけれど。
花壇に咲いた紫色のヒヤシンスといい、この藤色の折り鶴といい。
彼が生み出した小さなものたちからは、温かみがひしひしと感じられた気がした。