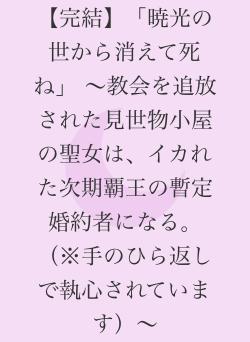しばらくすると、ミヤケンは勝男さんを送っていくいって、祖母の病室を後にした。
そして去り間際、私とミヤケンは連絡先の交換をしていた。
「謙斗くん、とてもいい子だったねぇ。話していて気持ちがいいし、なによりしいちゃんのお友達だものね。仲が良さそうでばあちゃん安心したわ」
すっかり私は、ミヤケンと友達ということになっている。
友達というには微妙な間柄だけれど、こんなに嬉しそうな祖母を前にして、否定もできなかった。
「おばあちゃんも、友達ができてよかったね」
「ふふ、お互いさまにねぇ」
祖母はころころと、楽しげに笑う。
こんな祖母を見るのは、かなり久しぶりな気がする。
「……あ、もうこんな時間なんだ。それじゃあ、私も今日は帰ろうかな」
そろそろこの病室にも、夕食が運ばれてくる。
こころなしかいい香りが漂っていた。
「鶴、けっきょく作れなかったね。でも、作って明日また持ってくるから。楽しみにしててね、おばあちゃん」
私は売店で買った千代紙を鞄にしまった。夜にでも折り方を検索して、挑戦してみよう。
そう心のなかで意気込むものの、祖母は少し困ったように笑っていた。
「しいちゃん、あんまりむりはしないでいいんだよ」
「え、むり? なんのこと? してないよむりなんて。もう体調は大丈夫だし……」
すると祖母は、ゆっくりと首を振る。
「体のことももちろん心配だけどね。ばあちゃんが言ってるのは、しいちゃんが負い目を感じて、むりしてここに来なくても大丈夫ってことなんだよ」
負い目といわれて、私はぎくりとした。
祖母がなにを伝えようとしているのか、わかってしまったから。
「……で、でも、むりはね……ぜんぜんしてないから」
「しいちゃんに会えるのは、ばあちゃんも本当に嬉しいんだよ。だけどね、しいちゃんには学校があって、友達もいるんだから。こんなにたくさん来なくても、ばあちゃんはもう大丈夫なんだよ」
慰めるような祖母の表情に、言葉が詰まってしまう。まるで粉薬を、水なしで飲んでしまったときのような心地になった。
「ごめんね、おばあちゃん……」
たしかに私は、祖母に負い目を感じていた。
祖母が入院するようになったのは、私と二人で暮らしていたとき、脳卒中を起こして倒れたから。
もっと搬送が早ければ、後遺症が残らずに済んだのかもしれない。
だけど祖母の左脚には、麻痺が残ってしまった。
リハビリを続けていれば回復するかもしれないと、そう聞いているけれど。庭で小さな畑を作っていた祖母はいま、しゃがむこともままならない。