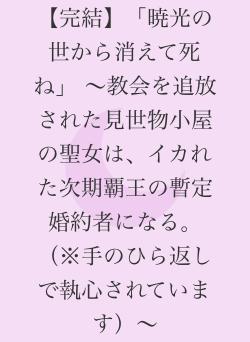「そうそう、これ見てくれない?」
「これって」
ズボンのポケットから携帯電話を取り出したミヤケンは、私に画面を見せてくる。
「四月の初めくらいに咲いてた、ヒヤシンスって名前の花。今までこういうの育てたことなかったけど、ちゃんと咲くと気分良くてさー、絶賛ハマり中」
画面の中には、艶やかな紫のヒヤシンスが色づいている。
それを嬉しそうに見せてくるので、私にまで気持ちが伝染していった。
「きれいですね」
「あ、佐山ちゃん笑った。やっぱり笑うと可愛いね」
「……なんでそういうことになるんですか」
美しい花を目に焼き付けていれば、いきなり私の話に切り替わった。
面と向かって慣れないことをいわれ身構えてしまう。
「いやいや、実はずっと気になってたんだよ。転校生ってそれだけで注目されるじゃん? しかも俺と佐山ちゃんてクラスも隣同士だし、どんだけサボっててもいろいろと耳に入ってきてたというか」
「……私のことをですか?」
「そう。ぜんぜん笑わない、話しかけても会話が続かない、いつもひとりで一匹狼状態、暗い」
「ああ……」
それはすべて学校のクラスメイトや同学年の生徒たちが抱く私の印象だった。
「佐山ちゃんが転校してきてそんな経ってなかった頃だと思う。廊下から佐山ちゃんのこと、ちらっと見えたときがあって」
「それで……?」
「あの子、笑ったら絶対可愛いんだろうなーって、そんときは想像してたかな」
どうしてこう、本人を前にしてド直球に伝えられるんだろう。
これも女好きたる所以なのか、ううん、絶対にそうだ。
「あの、あんまり見ないでください」
彼から顔をそむけるが、まだ話は続いていた。
「……ちゃんと笑える子なんだって、わかったからさ。もったいないなって、思うんだよ」
それは静かで、落ち着いた声音だった。
私にだけ聞こえるギリギリの大きさで、いつの間にか耳を澄ませている自分がいる。
「学校であんななのも、PTSDのせい? 不自由を強いられているから、人との付き合いを避けてるとか?」
「……そんなこと、聞いて楽しいですか」
「はは、楽しくはないね」
情けなく笑ったような声に、耳がこそばゆい。
知り合ったばかりの他人によくこれだけ強引に関わっていけるなと思う。私とは、まるで正反対。
「……症状が出て周りにどんな目で見られるのか。そう考えると、好きこのんで人付き合いをしようとは、思えないんです」
言わないといつまでも同じ問答を繰り返す予感がした。
だからミヤケンが尋ねた質問に、その通りだと答える。
半分、アタリ。もう半分は、別の理由だけれど。
「なら、症状を克服したとき……君は自由に笑えるってことだ」
「え?」
「やっぱり、俺に手伝わせてよ。佐山ちゃんの雨の克服。だって俺さ、知ったからにはスルーできないタチなんだ」
前にも聞いた気がする、その似たような台詞。
親身に寄ってくることが女好きな彼の方便なのだと、旧校舎裏を走り去っていくときは思っていた。
教室での一芝居。そして今、勝男さんの話を聞いて少しだけ考えを改める。
彼は学校での評判とかなり近い部分もある。
それに加えて――たぶん、一歩間違えればはた迷惑になり得る、超がつく関わりたがりのお人好し。
そういう人なんだと、思った。
「克服の手伝いって、具体的になにをするんですか?」
気圧された、といえばいいのだろうか。
私は彼に聞いてしまっていた。
だけどそれは、ただ流されたからという無責任なものじゃない。
中学二年生、永遠の時を止めた純太郎が、ふと脳裏によぎる。
本当は……本当は私も、どうしようもない過去と向き合うための、救いの手が欲しかった。