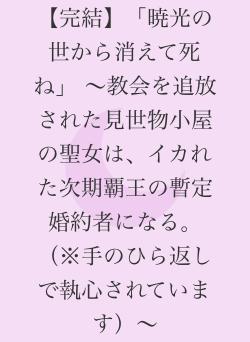「……最低」
昇降口を遠くに確認できたあたりで、私は走る速度をゆるめた。
短く息を吐き、そして吸い込んだ。
呼吸を整える合間、回想にふける。
やっぱり彼は、噂どおりの人だとはっきりわかった。
手伝い役とやらを頼む気はまったくなかったけれど、あの理由には不快だと、そう思った。
女好きといわれるミヤケンにとっては、些細な口説き文句だったのかもしれない。
だけど今の私は、そんな彼の性格に付き合うほどの余裕を持ち合わせていないのだ。
……面白おかしくかき乱されるほど、虚しく悲しいことはないんだから。
「ねえ、あそこにいるの佐山さんじゃない?」
感情に任せ肩にかかる鞄の持ち手をきつく握りしめたときだった。
そんな囁き声が聞こえてきた。
「あ、本当だ! あのあとどうしたんだろうね。ミヤケンにお姫様抱っこしてもらってたけどさー」
「なんか倒れたらしいけど、体が弱かったとか?」
「さぁ? ていうかあたしら、佐山さんと話したことないし。だって佐山さん、転校してきてからずっと一人でいるじゃん」
「んー、そうだけどさぁ。でも気になるじゃん。なんでミヤケンが佐山さんと一緒にいたとか」
振り返ると、同じクラスの女子と思われる二人組と目が合った。
彼女たちは、あ、と声を出す。こちらを見ながら肘でお互いの脇腹を突っつき合っていたが、なにも言わずに昇降口へとそそくさに歩いていった。
「あれ、あの子。ミヤケンが運んでた子じゃね? 昨日廊下ですれ違ったよ」
「なになに、なんの話し?」
「いや、昨日の放課後にミヤケンが保健室から女子を抱えて出てきて、それがあそこにいる子だって話」
さらに耳に入った会話の内容に、私は愕然とする。
いつの間にか生徒が一番に密集する登校時刻となっていた。
校門から昇降口にかけて流れ込んでくる生徒たちは、全員が全員ではないけれど、私に視線を送っている。
「そうそう。あの子、ミヤケンと保健室にいて……えーと、イチャついてる最中に気絶したんだっけ?」
「いや、知らねーよ。誰から聞いたんだそれ」
「誰だっけ。昨日部活で校内ランニングしてるときに、誰かが言ってたわ」
「それ、けっきょく誰だかわかんねーじゃん」
興味半分、好奇心は捨てきれないといった感じ。そんな男子生徒の曖昧な話し声が背中をかすめる。
噂というのは、当人たちの関係ないところで一人歩きして、真実をことごとく歪めていく。
私はそれをもう、身をもって知っていた。