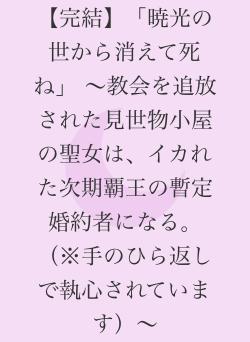いつの間にかミヤケンは、しゃがんだ状態で私の顔を覗き込んでいた。
「あ、なんだ。泣いてるんじゃないかって、心配したわ」
「泣いてないですけど」
「うん、よかった。もし泣いていた場合の慰め方法をどうしようかって悩む寸前だった」
「慰め方法?」
「知りたい? そうだなー、ほとんどの女の子なら頭ポンポンか優しくハグか……」
「その辺でもういいです」
「はい、りょーかい」
ミヤケンは立ち上がって笑いかけてくる。穏やかに細められた瞳がちょっと居心地悪い。
慰め方法に関する彼の発言には誠実さの欠片もなかった。
けれど心の中で燻っていたものが薄らいでいくような感覚に、今の一連の流れは彼がわざと作り出してくれたようにもみえる。
偶然かもしれないけれど、飄々とした変わらない態度に、ふとそう思ってしまった。
「ほぼ初対面の人間にこんなこと言われてもしょうがないだろうけど。佐山ちゃんが隠したいことは、誰にも言わない。だから、そこだけは信じてくれない?」
秘密にして欲しいとお願いしたのは私なのに、いつの間にかミヤケンのほうが下手に出ている。
それがなんだか不思議とおかしくて、私は頷いていた。
「わかりました、信じます。私のほうこそ、よろしくお願いします」
「あー、よかった! 佐山ちゃん、ずっと暗い顔してるからさ、どうしようかと思った」
安堵した様子のミヤケンの顔をそれとなく見る。
先ほどまで気にもなっていなかったけれど、母の言うとおり彼はとても綺麗な顔をしていた。
容姿だけでいうならば、モテるというのも納得。
「……それじゃあ、私はこれで」
ようやく切り替えられる。
そもそもミヤケンは校内で一目置かれた存在で、昨日の出来事がなければ関わることもない。
そんな人と長く一緒にいるのは、普段ひとりで学校生活を送る私からすると気が引ける。
目的はしっかりと果たしたので、そろそろ私は退散したかった。
――のに。
「あ、ちょっと待って、佐山ちゃん」
「はい」
「佐山ちゃんのことは誰にも言わない。言うつもりもない。その代わりひとつ俺の希望を聞いて欲しいんだけど」
「……希望。それは、なんですか?」
唐突に不安がよぎる。せっかく丸く収まったと思いきや、これだもの。
「昨日の友っちと岡ちゃん先生の話でさ、気になることがあって」
「……」
「PTSDの症状と雨を克服したいと思ったから、佐山ちゃんはこの学校に転校してきたんだって? なら、その克服する手伝い役とかに、立候補させて欲しいなーって。思ってさ」
「……は?」
どこまでが本気で、どこまでが冗談なのか。
困惑と呆然の両方が混ざりに混ざった結果、私は見事に硬直していた。
そしてなによりも、陽気に語るミヤケンの不自然すぎる真剣な眼差しが、私の理解の範疇を超えていた。