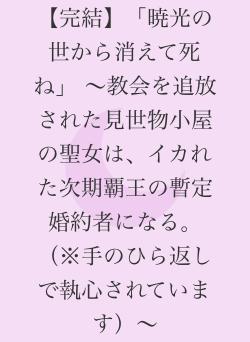聞き間違いなんかじゃなかったと、旧校舎裏に回り込んだ私は思い直す。
プラスチック製の深緑色に塗られた如雨露を片手に、ひとりの男子生徒が花壇に水をやっている。
宮謙斗――ミヤケンだった。
晴れきった朝の日差しは、柔らかそうに靡く栗色の髪を照らしていて。
高身長と思われる彼は、低い花壇との距離を縮めるように背中をわずかに丸めていた。
私はその姿を建物の影に隠れてひっそりと盗み見る。
はたから見たら完全に不審者だ。けれど、どうにも出られる空気ではない。
出ようと思えば出られるものの、私の足がすすんで前にいかないのは、困惑してしまったからだ。
「……」
瞳に映した彼の横顔は、これまでの醜聞をすべて払拭してしまうような、静謐な雰囲気に溢れていた。
保健室にいた人と、目と鼻の先にいる人はまるっきり同じ人物であるはずなのに、なんだか別人に見えてしまう。
要するに声をかけづらい。
それがいつまでも物陰に身を潜ませていた理由である。
ふいに、頭上からバタバタと鳥の羽ばたく音が聞こえた。
その一瞬で我に返ると、私は紙袋の手提げ紐を強く握りこんだ。
いつまでもこんなことをしていられない。
様子を隠れて見ているなんて、相手からしてみればすごく失礼だし気分も悪いだろう。
「ミヤケ……宮くん」
私は意を決して、花壇に近づいた。