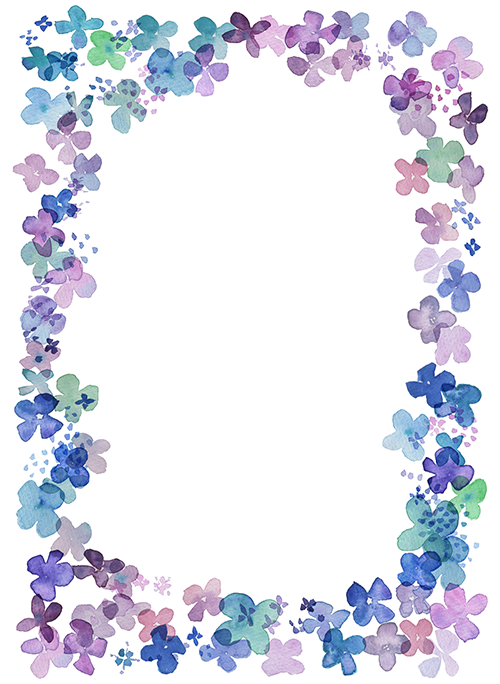夕日は悩ましげな雰囲気を出しているせいか、伏せがちな目や引き結ばれた唇から色気という色気が溢れており、直人は直視出来ずにそっと目を逸らす。
「お前ならモモに何も言わねぇで飛鳥って書くと思ってた」
「…俺はモモと兄妹になりたい訳ではない」
夕日がそう答えると直人は納得したようだ。
直人がこちらに来たことにより、することが無くなったのだろう華も夕日の元へ向かってくる。
「モモちゃんの、苗字、ですか?」
華は机に置いてある紙を覗き込むと、不思議そうに首を傾げた。
「えっと…そういえばモモちゃんの苗字を聞いたことが無いんですけど、
…家族に虐待されていて、元の苗字を使いたくないとかですか?」
幹部たちとは違い、モモの事情を初めから知らない華はそこからわかっていないらしい。100番と言った番号で常に呼ばれていたモモには、苗字どころか名前すら無かったのだ。
特に説明する気のない夕日は、華の言葉にまあそんなところだと肯定した。
モモも自分と同じように家から逃げ出してきたところを拾われたのだろう。であれば、華とモモは立場的に見れば同じようなものではないか?
夕日がモモに優しく接するのもそれが理由だろうか。
華は一人納得したように頷くと、モモの苗字を一緒になって考えてくれているようでまた深く首を捻った。
「くっそわかんねぇ…
いや、アイツに苗字がついてんのが想像できねぇ…」
「えっ、じゃあ直人もモモちゃんの本来の苗字を教えて貰ってないんですか!?」
「いや、…まあ」
直人は言葉を濁して夕日を見る。
夕日は直人に気がつくと、どうした?と問うようにクイッと片眉を上げる。
「お前ならモモに何も言わねぇで飛鳥って書くと思ってた」
「…俺はモモと兄妹になりたい訳ではない」
夕日がそう答えると直人は納得したようだ。
直人がこちらに来たことにより、することが無くなったのだろう華も夕日の元へ向かってくる。
「モモちゃんの、苗字、ですか?」
華は机に置いてある紙を覗き込むと、不思議そうに首を傾げた。
「えっと…そういえばモモちゃんの苗字を聞いたことが無いんですけど、
…家族に虐待されていて、元の苗字を使いたくないとかですか?」
幹部たちとは違い、モモの事情を初めから知らない華はそこからわかっていないらしい。100番と言った番号で常に呼ばれていたモモには、苗字どころか名前すら無かったのだ。
特に説明する気のない夕日は、華の言葉にまあそんなところだと肯定した。
モモも自分と同じように家から逃げ出してきたところを拾われたのだろう。であれば、華とモモは立場的に見れば同じようなものではないか?
夕日がモモに優しく接するのもそれが理由だろうか。
華は一人納得したように頷くと、モモの苗字を一緒になって考えてくれているようでまた深く首を捻った。
「くっそわかんねぇ…
いや、アイツに苗字がついてんのが想像できねぇ…」
「えっ、じゃあ直人もモモちゃんの本来の苗字を教えて貰ってないんですか!?」
「いや、…まあ」
直人は言葉を濁して夕日を見る。
夕日は直人に気がつくと、どうした?と問うようにクイッと片眉を上げる。