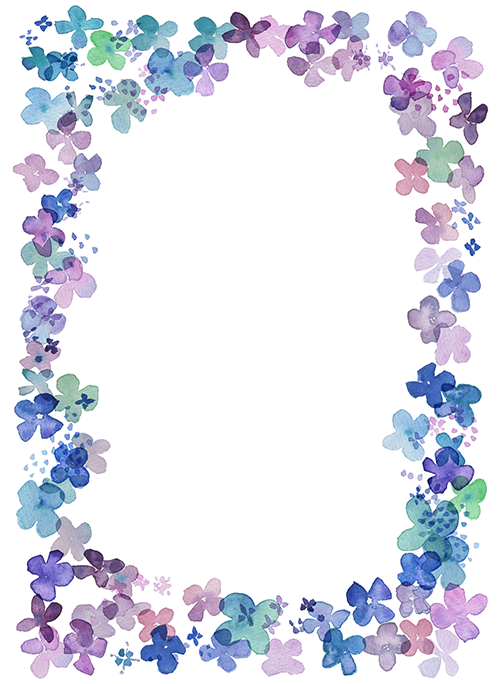――
もううんざりだった。
泣いてばかりいる母親も、アルコール中毒の父親も。防音設備の欠片もない部屋だから、うちの事情は全て理解しているだろうに、何も知らないフリをする隣人にも。
そして、気付いてくれないみんなに。
いっそどこかへ消えてしまいたい。
家出するつもりで財布と携帯だけを持って家を出た。
夕暮れ辺りに家を出たのか幸をなしたのか真夏の一番強い太陽を直に浴びることはなかったが、ジワリジワリと汗が滲み出て鬱陶しい。
化粧なんてするんじゃなかった。
そう思った。
宛もなくいつもの繁華街を突き進みようやく光が灯り出したネオンを見る。
ここはいつでも自由で落ち着く。
それにしても身体中の水分が蒸発しそうなほど蒸し暑い。
コンビニで水でも買おうと思い当たり、華は近道にもなる日の当たらない涼しい道を通ろうと路地裏に向かった。
まだそんなに遅くは無い時間帯であるため襲われはしないだろうという、軽い思い込みもあった。
後ろからいきなり腕を掴まれ着ている服を剥ぎ取られる。何度も叫ぼうと、逃げようとしたが脇腹を思い切り蹴られ力が出なかった。
これが力のない女の姿かと、自分に失望した。
男は“青鷺”という暴走族グループの一員らしい。
青鷺という名前は、この地区に住んでいる人ならば誰でも一度は耳にしたことがある名前だろう。
2年ほど前から活発に動くようになったらしく、親から子供へ、○○と○○には気をつけなさいと言われる二つのうちの一つには確実に入っていると思う。
この男がその青鷺だとは信じたくなくて必死に華は食い下がる。
男は泣いて華に嗜虐心を感じているようで、ニヤニヤと醜く顔を歪ませながら、より華に恐怖を感じさせるために自分が青鷺だと言う証拠を口に出していった。
華は恐怖で体が震えるのを感じた。
必死に誰かに助けを求めるが、こんな路地裏を通る人などほとんどいないことは華も知っていた。
男は華の体を路地裏の壁に押し付け、恐怖で歪む華の顔を楽しいながら何度も何度も華の体を突き上げた。華の快感なんて考慮もしない、最悪な抱き方だった。
しばらくして、男が達したようで華の腟内にじわりと精子が障壁も無しに放たれる。
最悪の気分だった。
華は疲れも構わずに無我夢中で男の声も聞かず、必死にそこを通るかも知れない誰かに助けを求めた。
もううんざりだった。
泣いてばかりいる母親も、アルコール中毒の父親も。防音設備の欠片もない部屋だから、うちの事情は全て理解しているだろうに、何も知らないフリをする隣人にも。
そして、気付いてくれないみんなに。
いっそどこかへ消えてしまいたい。
家出するつもりで財布と携帯だけを持って家を出た。
夕暮れ辺りに家を出たのか幸をなしたのか真夏の一番強い太陽を直に浴びることはなかったが、ジワリジワリと汗が滲み出て鬱陶しい。
化粧なんてするんじゃなかった。
そう思った。
宛もなくいつもの繁華街を突き進みようやく光が灯り出したネオンを見る。
ここはいつでも自由で落ち着く。
それにしても身体中の水分が蒸発しそうなほど蒸し暑い。
コンビニで水でも買おうと思い当たり、華は近道にもなる日の当たらない涼しい道を通ろうと路地裏に向かった。
まだそんなに遅くは無い時間帯であるため襲われはしないだろうという、軽い思い込みもあった。
後ろからいきなり腕を掴まれ着ている服を剥ぎ取られる。何度も叫ぼうと、逃げようとしたが脇腹を思い切り蹴られ力が出なかった。
これが力のない女の姿かと、自分に失望した。
男は“青鷺”という暴走族グループの一員らしい。
青鷺という名前は、この地区に住んでいる人ならば誰でも一度は耳にしたことがある名前だろう。
2年ほど前から活発に動くようになったらしく、親から子供へ、○○と○○には気をつけなさいと言われる二つのうちの一つには確実に入っていると思う。
この男がその青鷺だとは信じたくなくて必死に華は食い下がる。
男は泣いて華に嗜虐心を感じているようで、ニヤニヤと醜く顔を歪ませながら、より華に恐怖を感じさせるために自分が青鷺だと言う証拠を口に出していった。
華は恐怖で体が震えるのを感じた。
必死に誰かに助けを求めるが、こんな路地裏を通る人などほとんどいないことは華も知っていた。
男は華の体を路地裏の壁に押し付け、恐怖で歪む華の顔を楽しいながら何度も何度も華の体を突き上げた。華の快感なんて考慮もしない、最悪な抱き方だった。
しばらくして、男が達したようで華の腟内にじわりと精子が障壁も無しに放たれる。
最悪の気分だった。
華は疲れも構わずに無我夢中で男の声も聞かず、必死にそこを通るかも知れない誰かに助けを求めた。