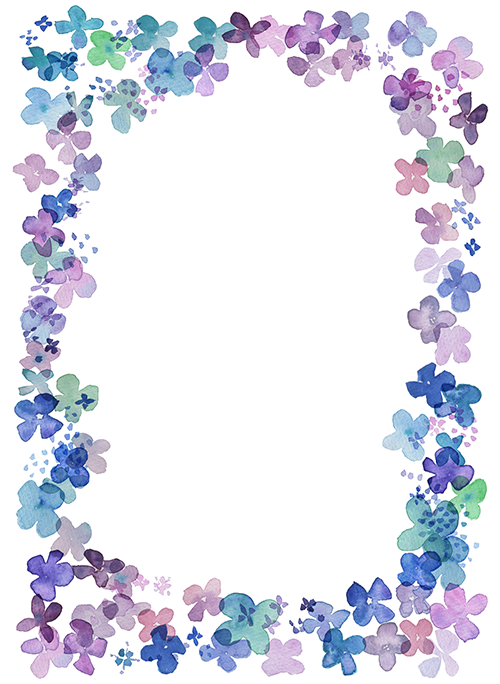コツコツと靴の音が響く。
少女が行動する中で、少女が自分で出したものでは無い、初めての音だ。
少女は顔をパッと輝かせてサメのぬいぐるみを投げ捨て、扉まで駆け寄った。
外側から鍵が開かれ入ってきた男に少女は近付く。
「こんにちは、こんにちは!」
「おはよう。……100番、仕事だ。早く食べてくれ」
「お仕事?うん!」
男の言葉を聞き、お盆に乗せられたなんの変哲のないパンとガラスのコップに入ったミルクを、少女は素早く胃に詰め込んだ。
少女が食べ終わるのを見届けると、男は少女を先導し歩き始めた。
「何番?」
「あー、今日は2603番だな」
「03番!」
2603番というと、細身で猫背なのが特徴のいかにも苦労性の人だ。
あまりレパートリーのない少女の話を毎度聞いてくれる優しい人でもある。
少女は嬉しそうにぴょんぴょんと跳ねる。
それでも男は少女を待たずにササッと歩いていくので、少女は少し小走りになりながら着いていった。
「03番だー!」
「おぉ、今日は100番か」
その場所に通されると、男は用は済んだとばかりに帰っていく。
男の言う100番のは紛れもなく少女の事だ。
少女は2603番と呼ばれる男に飛びついた。
少女が行動する中で、少女が自分で出したものでは無い、初めての音だ。
少女は顔をパッと輝かせてサメのぬいぐるみを投げ捨て、扉まで駆け寄った。
外側から鍵が開かれ入ってきた男に少女は近付く。
「こんにちは、こんにちは!」
「おはよう。……100番、仕事だ。早く食べてくれ」
「お仕事?うん!」
男の言葉を聞き、お盆に乗せられたなんの変哲のないパンとガラスのコップに入ったミルクを、少女は素早く胃に詰め込んだ。
少女が食べ終わるのを見届けると、男は少女を先導し歩き始めた。
「何番?」
「あー、今日は2603番だな」
「03番!」
2603番というと、細身で猫背なのが特徴のいかにも苦労性の人だ。
あまりレパートリーのない少女の話を毎度聞いてくれる優しい人でもある。
少女は嬉しそうにぴょんぴょんと跳ねる。
それでも男は少女を待たずにササッと歩いていくので、少女は少し小走りになりながら着いていった。
「03番だー!」
「おぉ、今日は100番か」
その場所に通されると、男は用は済んだとばかりに帰っていく。
男の言う100番のは紛れもなく少女の事だ。
少女は2603番と呼ばれる男に飛びついた。