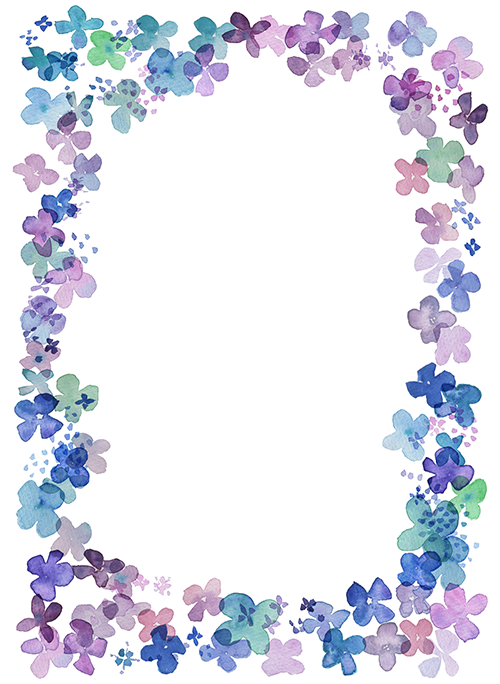「モモ暇そうだね」
「暇だよー」
「ねぇねぇ、俺が喫茶店っていうか、ケーキ屋なんだけど連れてってあげようか?」
春馬が言うケーキ屋といえば、何度もお土産のように買っては倉庫に持ってきてくれるあのケーキが売っている所だろうか。
その店のチョコケーキが、なんというか糖分控えめでずっと食べれるぐらいになんとも美味しいのだ。
モモはグデッと夕日にもたれかかっていた体を、お腹に力を入れて引き落とした。
「いいの?行きたい!」
ただでさえ部屋に籠りっきりだったので、この際どこでもいいから出かけたいと思っていたのも本当だ。
春馬はモモに対しおいでと腕を軽く広げてくれる。
何故か最近よくされるのだ。
モモが体を起こしてもらおうと手を伸ばすと、夕日がそれを阻むようにモモを持ち上げたまま立ち上がる。
「…嫉妬深いなぁ。
モモも嫌になったら言わないとダメだよ?」
そんなに夕日は嫉妬深いのだろうか。
ちらりと夕日を伺ってみると、もうモモの分まで出かける準備をしてくれているようで無言でモモの頭にお揃いの帽子を被せてくれた。
ただ嫉妬深いと受け入れるよりも先に嫉妬とはどのような感情なのだろうかを定義しておいた方がいいと思い、何を嫉妬と呼ぶのかを考えてみる。
羨ましいといった感情を持つことだとして考えてみよう。
それならばモモがあの夕日に抱かれていた女の人に感じた、もしもモモが抱かれていたらと想像したあの時の気持ちに近いのだろうか。
それは何だか違うような気もする。
モモはただ夕日の相手が自分であればと考えただけで、女の人に対しては一切の感情を持ち合わせていないのだから。
「暇だよー」
「ねぇねぇ、俺が喫茶店っていうか、ケーキ屋なんだけど連れてってあげようか?」
春馬が言うケーキ屋といえば、何度もお土産のように買っては倉庫に持ってきてくれるあのケーキが売っている所だろうか。
その店のチョコケーキが、なんというか糖分控えめでずっと食べれるぐらいになんとも美味しいのだ。
モモはグデッと夕日にもたれかかっていた体を、お腹に力を入れて引き落とした。
「いいの?行きたい!」
ただでさえ部屋に籠りっきりだったので、この際どこでもいいから出かけたいと思っていたのも本当だ。
春馬はモモに対しおいでと腕を軽く広げてくれる。
何故か最近よくされるのだ。
モモが体を起こしてもらおうと手を伸ばすと、夕日がそれを阻むようにモモを持ち上げたまま立ち上がる。
「…嫉妬深いなぁ。
モモも嫌になったら言わないとダメだよ?」
そんなに夕日は嫉妬深いのだろうか。
ちらりと夕日を伺ってみると、もうモモの分まで出かける準備をしてくれているようで無言でモモの頭にお揃いの帽子を被せてくれた。
ただ嫉妬深いと受け入れるよりも先に嫉妬とはどのような感情なのだろうかを定義しておいた方がいいと思い、何を嫉妬と呼ぶのかを考えてみる。
羨ましいといった感情を持つことだとして考えてみよう。
それならばモモがあの夕日に抱かれていた女の人に感じた、もしもモモが抱かれていたらと想像したあの時の気持ちに近いのだろうか。
それは何だか違うような気もする。
モモはただ夕日の相手が自分であればと考えただけで、女の人に対しては一切の感情を持ち合わせていないのだから。