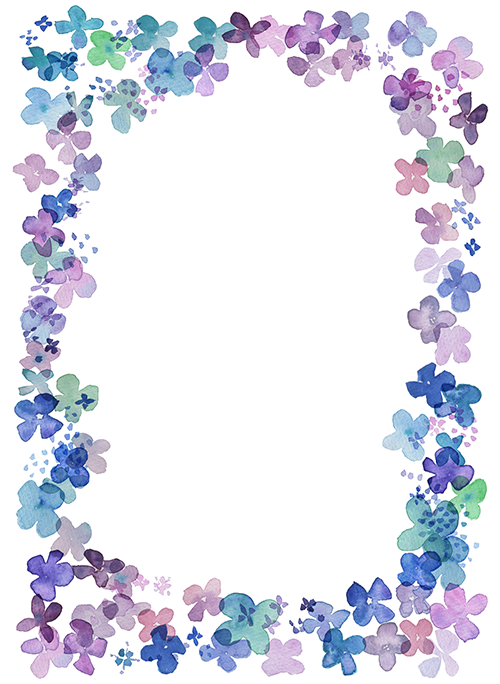「ふんふーんふんふんふん」
窓の締め切られた殺風景な部屋の中でその小柄な16の少女は微かに頭に残っているだけの曲を紡いでいる。
その一室にあるものは水の出る水道と大きなサメのぬいぐるみが一つずつ、あとは大量の本だけだ。
それも、子供用の動物図鑑一冊と、辞典、あとは大量にある大人が読むような人体解剖学の専門書だけというアンバランスさが際立っているものだ。
その他には時計ひとつない。
少女は図鑑をにこにことペラペラ捲りながら、独り言を言うようにぬいぐるみに話しかける。
「かわいいねー、サメ。強いね、かっこいい?海、水の中、冷たいね?」
サメのぬいぐるみはただジッと聞いている。少女は図鑑のサメの輪郭を指でなぞる。
「すい、ぞくかん?キラキラぁ……」
付属で載っていた写真の一枚が水族館で撮られたもののようで、その空間は青く輝いている。
少女は生まれてこの方、一度も家の外に出して貰えたことがない。
人との交流自体もそれほど無く、家から駆り出される時以外で誰かと話すことの出来る瞬間は日に三回食事が運ばれてくる時だけだった。
何故少女はこのように閉じ込められなければいけなかったのか。
だが少女はそれを考えることが無かった。
生まれてからずっとそうだったことから、その待遇が少女にとって当たり前となっているのだ。
窓の締め切られた殺風景な部屋の中でその小柄な16の少女は微かに頭に残っているだけの曲を紡いでいる。
その一室にあるものは水の出る水道と大きなサメのぬいぐるみが一つずつ、あとは大量の本だけだ。
それも、子供用の動物図鑑一冊と、辞典、あとは大量にある大人が読むような人体解剖学の専門書だけというアンバランスさが際立っているものだ。
その他には時計ひとつない。
少女は図鑑をにこにことペラペラ捲りながら、独り言を言うようにぬいぐるみに話しかける。
「かわいいねー、サメ。強いね、かっこいい?海、水の中、冷たいね?」
サメのぬいぐるみはただジッと聞いている。少女は図鑑のサメの輪郭を指でなぞる。
「すい、ぞくかん?キラキラぁ……」
付属で載っていた写真の一枚が水族館で撮られたもののようで、その空間は青く輝いている。
少女は生まれてこの方、一度も家の外に出して貰えたことがない。
人との交流自体もそれほど無く、家から駆り出される時以外で誰かと話すことの出来る瞬間は日に三回食事が運ばれてくる時だけだった。
何故少女はこのように閉じ込められなければいけなかったのか。
だが少女はそれを考えることが無かった。
生まれてからずっとそうだったことから、その待遇が少女にとって当たり前となっているのだ。