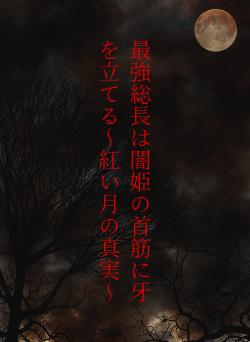「これだけ綺麗な花が咲いてるのに、俺には紫音しか見えない」
「ふぇ!?よ、夜桜先輩?」
「せっかく2人きりになれたんだ。カッコつけたセリフのひとつも言わせてくれよ」
「は、はぁ…」
こっちとしては恥ずかしいから困るんだけど。
「お前は花を見ながら、俺の話を軽く聞いてるだけでいいから」
「軽くなんて聞けないです!」
「なんでだ?」
「そんなこと言われたら恥ずかしくて、花を見るどころじゃ…なくなるからです」
意識したら更に顔が熱くなってきた。
「これだけ綺麗なものがあっても、お前は霞んだりしない。俺にとっては紫音が一番だから」
「私も夜桜先輩が一番です」
「紫音」
ドサッ。
私はその場に押し倒された。
これだけ求められてるのに、拒絶する理由がどこにあるだろう。
神さま、今だけはどうか許してください。
女の子の姿である私が、夜桜先輩にどうしようもなく溺愛されていることを。
月だけが私たちを照らす中で、私は夜桜先輩に抱きしめられた。
「ふぇ!?よ、夜桜先輩?」
「せっかく2人きりになれたんだ。カッコつけたセリフのひとつも言わせてくれよ」
「は、はぁ…」
こっちとしては恥ずかしいから困るんだけど。
「お前は花を見ながら、俺の話を軽く聞いてるだけでいいから」
「軽くなんて聞けないです!」
「なんでだ?」
「そんなこと言われたら恥ずかしくて、花を見るどころじゃ…なくなるからです」
意識したら更に顔が熱くなってきた。
「これだけ綺麗なものがあっても、お前は霞んだりしない。俺にとっては紫音が一番だから」
「私も夜桜先輩が一番です」
「紫音」
ドサッ。
私はその場に押し倒された。
これだけ求められてるのに、拒絶する理由がどこにあるだろう。
神さま、今だけはどうか許してください。
女の子の姿である私が、夜桜先輩にどうしようもなく溺愛されていることを。
月だけが私たちを照らす中で、私は夜桜先輩に抱きしめられた。