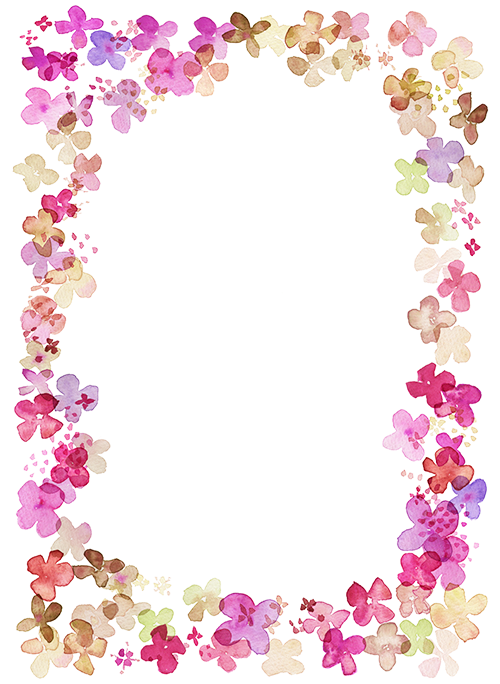「どれも似合っているものだから、全部欲しくなってしまう」
と満足げに言う聡一朗さんだったけれども、私の顔を見て、
「すまない、俺の好みばかりで決めていたけれども、君はどうなんだい? 気に入ったものはあったかい?」
と気遣ってくれる。
「もちろんです、どれも素敵でした」
「そう言う割には楽しそうな顔はしていないが。――そういえば、ファッションにはあまり関心がないと言っていたね」
私は小さく首を振り、
「おしゃれするのは嫌いじゃないんです、ただ、こういうことに慣れていなくて……」
うちは小さな菓子店でそれほど裕福というわけではなかったので、子どもの頃からあれもこれもと買ってもらうのを遠慮しがちだった。
それでおしゃれすることに疎くなってしまい、おしゃれではない自分にも慣れてどこか自己卑下になってしまって、自分に自信が持てなくなってしまった。
と満足げに言う聡一朗さんだったけれども、私の顔を見て、
「すまない、俺の好みばかりで決めていたけれども、君はどうなんだい? 気に入ったものはあったかい?」
と気遣ってくれる。
「もちろんです、どれも素敵でした」
「そう言う割には楽しそうな顔はしていないが。――そういえば、ファッションにはあまり関心がないと言っていたね」
私は小さく首を振り、
「おしゃれするのは嫌いじゃないんです、ただ、こういうことに慣れていなくて……」
うちは小さな菓子店でそれほど裕福というわけではなかったので、子どもの頃からあれもこれもと買ってもらうのを遠慮しがちだった。
それでおしゃれすることに疎くなってしまい、おしゃれではない自分にも慣れてどこか自己卑下になってしまって、自分に自信が持てなくなってしまった。