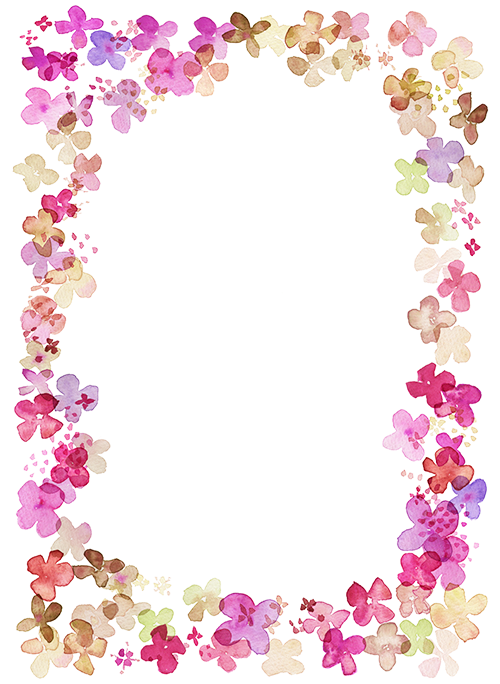「私は認めないわよ、あなたのような小娘が先生と結婚するなんて」
そんなことを言われても、どうすればいいというのだろう。
これは利害が一致しただけの関係だからあなたの考えているようなものではない、なんて言えるわけもないし。
私だって聡一朗さんがなぜ私を選んでくれたのか、未だに納得できない。
でも契約婚とはいえ、申し出てくれたのは聡一朗さんなのだ。
「図々しい子とは思っていたけれど、こうまであざといとは予想もしてなかったわ。大学にも行っていない無教養な小娘が、うまくやってくれたものね」
まるで性悪女を蔑むような言葉に、さすがの私もムッとくる。
たしかに私は大学に行かないことを選んだ。でも行けなかったわけじゃない。
それに聡一朗さんだって言ってくれた。
誰でもよかったわけじゃない、って。
「聡一朗さんが私をちゃんと評価して選んでくださったんです。その聡一朗さんの判断を、あなたがとやかく言う筋合いはないわ」
私にしては会心の反撃。
けれども、かえって火に油をそそいだようで、紗英子さんはさらに目を剥いて冷ややかな笑みを浮かべた。
そんなことを言われても、どうすればいいというのだろう。
これは利害が一致しただけの関係だからあなたの考えているようなものではない、なんて言えるわけもないし。
私だって聡一朗さんがなぜ私を選んでくれたのか、未だに納得できない。
でも契約婚とはいえ、申し出てくれたのは聡一朗さんなのだ。
「図々しい子とは思っていたけれど、こうまであざといとは予想もしてなかったわ。大学にも行っていない無教養な小娘が、うまくやってくれたものね」
まるで性悪女を蔑むような言葉に、さすがの私もムッとくる。
たしかに私は大学に行かないことを選んだ。でも行けなかったわけじゃない。
それに聡一朗さんだって言ってくれた。
誰でもよかったわけじゃない、って。
「聡一朗さんが私をちゃんと評価して選んでくださったんです。その聡一朗さんの判断を、あなたがとやかく言う筋合いはないわ」
私にしては会心の反撃。
けれども、かえって火に油をそそいだようで、紗英子さんはさらに目を剥いて冷ややかな笑みを浮かべた。