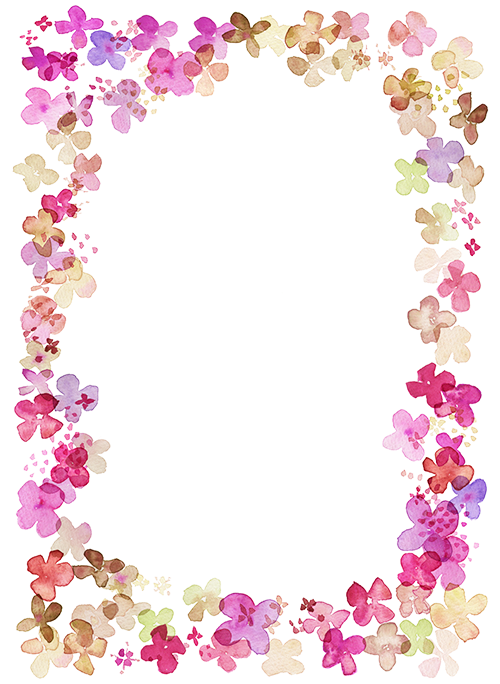同居しているからといって、一緒に帰宅後の時間を過ごす義務も必要性も私たちの関係には存在しない。
なのに、まるで普通の奥さんみたいな質問をしてしまった。
と、しょんぼりしていると、不意に頭をポンポンと撫でられた。
思わず聡一朗さんを見やると、その顔が近付いてきて、
「寂しい思いをさせてすまない。いちおう俺たち、新婚なのにな」
私の耳元でそっと囁いてくれた。
「今度一緒に食事に行こう。結婚のお祝いもまだだったし、君の好きなものをご馳走するよ」
そして、息もかかりそうなすぐそばで、微笑んでくれた。
聡一朗さん独特のそれではない、はっきりと分かる優しい笑み。
それをまるで、私だけに捧げてくれるように。
最後にもう一度ポンポンと私の頭を撫でると、聡一朗さんは去って行った。
その後ろ姿を茫然と見送る私の視界に、さっきの女の子たちが唖然としてこちらを見ている姿が映った。
私は真っ赤になって逃げるようにカフェから出て行った。
浮き立つような胸の高揚を隠すのに必死になりながら。
なのに、まるで普通の奥さんみたいな質問をしてしまった。
と、しょんぼりしていると、不意に頭をポンポンと撫でられた。
思わず聡一朗さんを見やると、その顔が近付いてきて、
「寂しい思いをさせてすまない。いちおう俺たち、新婚なのにな」
私の耳元でそっと囁いてくれた。
「今度一緒に食事に行こう。結婚のお祝いもまだだったし、君の好きなものをご馳走するよ」
そして、息もかかりそうなすぐそばで、微笑んでくれた。
聡一朗さん独特のそれではない、はっきりと分かる優しい笑み。
それをまるで、私だけに捧げてくれるように。
最後にもう一度ポンポンと私の頭を撫でると、聡一朗さんは去って行った。
その後ろ姿を茫然と見送る私の視界に、さっきの女の子たちが唖然としてこちらを見ている姿が映った。
私は真っ赤になって逃げるようにカフェから出て行った。
浮き立つような胸の高揚を隠すのに必死になりながら。