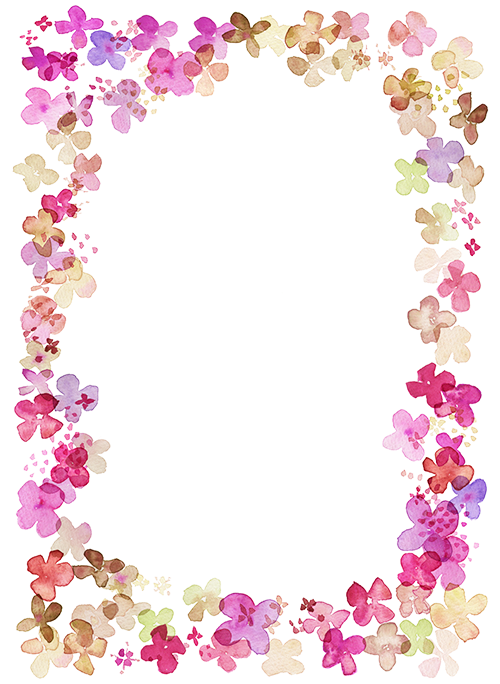すでに着席している人たちの後ろを詫びながらやっと席にたどり着くと、その子たちは急に不機嫌な顔になった。
邪魔だから私たちの前に座らないでよ、と言いたげな顔で私をじろじろと見てくる。
そう思われても後ろはもう空いていないんだもんなぁ……。
気付かないふりをして座って筆記用具を鞄から出していると、クスクスと後ろから笑い声が聞こえてきた。
「バック、やばくない?」
「いくつ? だっさ」
彼女たちが笑っているのは、私がサブバックとして持っていたキルティング素材のトートバックだった。
小学生の時にお母さんが作ってくれたものだ。
ずっとクローゼットの奥に閉まっていたけれど、両親が亡くなった後に形見として再び使い始めた。
うさぎのアップリケが手縫いされたそれは、たしかに大学生が持つには違和感がある。
けど、手に馴染んでいるし、意外に使い勝手もいいから気に入ってるんだけれどなぁ……。
と少ししょんぼりしていると、聡一朗さんが入って来た。
邪魔だから私たちの前に座らないでよ、と言いたげな顔で私をじろじろと見てくる。
そう思われても後ろはもう空いていないんだもんなぁ……。
気付かないふりをして座って筆記用具を鞄から出していると、クスクスと後ろから笑い声が聞こえてきた。
「バック、やばくない?」
「いくつ? だっさ」
彼女たちが笑っているのは、私がサブバックとして持っていたキルティング素材のトートバックだった。
小学生の時にお母さんが作ってくれたものだ。
ずっとクローゼットの奥に閉まっていたけれど、両親が亡くなった後に形見として再び使い始めた。
うさぎのアップリケが手縫いされたそれは、たしかに大学生が持つには違和感がある。
けど、手に馴染んでいるし、意外に使い勝手もいいから気に入ってるんだけれどなぁ……。
と少ししょんぼりしていると、聡一朗さんが入って来た。