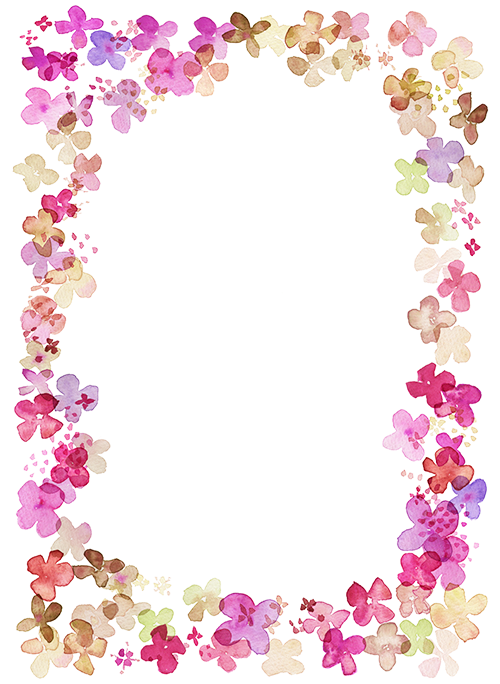聡一朗さんは歌うように推理を巡らす。
「――人付き合いが苦手なのか、単に清掃が好きなのか。前者なら内気に見えるはずだがそうは見えない。清掃が好きなら他のことに気を取られて飲み物をこぼしたりはしない。きっと大学、強いて言えばうちの大学に理由があるのかもしれない――」
詮索されている当人なのに、私は聡一朗さんのするどい洞察力に感激していた。
探偵のように口元に手をやりながら私を見つめるその鋭い視線にドキドキする。
「――うちの大学に執着する理由はなにか。君は絵本に気を取られていた。英語で書かれた絵本。うちには英文学科がある。君は翻訳家になりたいんだね。とりわけ絵本の」
「すごい! なにもかも当たっています!」
「さすが超エリート大学教授先生!」と拍手喝采でついはやし立ててしまって、はっと改める。
「まったくおっしゃる通りです……」
はにかみながらうなずいて、私は両親が死んだこと、大学進学を諦めて翻訳家の夢を一度断念したことを話した。
話し終わると、聡一朗さんはとても感慨深く思っている様子だった。
「――人付き合いが苦手なのか、単に清掃が好きなのか。前者なら内気に見えるはずだがそうは見えない。清掃が好きなら他のことに気を取られて飲み物をこぼしたりはしない。きっと大学、強いて言えばうちの大学に理由があるのかもしれない――」
詮索されている当人なのに、私は聡一朗さんのするどい洞察力に感激していた。
探偵のように口元に手をやりながら私を見つめるその鋭い視線にドキドキする。
「――うちの大学に執着する理由はなにか。君は絵本に気を取られていた。英語で書かれた絵本。うちには英文学科がある。君は翻訳家になりたいんだね。とりわけ絵本の」
「すごい! なにもかも当たっています!」
「さすが超エリート大学教授先生!」と拍手喝采でついはやし立ててしまって、はっと改める。
「まったくおっしゃる通りです……」
はにかみながらうなずいて、私は両親が死んだこと、大学進学を諦めて翻訳家の夢を一度断念したことを話した。
話し終わると、聡一朗さんはとても感慨深く思っている様子だった。