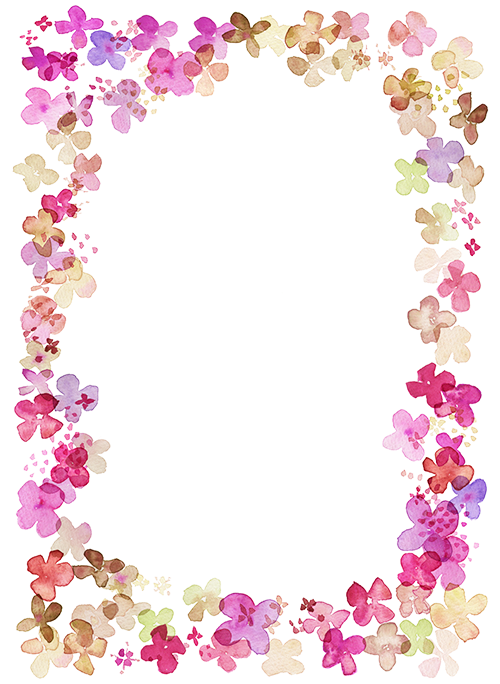「ごめんなさい、ついうれしくて。……実は最初は同情してくださったのかな、と思っていたんです。けど聡一朗さんは私自身の気持ちに気付いてくださっていたんですね」
聡一朗さんは少し間を空けて、どこか遠い昔を思い出すような顔をして、そっと口を開いた。
「同情から始まったのは事実かもな」
「……?」
「同情、と言うか共感と言うのかな」
どういう意味だろう?
聡一朗さんはまた少し間を置くと静かに続けた。
「重なったんだ。君に俺と、俺の姉が」
聡一朗さんと聡一朗さんのお姉さんが?
「今だから言うが、最初に君に会った時にいろいろと詮索してしまったよ。うちに来ている清掃員で若いのは君だけだ。学校にも通わず日中に働いているということは、収入に困っているのだろう。若いから働き先などどこにでもあるはずなのに、わざわざ高収入とは言い難い清掃員を選んだのにも事情があるのだろう――」
聡一朗さんは少し間を空けて、どこか遠い昔を思い出すような顔をして、そっと口を開いた。
「同情から始まったのは事実かもな」
「……?」
「同情、と言うか共感と言うのかな」
どういう意味だろう?
聡一朗さんはまた少し間を置くと静かに続けた。
「重なったんだ。君に俺と、俺の姉が」
聡一朗さんと聡一朗さんのお姉さんが?
「今だから言うが、最初に君に会った時にいろいろと詮索してしまったよ。うちに来ている清掃員で若いのは君だけだ。学校にも通わず日中に働いているということは、収入に困っているのだろう。若いから働き先などどこにでもあるはずなのに、わざわざ高収入とは言い難い清掃員を選んだのにも事情があるのだろう――」