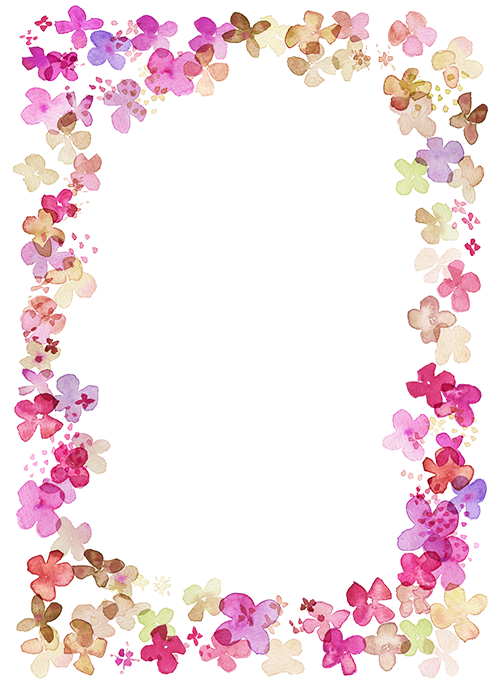「君こそが鍵だったな」
「どういう、意味ですか?」
「君じゃなければ、あの箱は永久に開けられなかった。そして、孤独の殻に閉じこもっていた俺も、解放されることがなかった」
聡一朗さんは、幸せそうに笑った。
「君という鍵が、俺の世界をふたたび色づかせてくれたんだ」
抱き寄せ、私の頬を包んだ。
「愛しているよ。大学教授だなんて偉そうにしているくせにありきたりな言葉しか紡げないのが情けないが、もうこれしか言えないから――。愛している、美良。心の底から君を」
そうして下りてくる唇は、すでに熱を帯び始めていた。
「どういう、意味ですか?」
「君じゃなければ、あの箱は永久に開けられなかった。そして、孤独の殻に閉じこもっていた俺も、解放されることがなかった」
聡一朗さんは、幸せそうに笑った。
「君という鍵が、俺の世界をふたたび色づかせてくれたんだ」
抱き寄せ、私の頬を包んだ。
「愛しているよ。大学教授だなんて偉そうにしているくせにありきたりな言葉しか紡げないのが情けないが、もうこれしか言えないから――。愛している、美良。心の底から君を」
そうして下りてくる唇は、すでに熱を帯び始めていた。