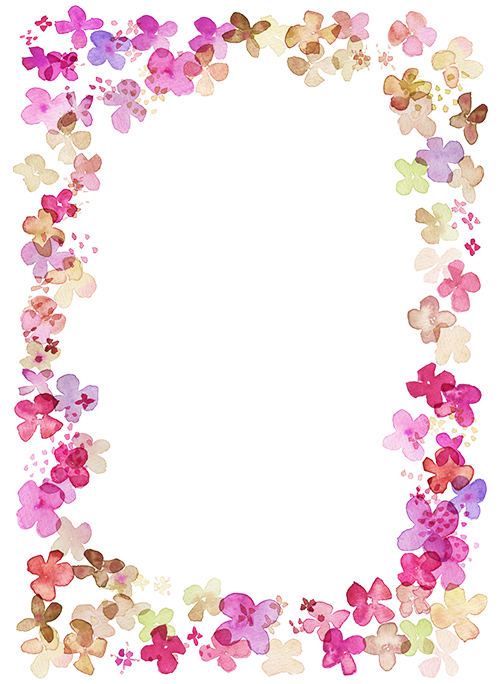そう思って扉に飛びつこうとした時には遅かった。
意地の悪い笑みを浮かべた紗英子さんに閉められ、押しても引いても扉はびくともしなかった。
外から鍵が掛けられたのだ。
「出して! どうしてこんなことするの!?」
「あなたって、ほんとバカで世間知らずのお子様ね」
嘲笑うような声が聞こえた。
「言ってあげてたでしょ、あなたみたいな小娘は先生に相応しくないって。そこで自分のバカさ加減を思い知るといいわ」
「待って、開けて! お願いだから!」
けれどももう声は無かった。
ヒールのコツコツという冷たい音だけが遠ざかっていくのが聞こえた。
意地の悪い笑みを浮かべた紗英子さんに閉められ、押しても引いても扉はびくともしなかった。
外から鍵が掛けられたのだ。
「出して! どうしてこんなことするの!?」
「あなたって、ほんとバカで世間知らずのお子様ね」
嘲笑うような声が聞こえた。
「言ってあげてたでしょ、あなたみたいな小娘は先生に相応しくないって。そこで自分のバカさ加減を思い知るといいわ」
「待って、開けて! お願いだから!」
けれどももう声は無かった。
ヒールのコツコツという冷たい音だけが遠ざかっていくのが聞こえた。