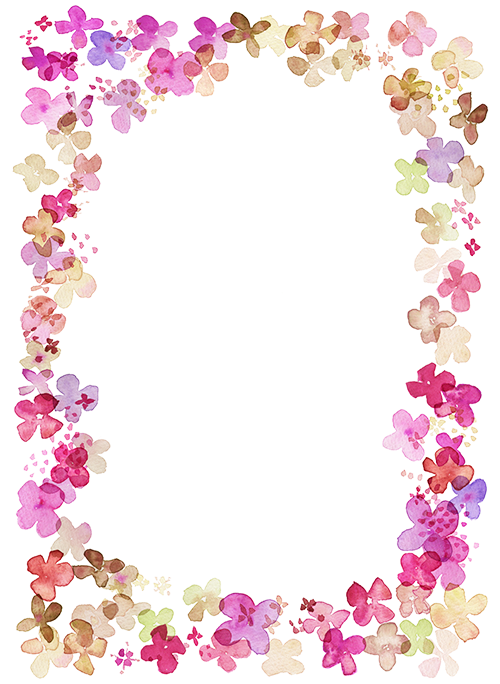「あいつは誰にも心を開かない、誰も自分の内に入り込ませない。でもそれは相手を疎んでいるからじゃない。なによりも自分が嫌いだからなんだよ。お姉さんの苦しみにずっと気付かず、自死に追いやってしまった自分がなによりも憎いからなんだ」
「『自分には愛する資格がない』――聡一朗さんは、私にそう言いました……」
「そうか」
「そんなわけないのに……! 聡一朗さんは私を救ってくれました。お姉さんが聡一朗さんをそうしたように、私のことを厚く援助してくれたんです。聡一朗さんはとても優しくて、誰よりも思いやりがあって……!」
言いながら、涙を抑えることができなかった。
優しさの中にいつも悲しみを隠し持っていた聡一朗さん。
彼は、私を思いやってくれるたびに鈍い痛みに耐えていたのだろうか。
こんな自分に人を思いやる資格はないと、罪悪感で研ぎ澄ませてしまった刃で、自らを傷つけるように。
「『自分には愛する資格がない』――聡一朗さんは、私にそう言いました……」
「そうか」
「そんなわけないのに……! 聡一朗さんは私を救ってくれました。お姉さんが聡一朗さんをそうしたように、私のことを厚く援助してくれたんです。聡一朗さんはとても優しくて、誰よりも思いやりがあって……!」
言いながら、涙を抑えることができなかった。
優しさの中にいつも悲しみを隠し持っていた聡一朗さん。
彼は、私を思いやってくれるたびに鈍い痛みに耐えていたのだろうか。
こんな自分に人を思いやる資格はないと、罪悪感で研ぎ澄ませてしまった刃で、自らを傷つけるように。