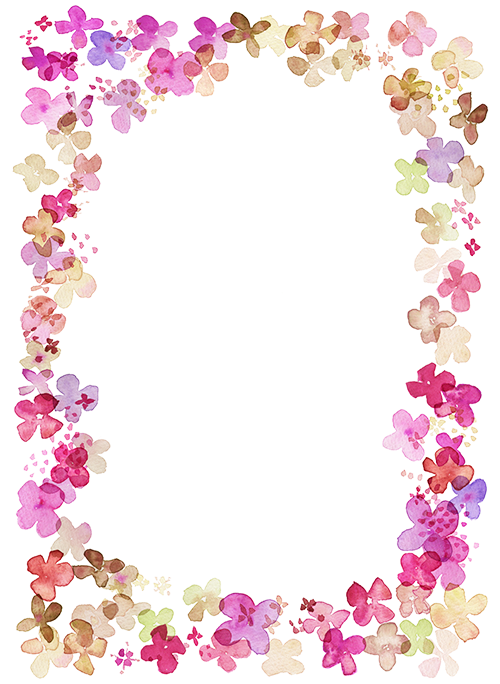「お姉さんのこと、あいつは君にほとんどなにも教えていないのか?」
どこか意味深な言葉に私は素直にうなずいた。
「はい、亡くなったこと以外はなにも」
「ったく、本当になにも知らせてないんだな、あの野郎は。愛しい妻になにやってるんだ」
苦笑いを浮かべつつ、私は内心で「そんな存在ではないからです」と答える。
愛している、と聡一朗さんは言ってくれた。
嬉しかった。
でも、こうしてお姉さんのことを知らせてもらえていない事実を知って、その喜びは小さくしぼむ。
たとえ愛されていても、私は聡一朗さんの心の奥底には分け入らせてもらえない。
一人で背負いこむ孤独を解消してあげられる存在ではないんだ……。
ついうなだれてしまう私を見て、柳瀬さんは少し沈黙した後、意を決したように話し出した。
どこか意味深な言葉に私は素直にうなずいた。
「はい、亡くなったこと以外はなにも」
「ったく、本当になにも知らせてないんだな、あの野郎は。愛しい妻になにやってるんだ」
苦笑いを浮かべつつ、私は内心で「そんな存在ではないからです」と答える。
愛している、と聡一朗さんは言ってくれた。
嬉しかった。
でも、こうしてお姉さんのことを知らせてもらえていない事実を知って、その喜びは小さくしぼむ。
たとえ愛されていても、私は聡一朗さんの心の奥底には分け入らせてもらえない。
一人で背負いこむ孤独を解消してあげられる存在ではないんだ……。
ついうなだれてしまう私を見て、柳瀬さんは少し沈黙した後、意を決したように話し出した。