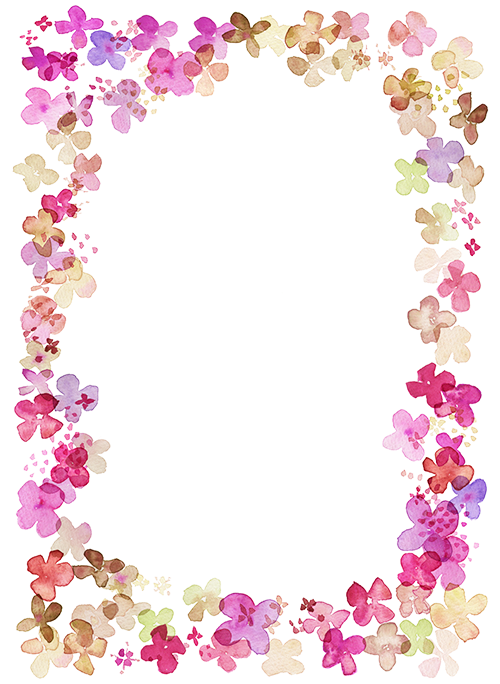「そう、だったんですか……」
命日が近いなんて初めて知った。
聡一朗さんはなにも教えてくれなかった。
忘れていたのか。それとも教える必要はないと思っていたのか……。
言葉を詰まらせている私を見て察したのか、柳瀬さんは気遣うように声を潜めて訊いた。
「聞いてなかったのかい。命日のこと」
「はい……」
柳瀬さんは、ちっと舌打ちした。
「ひとまず、手を合わさせてもらっていいかな」
「はい、どうぞ」
私は仏壇がある部屋に案内した。
柳瀬さんは、線香を添えるとじっと写真を見つめ、長く長く手を合わせた。
そして、最後にもう一度、写真を見つめる。
その真剣な顔には、悲しみが宿っているように見えた。
こうして忙しい合間を縫って手を合わせに来たことからも察することができるけれども、きっと柳瀬さんも、お姉さんとは浅からぬ交流があったのかもしれない。
リビングに戻ってソファに腰を掛けると、柳瀬さんはコーヒーを一口すすって口を開いた。
命日が近いなんて初めて知った。
聡一朗さんはなにも教えてくれなかった。
忘れていたのか。それとも教える必要はないと思っていたのか……。
言葉を詰まらせている私を見て察したのか、柳瀬さんは気遣うように声を潜めて訊いた。
「聞いてなかったのかい。命日のこと」
「はい……」
柳瀬さんは、ちっと舌打ちした。
「ひとまず、手を合わさせてもらっていいかな」
「はい、どうぞ」
私は仏壇がある部屋に案内した。
柳瀬さんは、線香を添えるとじっと写真を見つめ、長く長く手を合わせた。
そして、最後にもう一度、写真を見つめる。
その真剣な顔には、悲しみが宿っているように見えた。
こうして忙しい合間を縫って手を合わせに来たことからも察することができるけれども、きっと柳瀬さんも、お姉さんとは浅からぬ交流があったのかもしれない。
リビングに戻ってソファに腰を掛けると、柳瀬さんはコーヒーを一口すすって口を開いた。