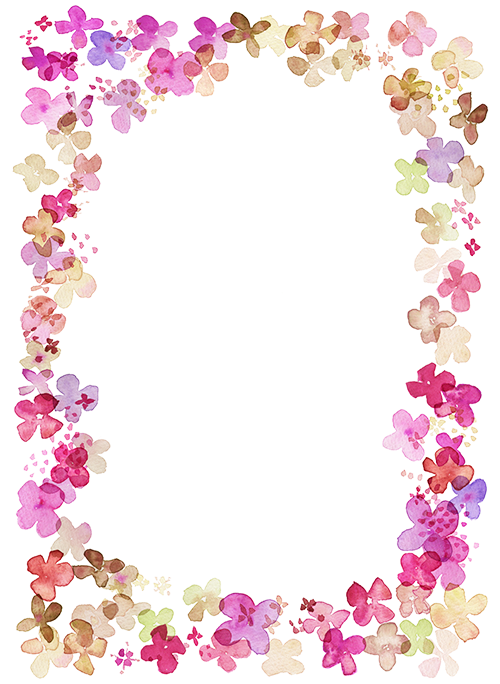気を悪くしただろうか、と思ったのも束の間、聡一朗さんの手が私の頬を撫でた。
そして、親指でやさしく私の唇をなぞる。
そのくすぐったさに笑みを漏らしながら、私は拗ねた顔を浮かべた。
「寂しかったんですよ。ずっと、ずっと。――本当は、今だって、寂しい」
聡一朗さんが急に体勢を変えた。
身を乗り出して、覆いかぶさるように、私と顔を近付ける。
「そうとう酔っているね。君は」
「はい。こんなにたくさん飲んだの、初めてかもしれないです……ふふっ」
どうしてか可笑しくなってきた。
「すごく、ふわふわします。なんだかこうして聡一朗さんとお話している今が、夢みたいなき――」
最後まで言えなかった。
唇を塞がれてしまったから。
そして、親指でやさしく私の唇をなぞる。
そのくすぐったさに笑みを漏らしながら、私は拗ねた顔を浮かべた。
「寂しかったんですよ。ずっと、ずっと。――本当は、今だって、寂しい」
聡一朗さんが急に体勢を変えた。
身を乗り出して、覆いかぶさるように、私と顔を近付ける。
「そうとう酔っているね。君は」
「はい。こんなにたくさん飲んだの、初めてかもしれないです……ふふっ」
どうしてか可笑しくなってきた。
「すごく、ふわふわします。なんだかこうして聡一朗さんとお話している今が、夢みたいなき――」
最後まで言えなかった。
唇を塞がれてしまったから。