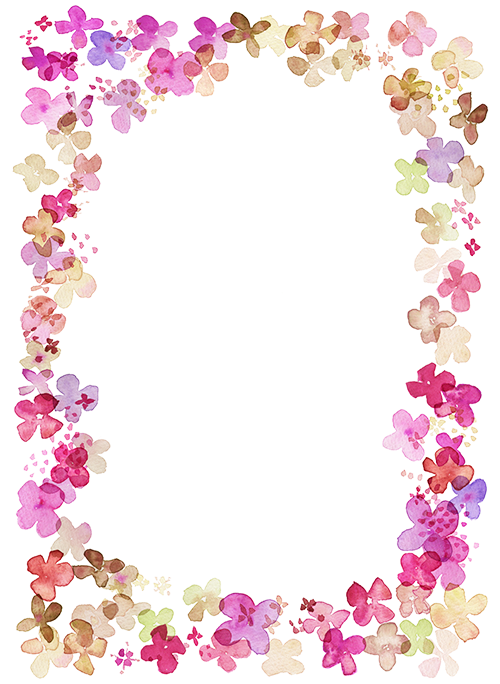手に温もりを感じた。
朦朧としながら伸ばした私の手を、聡一朗さんがやさしく握ってくれたからだ。
ズキズキと痛む頭で思い返す。
そうだ、私は倒れてしまって……。
それからのことは、途切れ途切れの記憶として覚えている。
聡一朗さんが私を抱き止めながら、誰かになにか言って――タクシーに乗せてくれて。
私はずっと聡一朗さんにもたれていて、その間もずっと聡一朗さんは声を掛けてくれたり、やさしく頭を撫でてくれたりした。
そして、お姫様のように抱きかかえて自宅まで運んでくれて……。
朦朧としながら伸ばした私の手を、聡一朗さんがやさしく握ってくれたからだ。
ズキズキと痛む頭で思い返す。
そうだ、私は倒れてしまって……。
それからのことは、途切れ途切れの記憶として覚えている。
聡一朗さんが私を抱き止めながら、誰かになにか言って――タクシーに乗せてくれて。
私はずっと聡一朗さんにもたれていて、その間もずっと聡一朗さんは声を掛けてくれたり、やさしく頭を撫でてくれたりした。
そして、お姫様のように抱きかかえて自宅まで運んでくれて……。