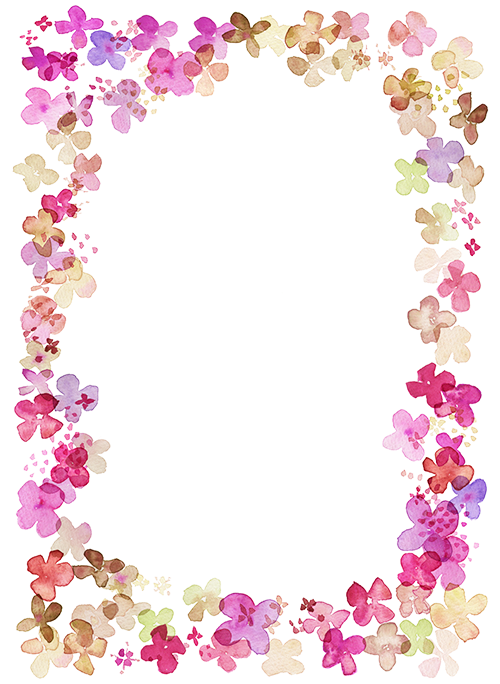突然、それまで親しく会話した人たちが笑顔の仮面を被っているように見えた。
みんな本心では聡一朗さんを妬み、そして私を嘲笑っているのではないか――そんな気がしてきて、息が詰まった。
私は聡一朗さんには釣り合わない。
そんなこと聡一朗さんだって十分解かっている。
私の経歴や若さでなにか言われることは聡一朗さんだって解かっていたはず。
なのに、どうして私なんかを選んだんだろう。
『君を愛することはない』
聡一朗さんの言葉が、ずきりと胸を刺した。
私が聡一朗さんの妻で、本当にいいのだろうか。
「お疲れ様です」
酸素を求めるように廊下に出ると、不意に声を掛けられた。
若い男性の院生の方だった。
みんな本心では聡一朗さんを妬み、そして私を嘲笑っているのではないか――そんな気がしてきて、息が詰まった。
私は聡一朗さんには釣り合わない。
そんなこと聡一朗さんだって十分解かっている。
私の経歴や若さでなにか言われることは聡一朗さんだって解かっていたはず。
なのに、どうして私なんかを選んだんだろう。
『君を愛することはない』
聡一朗さんの言葉が、ずきりと胸を刺した。
私が聡一朗さんの妻で、本当にいいのだろうか。
「お疲れ様です」
酸素を求めるように廊下に出ると、不意に声を掛けられた。
若い男性の院生の方だった。