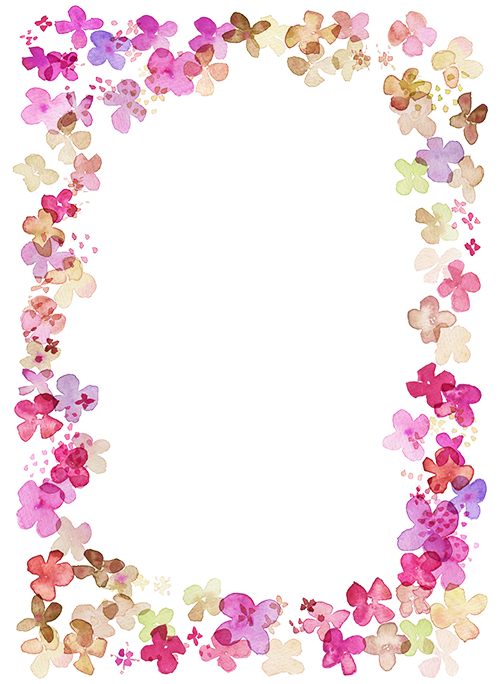聡一朗さんはそれからも大勢の人に囲まれていて、私のもとに戻る余裕がなさそうだった。
談笑している聡一朗さんを見守っていると、どこからか声が聞こえてきた。
「やれやれ、今を時めくとはこのことだな。青二才がいい気なものだ」
ドキっとさせられるような、嫌な声色だった。
「しかも、今日連れて来た嫁を見たか?」
「ああ、まだ子どもじゃないか」
「堅物に見せておいて意外に幼稚趣味だったと見える」
嘲笑を交えて話すのは聡一朗さんのことに違いなかった。
ズキズキと嫌な胸の高鳴りを覚える。
しかも私のことまで話題にしている。
聞かない方がいい、と思っても、つい耳をそばだててしまう。
談笑している聡一朗さんを見守っていると、どこからか声が聞こえてきた。
「やれやれ、今を時めくとはこのことだな。青二才がいい気なものだ」
ドキっとさせられるような、嫌な声色だった。
「しかも、今日連れて来た嫁を見たか?」
「ああ、まだ子どもじゃないか」
「堅物に見せておいて意外に幼稚趣味だったと見える」
嘲笑を交えて話すのは聡一朗さんのことに違いなかった。
ズキズキと嫌な胸の高鳴りを覚える。
しかも私のことまで話題にしている。
聞かない方がいい、と思っても、つい耳をそばだててしまう。