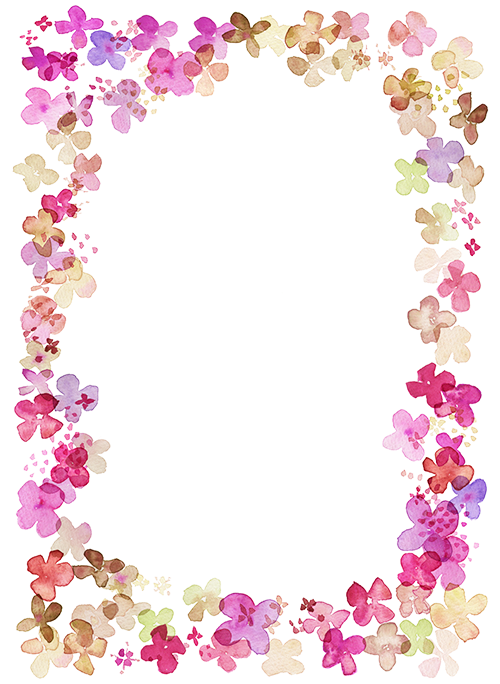「おまえだって女はとっかえひっかえで、結婚なんて微塵も意識してないだろ。俺に呆れる資格はないはずだ」
「はは、それを言われると弱いな。だからまぁ責めることはしないさ。美良ちゃんだってすべて承知でおまえと結婚生活を送っているんだろうからな」
ウィスキーをあおり、アルコールが脳をふわりと麻痺させていくのを感じながら俺はぽつりと言った。
「……別に誰でもいいというわけじゃなかった。彼女だから、結婚したんだ」
「それってつまり、おまえにとって彼女は特別な女ってことだろ」
俺は無言の返答をし、独り言ちるように低い声で言った。
「彼女には『君を愛するつもりはない』と、しかと伝えている。だから好きにして欲しいし、妻として俺に尽くす必要もないとも言いきかせている」
「それって、『俺は誰よりも君を愛してしまっている』って言っちゃっているようにしか聞こえないんだけど」
「……」
「それで? 彼女はなんて言ったんだ」
「それでもいいと。でも自分は妻として俺に尽くしたい。俺の喜ぶ顔が見られればそれでいいと」
「わ」
凌はひとしきり口を付けていたグラスを置いた。
「おまえ、想像以上のいい子だぞ。美良ちゃん」
「……そうだな」
「はは、それを言われると弱いな。だからまぁ責めることはしないさ。美良ちゃんだってすべて承知でおまえと結婚生活を送っているんだろうからな」
ウィスキーをあおり、アルコールが脳をふわりと麻痺させていくのを感じながら俺はぽつりと言った。
「……別に誰でもいいというわけじゃなかった。彼女だから、結婚したんだ」
「それってつまり、おまえにとって彼女は特別な女ってことだろ」
俺は無言の返答をし、独り言ちるように低い声で言った。
「彼女には『君を愛するつもりはない』と、しかと伝えている。だから好きにして欲しいし、妻として俺に尽くす必要もないとも言いきかせている」
「それって、『俺は誰よりも君を愛してしまっている』って言っちゃっているようにしか聞こえないんだけど」
「……」
「それで? 彼女はなんて言ったんだ」
「それでもいいと。でも自分は妻として俺に尽くしたい。俺の喜ぶ顔が見られればそれでいいと」
「わ」
凌はひとしきり口を付けていたグラスを置いた。
「おまえ、想像以上のいい子だぞ。美良ちゃん」
「……そうだな」