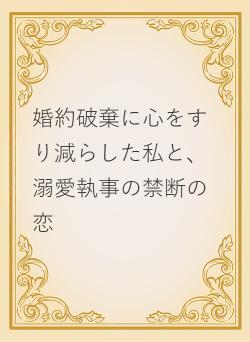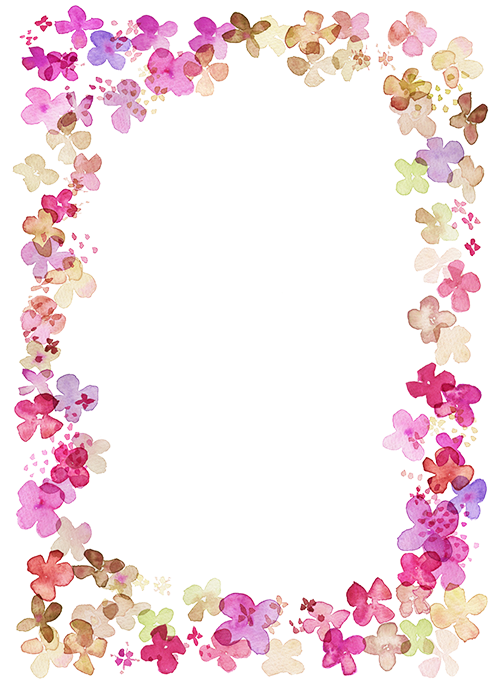私は彼のその気遣いが嬉しく、ぜひにということで髪につけようとする。
でも自分で髪飾りをつけたことがない私はうまく手を後ろに回して自分でつけることができない。
それを見かねたリオネル様は私の手からその髪飾りを受け取ると、そっと優しい手つきで髪につけてくださる。
鏡がないので、自分で似合っているのかどうかわからずむずがゆい思いでいると、その心を読んだかのように彼は言った。
「とても似合っていますよ、クラリス様」
「そう? よかった……」
そうそっけなくいつものように答えているふりをしたけど、内心ちょっとドキッとしていて自分の気持ちを隠すのに必死だった。
彼は私と目が合うと、眩しいほどの笑顔を見せてくれる。
ああ、この笑顔をずっと見ていられたら──
彼の隣にいられたら──
なんて叶わない想いを最近は抱いてしまっている。
きっと国王が私のために婚約者を選んでいるだろうし、きっとこの恋は叶わない。
何より剣の腕を磨いて強くなることを目指していた彼が、国王になりたいと願うはずなんてない。
そうね、今だけ。
でも自分で髪飾りをつけたことがない私はうまく手を後ろに回して自分でつけることができない。
それを見かねたリオネル様は私の手からその髪飾りを受け取ると、そっと優しい手つきで髪につけてくださる。
鏡がないので、自分で似合っているのかどうかわからずむずがゆい思いでいると、その心を読んだかのように彼は言った。
「とても似合っていますよ、クラリス様」
「そう? よかった……」
そうそっけなくいつものように答えているふりをしたけど、内心ちょっとドキッとしていて自分の気持ちを隠すのに必死だった。
彼は私と目が合うと、眩しいほどの笑顔を見せてくれる。
ああ、この笑顔をずっと見ていられたら──
彼の隣にいられたら──
なんて叶わない想いを最近は抱いてしまっている。
きっと国王が私のために婚約者を選んでいるだろうし、きっとこの恋は叶わない。
何より剣の腕を磨いて強くなることを目指していた彼が、国王になりたいと願うはずなんてない。
そうね、今だけ。