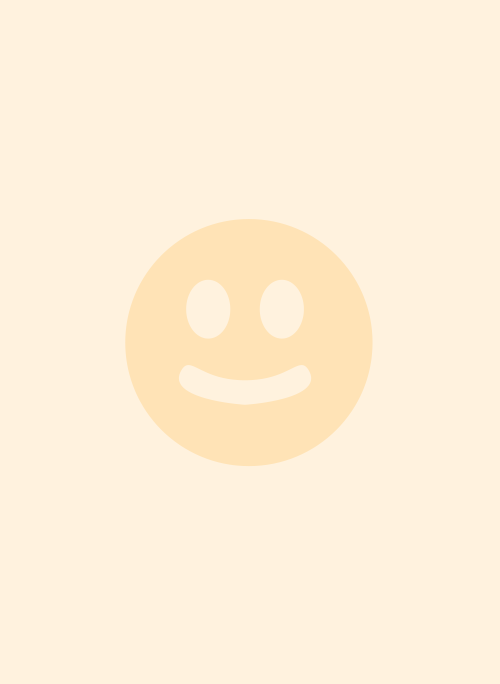ある平凡な日の昼休みに、オレとサトの前であっけらかんという怜。
それにも驚いたけど、それよりもまさかサトがすぐ返事するとも思っていなかった。
「……うん、いいよ」
結局、オレの中学から募らせた恋は敢え無く散った。
だからといって、オレにとってサトは大切な人に変わりはない。
一緒に笑って、怒って。
嫌いになるにはあまりにも思い出がありすぎた。
張り詰めていたものが切れて、ずっと続けたバスケは辞めてしまった。
当然、怜は楽しそうにバスケを続けるといって、バスケ部に入部。
そんな怜を待つサトに付き合っているときだった。
二人が付き合い始めて間もないとき、一度だけサトに聞かれたことがある。
「太一はどう思う?」
どうって、いわれても…。
なんていっていいかわからず答えに惑う。
体育館の出入り口近くの花壇に腰掛けていたオレは視線を落として、無意味に指を動かしていた。
未練がましいオレは、諦めるなんて器用な想いはもてていなくて。
あの時、想いをぶつけていれば……。
もしかしたら変わった『今』があったのかもしれないと、今更ながら思う。
臆病者のオレが出した答え。
「怜、いいやつじゃん。大切にしろよ?」
それにも驚いたけど、それよりもまさかサトがすぐ返事するとも思っていなかった。
「……うん、いいよ」
結局、オレの中学から募らせた恋は敢え無く散った。
だからといって、オレにとってサトは大切な人に変わりはない。
一緒に笑って、怒って。
嫌いになるにはあまりにも思い出がありすぎた。
張り詰めていたものが切れて、ずっと続けたバスケは辞めてしまった。
当然、怜は楽しそうにバスケを続けるといって、バスケ部に入部。
そんな怜を待つサトに付き合っているときだった。
二人が付き合い始めて間もないとき、一度だけサトに聞かれたことがある。
「太一はどう思う?」
どうって、いわれても…。
なんていっていいかわからず答えに惑う。
体育館の出入り口近くの花壇に腰掛けていたオレは視線を落として、無意味に指を動かしていた。
未練がましいオレは、諦めるなんて器用な想いはもてていなくて。
あの時、想いをぶつけていれば……。
もしかしたら変わった『今』があったのかもしれないと、今更ながら思う。
臆病者のオレが出した答え。
「怜、いいやつじゃん。大切にしろよ?」